アライグマ対策に効果的なゴミ置き場の管理【密閉容器の使用がカギ】地域で取り組む3つの改善ポイント

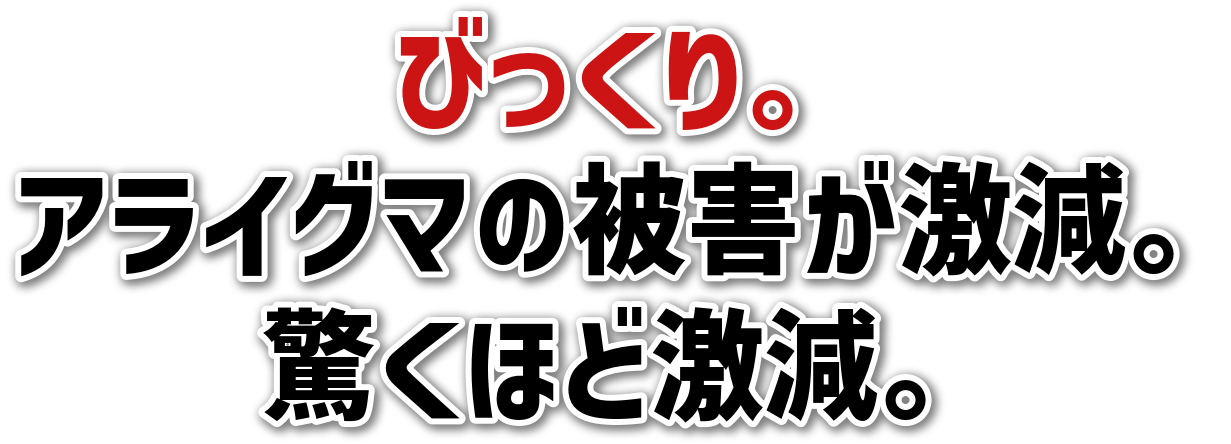
【この記事に書かれてあること】
アライグマのゴミ荒らしに悩まされていませんか?- アライグマのゴミ荒らし被害が深刻化
- 密閉容器の正しい選び方と使用法が重要
- ゴミ収集日とアライグマの活動時間の調整が必要
- 住民の協力体制で被害を大幅に軽減可能
- 清掃頻度と方法の見直しで衛生問題を解決
- 5つの裏技でアライグマを寄せ付けない環境作り
実は、ゴミ置き場の管理方法を見直すだけで、被害を大幅に減らせるんです。
密閉容器の選び方から、住民の協力体制作りまで、誰でも今すぐ始められる対策をご紹介します。
さらに、香辛料や光・音を使った驚きの裏技も。
「もうアライグマには負けない!」そんな自信が持てる具体策が満載。
ゴミ置き場の悩みを解決し、快適な住環境を取り戻すヒントがここにあります。
さあ、アライグマ撃退作戦の始まりです!
【もくじ】
アライグマのゴミ荒らし被害の実態と影響

ゴミ置き場が狙われる「3つの理由」を知ろう!
ゴミ置き場がアライグマに狙われる理由は、餌、隠れ場所、アクセスの容易さの3つです。まず、ゴミ置き場は、アライグマにとって格好の「食事処」なんです。
「わぁ!こんなところに美味しそうな物がたくさんあるぞ!」とアライグマは大喜び。
生ゴミや食べ残しは、彼らにとって魅力的な餌となります。
次に、ゴミ箱や周辺の物陰は、絶好の「隠れ家」になるんです。
「ここなら安全に食事ができるぞ」とアライグマは考えます。
人目を気にせず、ゆっくりと食事を楽しめる環境が整っているわけです。
最後に、多くのゴミ置き場は「アクセスが簡単」なんです。
「こんなに簡単に入れるなんて、ラッキー!」とアライグマは喜びます。
低い柵や開けっ放しの蓋は、彼らにとって侵入の障害にはなりません。
- 豊富な餌源:生ゴミや食べ残し
- 安全な隠れ場所:ゴミ箱や周辺の物陰
- 簡単なアクセス:低い柵や開いた蓋
だからこそ、私たちは賢明な対策を講じる必要があるのです。
アライグマの夜間活動とゴミ荒らしの関係性
アライグマの夜行性と、私たちのゴミ出しの習慣がピッタリ一致してしまうのです。これがゴミ荒らしの大きな原因となっています。
アライグマは日が暮れてから活動を始めます。
「よーし、今夜も美味しいものを探しに行くぞ!」と意気込むのです。
一方、多くの家庭では夕食後や寝る前にゴミを出す習慣がありますよね。
「明日の朝、ゴミ収集車が来るから今のうちに出しておこう」という具合に。
この人間とアライグマの行動パターンが見事に重なり、ゴミ荒らしの絶好の機会を生み出しているんです。
夜中、静かな住宅街。
人々が眠りについたころ、アライグマたちの「ゴチソウ」タイムが始まるわけです。
- アライグマの活動時間:日没後〜夜明け前
- 一般的なゴミ出し時間:夕方〜夜
- ゴミ収集時間:早朝
「人間さんたち、わざわざ夜に美味しいものを並べてくれてありがとう!」なんてアライグマは喜んでいるかもしれません。
だからこそ、私たちのゴミ出しのタイミングを見直すことが、アライグマ対策の第一歩となるのです。
夜間のゴミ出しを避け、朝の収集直前に出すなど、ちょっとした工夫で大きな効果が期待できるんです。
ゴミ荒らしがもたらす「衛生問題」に要注意
アライグマのゴミ荒らしは、見た目の汚さだけでなく、深刻な衛生問題を引き起こす可能性があるんです。それは私たちの健康にも直接影響を及ぼしかねません。
まず、ゴミを散らかすことで、悪臭が発生します。
「うわっ、なんだこの臭い!」と鼻をつまみたくなるような強烈な匂いが漂うことも。
この悪臭は単に不快なだけでなく、周辺住民のストレスの原因にもなりかねません。
さらに厄介なのが、病原体の拡散です。
アライグマの糞尿には、様々な細菌やウイルスが含まれている可能性があるんです。
これらが食べ物の残りかすと混ざることで、危険な病原体の温床となってしまいます。
- 悪臭の発生:腐敗した食べ物や糞尿の匂い
- 病原体の拡散:アライグマが運ぶ細菌やウイルス
- 害虫の増加:ゴミに引き寄せられるハエや蚊
- アレルギー反応:アライグマの毛や糞による刺激
ハエや蚊が増えれば、さらなる衛生リスクが高まります。
「あれ?最近蚊に刺されることが多くなったな」なんて感じたら要注意です。
そして見逃せないのが、アレルギー反応の可能性。
アライグマの毛や糞に含まれる物質が、喘息やアレルギー性鼻炎を引き起こすこともあるんです。
これらの衛生問題は、私たちの日常生活に静かに、しかし確実に影響を与えています。
だからこそ、アライグマのゴミ荒らし対策は、単なる美観の問題ではなく、健康を守るための重要な取り組みなんです。
近隣トラブルの原因に!ゴミ荒らしの二次被害
アライグマのゴミ荒らしは、思わぬところで近隣トラブルの種になってしまうんです。その影響は、単なるゴミの散乱だけにとどまらないのです。
まず、散らかされたゴミの責任問題が浮上します。
「誰のゴミだ?」「誰が片付けるんだ?」といった声が聞こえてきそうです。
特に共同住宅や集合住宅では、この問題が深刻化しやすいんです。
次に、清掃の負担増加が挙げられます。
毎朝のようにゴミを片付ける羽目になれば、誰だって気分が悪くなりますよね。
「また今朝もゴミが散らかってる…」とため息をつく日々が続けば、住民同士の関係にも影響が出かねません。
さらに、悪臭問題も無視できません。
アライグマが荒らしたゴミから発生する臭いは、近隣住民の不快感を募らせます。
「隣の家のゴミ臭いよ!」なんて苦情が飛び交えば、住民同士の関係はギクシャクしてしまいます。
- ゴミの責任問題:誰のゴミか、誰が片付けるか
- 清掃負担の増加:毎日の片付けによるストレス
- 悪臭問題:散乱したゴミからの不快な臭い
- 防犯意識の低下:ゴミ荒らしを放置することによる影響
- 地域イメージの悪化:清潔さや管理状態への不信感
ゴミ荒らしを放置することで、「この地域は管理が行き届いていない」という印象を与えかねません。
これが不審者を引き寄せる原因にもなりうるのです。
最終的には、地域全体のイメージダウンにつながる可能性もあります。
清潔さや管理状態に疑問を感じた人々が、その地域から離れていってしまうかもしれません。
このように、アライグマのゴミ荒らしは、思わぬ形で人々の関係性や地域の雰囲気を損なう可能性があるのです。
だからこそ、地域ぐるみでこの問題に取り組むことが大切なんです。
放置厳禁!ゴミ荒らしで「資産価値低下」の危険性
アライグマのゴミ荒らしを放置すると、なんと家や土地の資産価値が下がってしまう可能性があるんです。これは多くの人が見落としがちな、しかし非常に重要な問題なんです。
まず、ゴミ荒らしが常態化すると、その地域全体のイメージが悪化します。
「この辺りはゴミだらけで臭いよね」なんて噂が立てば、たちまち不動産の評価は下がってしまいます。
きれいな街並みは、資産価値を保つ重要な要素なんです。
また、ゴミ荒らしは害虫や有害動物を引き寄せる原因にもなります。
「あの家の周りにはゴキブリがよく出るらしいよ」なんて話が広まれば、もう終わりです。
衛生面での不安は、不動産価値を大きく損なう要因になるんです。
さらに、継続的なゴミ荒らしは建物自体にもダメージを与えます。
アライグマが建物に侵入しようとして、外壁や屋根を傷つけることもあるんです。
「修繕が必要な家」というレッテルは、即座に資産価値の低下につながります。
- 地域イメージの悪化:清潔感の欠如による評価低下
- 害虫・有害動物の増加:衛生面での不安要素
- 建物への物理的ダメージ:修繕必要性による価値低下
- 近隣関係の悪化:トラブルによる住みにくさ
- 将来的な開発計画への影響:投資価値の減少
ゴミ荒らしをきっかけに住民同士のトラブルが増えれば、「住みにくい地域」というレッテルを貼られかねません。
これも不動産価値を下げる大きな要因となるんです。
最終的には、その地域の将来的な開発計画にも影響を及ぼす可能性があります。
「問題のある地域」とみなされれば、新たな投資や開発が敬遠されるかもしれません。
これは長期的に見て、資産価値の上昇を妨げる要因となるのです。
このように、一見些細に思えるゴミ荒らしの問題が、実は私たちの大切な資産にまで影響を及ぼす可能性があるんです。
だからこそ、早めの対策が重要なんです。
「我が家の価値は我が手で守る」という意識を持つことが、実は賢い投資なのかもしれません。
効果的なゴミ置き場管理の具体策

密閉容器の選び方と「正しい使用法」を押さえよう
アライグマ対策の要は、頑丈で密閉性の高い容器を選ぶことです。まず、容器選びのポイントをおさえましょう。
「こんな容器を選べば安心!」というものがあるんです。
- 材質は金属製が理想的
- 蓋はロック機能付きのもの
- 重量感のあるタイプを選ぶ
- 容量は家族の人数に合わせて
プラスチック製だと、ガリガリと噛まれて穴を開けられちゃうかも。
ロック機能付きの蓋なら、「カチッ」と音がするまでしっかり閉めることで、不意に開くこともありません。
重量感のある容器を選ぶのも大切です。
軽すぎると、アライグマに倒されてしまう可能性が。
「えいっ!」と押しても動かないくらいの重さが理想的です。
容量は、ゴミを溜め込まないためにも、2、3日で一杯になる程度を目安に。
「ゴミ、増えちゃったな〜」と思ったら、追加で容器を購入するのもいいでしょう。
使い方も重要です。
毎回使用後は必ず蓋をロックすること。
「ちょっとの間だから…」は禁物です。
アライグマは隙あらばやってきますからね。
また、容器の周りはいつもキレイにしておきましょう。
ポイ捨てされたゴミや食べこぼしがあると、それだけでアライグマを引き寄せてしまいます。
「ピカピカのゴミ置き場」を心がけるのが、アライグマ対策の第一歩なんです。
ゴミ収集日vs夜行性!タイミング調整の重要性
アライグマ対策で忘れてはいけないのが、ゴミの出すタイミングです。これがバッチリ合えば、被害はグンと減らせるんです。
アライグマは夜行性。
日が沈むとゴソゴソ活動を始めます。
「さあて、今夜もごちそうを探しに行くぞ〜」なんて感じでしょうか。
一方、多くの地域でゴミ収集は朝。
この時間のズレが、アライグマにとっては格好の「食事時間」になっているんです。
じゃあ、どうすればいいの?
答えは簡単。
ゴミは収集日の朝に出すことです。
「え〜、面倒くさい…」なんて思う人もいるかもしれません。
でも、これが最も効果的な対策なんです。
具体的には、こんな感じで行動してみましょう。
- 前日の夜にゴミを出さない
- 収集時間の30分前くらいにゴミを出す
- 長期休暇中は近所で協力してゴミ出しをする
その気持ち、よーくわかります。
でも、ちょっと早起きして時間を作る価値は十分にあるんです。
毎朝ゴミが散らかっている光景を見るよりずっといいですよね。
長期休暇中の対策も忘れずに。
お隣さんと「留守中はゴミ出し協力し合おう」と約束しておけば安心です。
ご近所付き合いも深まって一石二鳥かも?
この「タイミング戦略」で、アライグマに「ちぇっ、今日もゴミがないぞ」と言わせちゃいましょう。
コツコツ続ければ、きっとアライグマも諦めて別の場所に行っちゃうはず!
住民の協力体制「5つのルール」で被害激減
アライグマ対策、実は住民の協力がカギなんです。「えっ、私たちにできることなんてあるの?」って思うかもしれません。
でも、大丈夫。
簡単な「5つのルール」を守るだけで、被害はグンと減らせるんです。
では、その魔法の5つのルールをご紹介しましょう!
- ゴミは決められた時間に出す
- ゴミ箱の蓋は必ず閉める
- ゴミ置き場の周りはいつもキレイに
- アライグマの目撃情報を共有する
- 定期的に対策会議を開く
「あ、明日ゴミの日だった!」と夜中に慌てて出すのはNG。
朝一番がベストです。
蓋の閉め忘れも要注意。
「ちょっとくらい…」が命取り。
アライグマは小さな隙も見逃しません。
カチッと音がするまでしっかり閉めましょう。
ゴミ置き場の周りの掃除も大切。
食べこぼしや散らかったゴミは、アライグマにとって「ウェルカム」のサインと同じです。
みんなで協力して、いつもピカピカに保ちましょう。
目撃情報の共有も効果的。
「昨日、庭にアライグマが出たよ」なんて情報、すぐに広めることが大事です。
住民同士で連絡網を作るのもいいかもしれません。
そして、定期的な対策会議。
「今月はアライグマの被害減ったね」「〇〇さん家の対策、効果あったみたい」なんて情報交換の場を持つことで、地域全体の対策レベルがアップします。
これらのルールを守るのは、正直面倒くさいかもしれません。
でも、「我が家だけ」じゃなく「みんなで」取り組むことで、効果は倍増するんです。
さあ、あなたの地域でも、アライグマ撃退作戦を始めてみませんか?
清掃頻度と方法の見直しで「根本解決」へ
アライグマ対策の重要ポイント、それは徹底的な清掃なんです。「え?掃除するだけでいいの?」って思うかもしれません。
でも、これが実は大きな効果を生むんです。
まず、清掃の頻度について考えてみましょう。
週に1回じゃ足りません。
毎日の清掃が理想的です。
「えー、毎日なんて無理!」って声が聞こえてきそうですね。
でも、ちょっと待ってください。
実は5分程度で十分なんです。
具体的な清掃方法を見てみましょう。
- ゴミ箱の内外を消毒液で拭く
- 周辺の地面を掃く
- 食べこぼしや散らかったゴミを拾う
- 異臭がある場合は重点的に洗浄する
アライグマは嗅覚が鋭いので、消毒液の匂いは彼らを寄せ付けません。
「シュッシュッ」と吹きかけて、サッと拭くだけでOK。
地面を掃くのも忘れずに。
小さなゴミや食べかすが残っていると、それだけでアライグマを引き寄せてしまいます。
「ここにはご馳走がありそうだぞ」なんて思わせちゃダメです。
異臭には特に注意が必要です。
生ゴミの匂いは、アライグマにとっては「おいしそう〜」のサイン。
匂いの元をしっかり洗い流しましょう。
清掃時の服装も大切です。
手袋とマスクは必須。
アライグマの糞尿には病原菌がいることもあるので、直接触れないように注意が必要です。
「毎日の清掃、大変そう…」なんて思った人もいるかもしれません。
でも、家族や近所の人と当番制にすれば、それほど負担にはなりません。
むしろ、ご近所付き合いのきっかけになるかも?
この清掃習慣、続けていくうちに、きっとアライグマは「この場所には美味しいものがないな」と学習して、別の場所に行ってしまうはずです。
根気よく続けることが、アライグマ対策の「根本解決」への近道なんです。
アライグマvs野良猫!群れ行動の違いと対策法
アライグマと野良猫、一見似ているようで実は大きく違うんです。この違いを知ることで、より効果的な対策が打てるんですよ。
まず、行動パターンの違いから見ていきましょう。
アライグマは基本的に単独行動。
「俺様は一匹狼だぜ!」って感じでしょうか。
一方、野良猫は群れを作ることがあります。
「みんなでワイワイするのが好き♪」みたいな感じですね。
この違い、対策にどう活かせるでしょうか?
- 餌の量:アライグマ対策は少量でOK
- 侵入経路:アライグマは高所も利用
- 活動範囲:アライグマはより広範囲
- 音への反応:アライグマは警戒心が強い
大量の餌を用意する必要はありません。
侵入経路は要注意。
アライグマは木登りが得意で、高い場所からも侵入してきます。
「2階の窓から入ってくるなんて…」なんてことも。
野良猫対策より、上方にも気を配る必要があります。
活動範囲も違います。
アライグマはより広い範囲を動き回ります。
だから、ご近所全体で対策を講じることが大切。
「うちの庭だけキレイにしても…」じゃ不十分なんです。
音への反応も異なります。
アライグマは警戒心が強いので、突然の大きな音にビックリして逃げちゃいます。
この特性を利用して、音を出す装置を設置するのも効果的。
でも、共通点もあります。
どちらも夜行性で、食べ物に引き寄せられやすいこと。
だから、夜間のゴミ出しは絶対NG。
食べ残しも放置厳禁です。
こうした違いを理解することで、「あれ?アライグマ対策したのに、野良猫が来るようになっちゃった…」なんて事態も避けられます。
それぞれの特性に合わせた対策を講じることで、両方から我が家を守ることができるんです。
さあ、アライグマと野良猫、どちらにも負けない対策を始めましょう!
ゴミ置き場のアライグマ対策「5つの裏技」

香辛料の力でアライグマを寄せ付けない!
アライグマを撃退する強力な武器、それが香辛料なんです。アライグマは鋭い嗅覚の持ち主。
だからこそ、強烈な香りには弱いんです。
特に効果的なのが、唐辛子パウダー。
「ヒリヒリする〜!」とアライグマも逃げ出しちゃうんです。
使い方は簡単。
ゴミ箱の周りに適量をふりかけるだけ。
ただし、風で飛ばされないよう、地面にしっかりとまぶすのがコツです。
他にも、ブラックペッパーやシナモンも効果があります。
これらをゴミ箱の周りに置いておくだけでも、アライグマは「うわっ、こんな臭いところには近づきたくない!」と思うはずです。
- 唐辛子パウダー:最強の威力を発揮
- ブラックペッパー:刺激的な香りでアライグマを撃退
- シナモン:甘くて強い香りが効果的
- ニンニクパウダー:独特の臭いがアライグマを遠ざける
雨が降ると効果が薄れてしまうので、定期的に補充する必要があります。
また、風の強い日は近所に飛んでいってしまう可能性もあるので、使用量には気をつけましょう。
「でも、香辛料って高くないの?」なんて心配する方もいるかもしれません。
大丈夫です。
スーパーの安売りコーナーや、業務用スーパーを利用すれば、比較的安価に手に入りますよ。
この方法、実は一石二鳥なんです。
アライグマ対策になるだけでなく、ゴミ置き場周辺の虫よけにも効果があるんです。
「害虫も寄ってこなくなった!」なんて嬉しい副効果も期待できます。
香辛料の力で、アライグマに「ここはダメだ〜」と思わせちゃいましょう。
きっと彼らも、もっと居心地の良い場所を探しに行くはずです。
光と音の組み合わせで「24時間警戒」態勢
アライグマは夜行性。だからこそ、光と音を使った対策が効果的なんです。
これで24時間態勢の「アライグマよけシステム」が作れちゃいます。
まずは光の対策から。
発光ダイオードを使った動きに反応するセンサーライトがおすすめです。
アライグマが近づくと「パッ」と明るく照らすので、「うわっ、見つかっちゃった!」とびっくりして逃げ出すんです。
次は音の出る装置。
人の声が録音された機械や、不規則な音を出す装置が効果的です。
「ここに人がいるぞ!」とアライグマに思わせるわけです。
この2つを組み合わせると、さらに効果抜群。
例えば、こんな感じです。
- アライグマが近づく
- センサーが反応して明るく照らす
- 同時に音声が流れる
- アライグマが「危険だ!」と感じて逃げ出す
夜中に大音量で鳴り響いたら、ご近所さんから苦情が来ちゃうかもしれません。
また、電池式の場合は定期的な交換も忘れずに。
「せっかく設置したのに電池切れで動かなかった」なんてことにならないよう注意が必要です。
この方法、実は他の野生動物対策にも使えるんです。
タヌキやハクビシンなども、同じように光と音に反応して逃げ出します。
「一石二鳥どころか、一石三鳥!」なんて嬉しい効果も。
光と音の力で、アライグマに「ここは危険な場所だ」と学習させちゃいましょう。
きっと彼らも、もっと安全な場所を探しに行くはずです。
ゴミ箱周辺の地面改良で「侵入困難」に
アライグマの足元対策、実はこれが意外と効果的なんです。彼らは歩きやすい場所を好むので、足元を不快にすれば「ここは歩きにくいな」と避けてくれるんです。
まず、おすすめなのが砂利敷き。
小石をゴミ箱の周りに敷き詰めるんです。
アライグマにとっては、ゴツゴツした地面は歩きづらいんです。
「痛いよ〜」って感じでしょうか。
次に効果的なのが、金網の設置。
地面に水平に金網を敷き、その上に土や砂利を被せるんです。
アライグマが歩くと、金網がグラグラして不安定に。
「こわっ!歩けない!」ってなっちゃうんです。
他にも、こんな方法があります。
- トゲトゲした植物を植える:バラやサボテンなどが効果的
- 滑りやすい素材を使う:金属板や滑らかな石を敷き詰める
- 水たまりを作る:アライグマは水を嫌がる傾向がある
あまりにも歩きにくくすると、ゴミ出しの時に人間も困っちゃいます。
「アライグマは来なくなったけど、自分も転びそう…」なんてことにならないよう、バランスが大切です。
また、定期的なメンテナンスも忘れずに。
砂利が散らばったり、金網が露出したりしないよう、時々チェックが必要です。
この方法、実は見た目もスッキリするんです。
「ゴミ置き場がおしゃれになった!」なんて、思わぬ副効果も。
地域の景観向上にも一役買えちゃいます。
アライグマに「ここは歩きにくいぞ」と思わせて、自然と遠ざかってもらいましょう。
きっと彼らも、もっと快適な場所を探しに行くはずです。
天敵の匂いで「本能的な恐怖」を呼び起こす
アライグマを追い払う強力な武器、それが天敵の匂いなんです。本能的な恐怖心を呼び起こして、アライグマを遠ざけちゃうんです。
特に効果的なのが、オオカミの尿の匂い。
「えっ、そんなの手に入るの?」って思いますよね。
実は、人工的に作られたスプレーが市販されているんです。
これをゴミ箱の周りに吹きかけるだけで、アライグマは「ヤバイ!オオカミがいる!」と勘違いして逃げ出すんです。
他にも、こんな天敵の匂いが効果的です。
- クマの匂い:強烈な恐怖を与える
- キツネの匂い:警戒心を高める
- 大型猛禽類の匂い:空からの攻撃を連想させる
スプレーをゴミ箱の周りや、アライグマが通りそうな場所に吹きかけるだけ。
ただし、雨が降ると効果が薄れるので、定期的に補充する必要があります。
注意点もあります。
これらの匂いは人間にも結構強烈です。
「アライグマは来なくなったけど、自分も近づきたくない…」なんてことにならないよう、使用量には気をつけましょう。
また、家庭で飼っているペットにも影響を与える可能性があります。
特に犬は敏感に反応するかもしれません。
「ワンちゃんが急におびえだした!」なんてこともあり得るので、ペットがいる家庭では使用を控えめにするのがいいでしょう。
この方法、実は他の野生動物対策にも効果があるんです。
タヌキやハクビシンなども、同じように天敵の匂いを嫌がります。
「一石二鳥」どころか「一石三鳥」の効果が期待できるかも。
天敵の匂いで、アライグマの本能的な恐怖心を刺激しちゃいましょう。
きっと彼らも、もっと安全だと感じる場所を探しに行くはずです。
「自動閉鎖システム」でうっかり開放を防止
ゴミ箱の蓋、開けっ放しになっていませんか?これが意外とアライグマを招き入れる原因なんです。
でも、大丈夫。
「自動閉鎖システム」を使えば、この問題を解決できちゃいます。
このシステム、実はとってもシンプル。
バネの力を利用して、蓋が自動的に閉まるようにするんです。
使い方は簡単。
ゴミを入れたら手を離すだけ。
「カチッ」と音がして、しっかり閉まります。
自作するなら、こんな方法があります。
- バネを取り付ける:蝶番にバネを付けて引き戻す力を加える
- 重り式:蓋の裏側におもりを付けて自然に閉まるようにする
- 滑車システム:滑車を使って蓋を引き上げる仕組みを作る
ゆっくりと確実に閉まるので、「バタン!」という音で近所に迷惑をかける心配もありません。
ただし、注意点もあります。
機械なので、時々メンテナンスが必要です。
バネの張りが弱くなったり、油圧が効かなくなったりすることもあるので、定期的なチェックを忘れずに。
また、力の加減も大切。
強すぎると子供やお年寄りが開けられなくなっちゃうかも。
「ゴミ捨てるのに筋トレが必要になっちゃった!」なんてことにならないよう、調整が必要です。
この方法、実は他のメリットもあるんです。
雨風が入りにくくなるので、ゴミ置き場の衛生状態が保てます。
「臭いも減った!」なんて嬉しい効果も期待できるかも。
自動閉鎖システムで、アライグマに「ここは開かないぞ」とガッカリさせちゃいましょう。
きっと彼らも、もっと簡単に開けられる場所を探しに行くはずです。
うっかり開放、これで完全防止!