アライグマのゴミ箱あさり対策【夜間の食べ残しが誘因】簡単にできる3つのゴミ箱管理テクニックを紹介

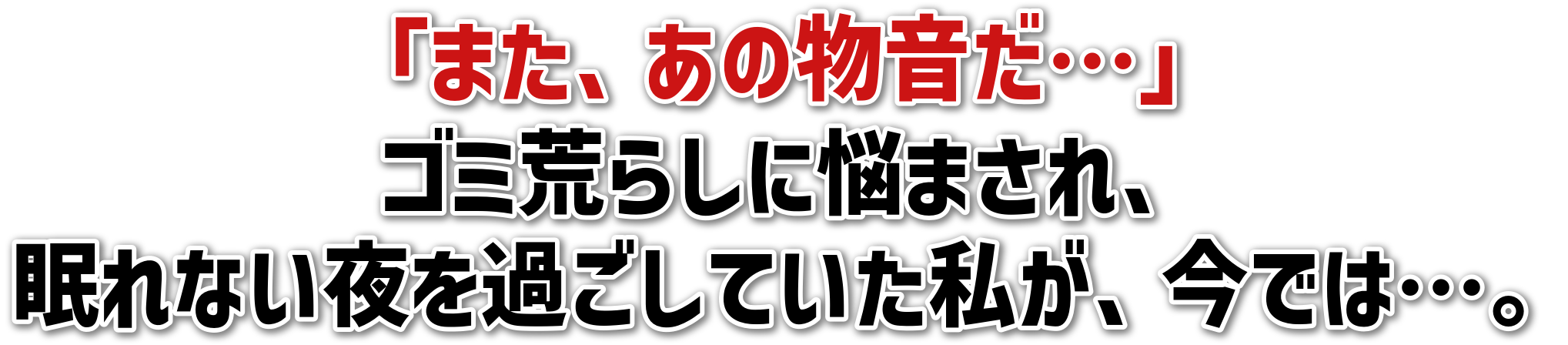
【この記事に書かれてあること】
毎朝、散らかったゴミを片付けるのにうんざりしていませんか?- アライグマによるゴミ箱あさり被害の実態と深刻さ
- 頑丈なゴミ箱の選び方と効果的な設置方法
- 光や音を使ったアライグマ撃退テクニック
- アライグマの嗅覚能力を考慮した対策の重要性
- 10の驚きの裏技でアライグマを寄せ付けない方法
アライグマによるゴミ箱あさりは、単なる面倒事ではありません。
衛生問題や近隣トラブルにも発展しかねない深刻な問題なのです。
でも、安心してください。
この記事では、アライグマのゴミ箱あさりを撃退する10の驚きの裏技をご紹介します。
頑丈なゴミ箱の選び方から、意外な日用品を使った対策まで、すぐに実践できる方法が満載です。
これらの対策を実践すれば、きっとアライグマとの戦いに勝利できるはずです。
さあ、一緒にアライグマ撃退作戦を始めましょう!
【もくじ】
アライグマのゴミ箱あさり問題と深刻な被害

アライグマが引き起こす「夜間の騒音被害」に注意!
夜中にガタガタ音がして目が覚める…そんな経験ありませんか?実はこれ、アライグマによるゴミ箱あさりが原因かもしれません。
アライグマは夜行性の動物で、深夜に活動します。
ゴミ箱をあさる際に出す音は、思いのほか大きいんです。
「ガシャン!ガタガタ…」
こんな音が毎晩続くと、睡眠不足に悩まされることも。
アライグマは器用な手先を持ち、ゴミ箱の蓋を開けたり、中身をひっくり返したりするのが得意です。
その結果、金属製のゴミ箱がぶつかり合う音や、中身が散らばる音が発生します。
特に静かな住宅街では、この騒音が目立ちます。
近所迷惑にもなりかねません。
「うちの家族はゴミの出し方が悪いんじゃないか」と誤解を受けることも。
- 深夜0時〜朝4時頃が最も活発
- 金属音や物が倒れる音が特徴的
- 継続的な騒音で睡眠の質が低下
長期的な睡眠不足は、日中の集中力低下や体調不良につながりかねません。
早めの対策が大切です。
まずは、ゴミ箱の置き場所を見直してみましょう。
家から離れた場所に移動させるだけでも、騒音被害は軽減できます。
また、しっかりとした蓋つきのゴミ箱を使用するのも効果的。
アライグマが簡単に開けられないようにすれば、騒音も減らせるというわけです。
ゴミ箱あさりによる「衛生問題と悪臭」の実態
ゴミ箱あさりの後始末、面倒くさいですよね。でも、放っておくとどうなるか想像してみてください。
そう、衛生問題と悪臭の温床になっちゃうんです。
アライグマがゴミをあさった跡は、まるで台風が通り過ぎたよう。
生ゴミが散らばり、腐敗が進みます。
特に夏場は要注意。
高温多湿の環境で、バクテリアの繁殖スピードが加速します。
「うわっ、なんだこの臭い!」
朝起きて外に出たら、強烈な悪臭が漂っている…。
そんな経験をした人も多いのではないでしょうか。
腐敗した生ゴミの匂いは、想像以上に強烈です。
近所の人から苦情が来るのも無理はありません。
衛生面でも大問題です。
散らかったゴミは、ハエやゴキブリなどの害虫を引き寄せます。
さらに、アライグマの糞尿にも注意が必要。
寄生虫や病原菌が含まれている可能性があるんです。
- 生ゴミの腐敗による悪臭発生
- 害虫の温床になりやすい
- アライグマの糞尿による感染症リスク
- 近隣トラブルの原因に
アライグマが開けられないよう、重石を乗せるのも効果的。
また、こまめな清掃も大切。
ゴミ箱の周りを清潔に保つことで、アライグマを寄せ付けにくくなります。
「でも、毎日の清掃は大変…」
そう思う人も多いはず。
そんな時は、ご近所さんと協力するのがいいかもしれません。
当番制で清掃を行えば、負担も軽減できます。
みんなで協力して、清潔で住みやすい環境を守りましょう。
アライグマの食性と「ゴミ箱を狙う理由」を解説
アライグマがゴミ箱を狙う理由、気になりませんか?実は、彼らの食性と深い関係があるんです。
アライグマは雑食性。
つまり、何でも食べちゃうんです。
彼らの野生での食事メニューは豊富です。
果物、昆虫、小動物、魚…。
まさに「なんでも屋さん」。
この多様な食性が、ゴミ箱を魅力的なレストランに変えてしまうんです。
「うわ?、ここは宝の山だ!」
アライグマの頭の中はこんな感じかもしれません。
人間の食べ残しは、彼らにとって栄養満点の食事。
特に高カロリーな食べ物に目がないんです。
- 果物や野菜の残り:天然の食べ物に近い
- 肉や魚の残り:タンパク質源として重要
- 油っぽい食べ物:高カロリーで魅力的
- 甘い食べ物:エネルギー源として好む
一度おいしい食べ物がある場所を覚えると、何度も訪れます。
つまり、ゴミ箱あさりは学習行動なんです。
「昨日もおいしかったから、今日も行ってみよう!」
こんな風に考えているかもしれません。
また、彼らの手先の器用さも問題を大きくします。
人間の親指のような動きができる手で、簡単に蓋を開けたり、袋を破いたりできるんです。
対策としては、食べ残しを直接ゴミ箱に捨てないことが大切。
生ゴミは新聞紙で包んでから捨てる、または密閉容器に入れるなどの工夫が効果的です。
また、果物の皮や種なども、アライグマを引き寄せる原因になります。
これらもしっかり包んで捨てましょう。
アライグマの食性を理解することで、より効果的な対策が立てられます。
彼らの本能的な行動を理解し、上手に付き合っていくことが大切なんです。
放置すると「近隣トラブル」に発展する可能性も
アライグマのゴミ箱あさり問題、放っておくとどうなると思いますか?実は、ご近所さんとのトラブルに発展しかねないんです。
これは決して他人事ではありません。
まず、散らかったゴミ。
風で飛ばされて、隣の家の庭に入り込んでしまうことも。
「なんで私の庭にゴミが?」と、不快に思われるのは当然です。
「うちの家族がちゃんと片付けていないのかしら…」
そんな風に誤解されてしまうかもしれません。
実際は、アライグマが原因なのに、そのことを知らない人からすれば、あなたの家のマナーが悪いように見えてしまうんです。
さらに、悪臭の問題も。
特に夏場は要注意です。
生ゴミの腐敗が進み、強烈な匂いが発生します。
この匂いが隣家に漂えば、苦情の的になること間違いなし。
- 散らかったゴミの飛散
- 悪臭による生活環境の悪化
- 害虫の増加による衛生問題
- 夜間の騒音によるストレス
「あの家は困った家だ」というレッテルを貼られてしまう可能性も。
これは、長年築いてきた信頼関係を一瞬で崩してしまうかもしれない深刻な問題なんです。
対策としては、まずアライグマ対策を行っていることを周りに知らせることが大切。
「実はアライグマの被害に遭っていて、今対策中なんです」と説明すれば、理解を得られやすいでしょう。
また、ご近所さんと協力して対策を立てるのも効果的。
「みんなで力を合わせてアライグマ対策しませんか?」と声をかけ、地域ぐるみでの取り組みを始めるのもいいかもしれません。
問題を放置せず、積極的に対策を講じることで、近隣トラブルを未然に防ぐことができます。
アライグマ問題は、実は地域のつながりを強める機会にもなるんです。
みんなで協力して、住みよい環境を作っていきましょう。
アライグマのゴミ箱あさりは「違法」なの?
アライグマのゴミ箱あさり、迷惑だと思いますよね。でも、これって法律的にはどうなんでしょうか?
結論から言うと、アライグマ自体の行為は「違法」ではありません。
でも、問題は別のところにあるんです。
まず、アライグマは野生動物。
彼らには「法律を守る」という概念がありません。
ただ本能のままに行動しているだけなんです。
「お腹すいたから食べ物探すよ?」
アライグマの頭の中はこんな感じかもしれません。
彼らにとって、ゴミ箱は格好の食料源。
人間社会のルールなど、お構いなしです。
ただし、アライグマを飼育したり、野外に放したりすることは違法行為になる可能性があります。
日本では、アライグマは「特定外来生物」に指定されているんです。
- アライグマの飼育・保管の禁止
- 野外への放出の禁止
- 輸入の制限
- 販売・譲渡の規制
違反すると罰則の対象になることも。
では、ゴミ箱あさりの被害に遭った場合はどうすればいいのでしょうか。
まず、自治体に相談するのがおすすめです。
多くの自治体では、アライグマ対策の窓口を設けています。
「うちの地域でアライグマの被害が増えているんです」
こんな風に相談してみましょう。
専門家のアドバイスをもらえたり、捕獲の支援を受けられたりすることもあります。
また、自分で対策を行う場合も、法律に注意が必要です。
例えば、アライグマを勝手に捕獲して処分するのは違法になる可能性があります。
必ず自治体のガイドラインに従って行動しましょう。
アライグマのゴミ箱あさりは、彼らにとっては自然な行動。
でも、人間社会との軋轢を生む原因にもなります。
法律を理解し、適切な対策を取ることで、人間とアライグマが共存できる環境づくりが大切なんです。
効果的なゴミ箱対策とアライグマ撃退法

アライグマに強い「頑丈なゴミ箱」の選び方
アライグマに強いゴミ箱を選ぶなら、頑丈で密閉性の高いものがおすすめです。アライグマは力が強く、器用な手先を持っているので、普通のゴミ箱では太刀打ちできません。
まず、材質にこだわりましょう。
金属製や厚手のプラスチック製が理想的です。
薄っぺらい素材だと、アライグマにかじられたり、爪で引っかかれたりして、すぐに穴が開いてしまいます。
次に重要なのが蓋の構造です。
ただ被せるだけの蓋では、アライグマにひょいっと開けられてしまいます。
がっちりとロックできる蓋付きのゴミ箱を選びましょう。
中にはバネ仕掛けの蓋や、二重ロック式の蓋を採用しているものもあります。
「でも、そんなゴミ箱、高そう…」
そう思った方もいるかもしれません。
確かに、一般的なゴミ箱より値段は張ります。
でも、長い目で見ると、アライグマ被害の防止や毎日の清掃の手間を考えれば、十分にもとが取れるんです。
- 金属製や厚手のプラスチック製を選ぶ
- ロック機能付きの蓋を確認
- 大きさは家族の人数や排出量に応じて
- 安定性のあるデザインを選ぶ
小さすぎると、ゴミがあふれてしまい、結局アライグマの餌になってしまいます。
かといって大きすぎると、置き場所に困ったり、扱いにくかったりします。
家族の人数や1日のゴミの量を考えて、ちょうどいいサイズを選びましょう。
「ゴロンッ」
転倒しやすいゴミ箱は避けましょう。
アライグマに倒されると、中身が散らばってしまいます。
底が広く、安定性の高いデザインのものを選ぶのがコツです。
頑丈なゴミ箱を選ぶことで、アライグマの被害を大幅に減らすことができます。
ちょっとした投資で、毎朝のゴミ拾いから解放されるんです。
快適な生活のために、ぜひ検討してみてください。
ゴミ箱の「設置場所」と「固定方法」のポイント
ゴミ箱の設置場所と固定方法、実はアライグマ対策の重要なポイントなんです。適切な場所に、しっかりと固定することで、アライグマの被害を大きく減らすことができます。
まず、設置場所について考えてみましょう。
アライグマは人目を避けたがる性質があります。
だから、人の目につきやすい場所にゴミ箱を置くのが効果的です。
「家の近くに置けば安心?」
そう思う方も多いでしょう。
でも、ちょっと待ってください。
家の壁に接するように置くと、アライグマが壁を伝って簡単に侵入できてしまうんです。
壁から少し離して置くのがコツです。
また、明るい場所に置くのも有効です。
アライグマは夜行性なので、明るい場所は苦手。
玄関灯やセンサーライトの近くに置けば、アライグマは近づきにくくなります。
次に、固定方法です。
アライグマは力が強いので、ゴミ箱を簡単に倒してしまいます。
そこで、しっかりと固定することが大切になってきます。
- 壁や柱にチェーンで固定する
- 重石を乗せる
- 専用の固定具を使用する
- 地面に埋め込む(可能な場合)
そう心配する方もいるでしょう。
確かに、あまりにがっちり固定しすぎると、ゴミ出しが大変になってしまいます。
チェーンで固定する場合は、ある程度の長さを持たせるなど、使いやすさも考えて工夫しましょう。
複数のゴミ箱を置く場合は、間隔にも注意が必要です。
ゴミ箱同士をくっつけて置くと、アライグマが間に入り込んで隠れてしまう可能性があります。
適度な間隔を空けて置くのがおすすめです。
「ガタン!ゴロゴロ…」
こんな音で目が覚めることがなくなれば、朝からすっきりした気分で1日を始められますよ。
ゴミ箱の設置場所と固定方法を工夫して、アライグマの被害から自宅を守りましょう。
アライグマvs人間の嗅覚能力!対策に活かす方法
アライグマと人間の嗅覚能力、どっちが上だと思いますか?実は、アライグマの嗅覚は人間の何十倍も鋭いんです。
この能力の差を知ることで、より効果的なアライグマ対策ができるようになります。
まず、アライグマの嗅覚能力について見てみましょう。
アライグマは非常に鋭敏な鼻を持っています。
人間が気づかないような微かな匂いも、アライグマにはバッチリ分かってしまうんです。
「えっ、そんなに違うの?」
そう思った方も多いでしょう。
実際、アライグマの嗅覚は人間の40倍以上とも言われています。
例えるなら、人間が1メートル先の匂いを感じ取れるとしたら、アライグマは40メートル先の匂いを感じ取れるということです。
この能力の差を知ると、なぜアライグマがゴミ箱に寄ってくるのかがよく分かりますよね。
人間には感じられない微かな食べ物の匂いも、アライグマには丸見えなんです。
では、この嗅覚能力の差を利用して、どんな対策ができるでしょうか?
- 強い香りを使ってごまかす
- 密閉性の高い容器を使う
- 食べ物の匂いを消す工夫をする
- アライグマの嫌いな匂いを利用する
ハッカ油やアンモニア水など、アライグマの嫌いな匂いを利用すれば、寄せ付けない効果が期待できます。
また、食べ物の匂いを消す工夫も大切です。
生ゴミは新聞紙で包んでから捨てる、コーヒーかすを混ぜるなどの方法で、匂いを抑えることができます。
「でも、毎日そんな手間をかけるのは大変…」
そう思う方もいるかもしれません。
でも、アライグマの被害に悩まされるよりは、ずっとマシですよね。
少しの手間で大きな効果が得られるんです。
アライグマの優れた嗅覚能力を知ることで、より効果的な対策が立てられます。
匂いを利用したアライグマ対策、ぜひ試してみてください。
きっと、予想以上の効果が得られるはずです。
光と音を使った「アライグマ撃退テクニック」
アライグマを撃退するのに、光と音が効果的だって知っていましたか?これらを上手く使えば、アライグマを寄せ付けない環境を作ることができるんです。
まず、光を使った対策から見ていきましょう。
アライグマは夜行性の動物です。
つまり、明るい場所は苦手なんです。
この特性を利用して、ゴミ箱周辺を明るくすることで、アライグマを寄せ付けにくくすることができます。
「でも、夜中に明かりをつけっぱなしにするのは…」
そう思った方、大丈夫です。
動体検知センサー付きのライトを使えば、アライグマが近づいてきたときだけ点灯させることができます。
突然の明かりにびっくりして、アライグマは逃げ出してしまうんです。
- 動体検知センサー付きLEDライト
- ソーラー式のガーデンライト
- 点滅するイルミネーションライト
アライグマは、突然の大きな音や、人間の声に似た音を怖がる傾向があります。
「ガシャーン!」
こんな音が突然聞こえたら、アライグマもびっくりして逃げ出してしまいます。
音を利用した対策グッズには、次のようなものがあります。
- 超音波発生装置
- 風鈴
- ラジオ(人間の声が流れるチャンネルに合わせる)
人間には聞こえない高周波の音を発生させ、アライグマを不快にさせます。
ただし、ペットがいる家庭では注意が必要です。
犬や猫にも影響を与える可能性があるからです。
光と音を組み合わせて使うのも効果的です。
例えば、動体検知センサー付きのライトと風鈴を一緒に設置すれば、アライグマが近づいたときに光と音で同時に驚かせることができます。
「ピカッ!チリンチリン♪」
こんな感じで、アライグマを効果的に撃退できるんです。
ただし、同じ対策を続けていると、アライグマが慣れてしまう可能性もあります。
定期的に方法を変えたり、複数の対策を組み合わせたりすることで、より効果を高めることができますよ。
光と音を使ったアライグマ撃退テクニック、ぜひ試してみてください。
ゴミ出しのタイミングも重要!「時間帯」の工夫
ゴミ出しのタイミング、実はアライグマ対策の重要なポイントなんです。適切な時間帯を選ぶことで、アライグマの被害を大幅に減らすことができます。
まず押さえておきたいのが、アライグマの活動時間です。
アライグマは夜行性の動物で、主に夕方から夜明けにかけて活動します。
つまり、この時間帯にゴミを外に出しておくと、アライグマの格好のエサ場になってしまうんです。
「えっ、じゃあいつ出せばいいの?」
そう思った方、安心してください。
ベストなタイミングは、収集日の朝です。
できるだけ収集時間の直前に出すのが理想的です。
例えば、こんな感じでゴミ出しのスケジュールを立てるのはどうでしょうか。
- 前日の夜:ゴミを分別し、袋に入れる準備をする
- 当日の朝:朝食後、出勤や登校の直前にゴミを出す
- 収集後:速やかにゴミ箱を回収し、洗浄する
確かに、朝のバタバタした時間にゴミ出しをするのは大変かもしれません。
そんな時は、ご家族や隣近所の方と協力するのもいいアイデアです。
当番制にして、順番にゴミ出しを担当するなど、工夫次第で負担を軽減できます。
長期旅行などで、どうしても前日の夜にゴミを出さざるを得ない場合は、頑丈なゴミ箱を使うなどの対策が必要です。
ロック機能付きの蓋や、重石を乗せるなど、アライグマが開けられないよう工夫しましょう。
また、生ゴミの管理にも気を付けましょう。
特に夏場は、室内に置いておくと匂いや衛生面が気になりますよね。
そんな時は、冷凍庫で保管する方法もおすすめです。
冷凍しておけば、臭いも抑えられ、アライグマを引き寄せる心配もありません。
「でも、冷凍庫のスペースが…」
そう思った方も多いかもしれません。
でも、専用の密閉容器を使えば、匂いも漏れにくく、スペースも節約できます。
ちょっとした工夫で、生活の質が大きく変わりますよ。
ゴミ出しのタイミングを工夫することで、アライグマの被害を大幅に減らすことができます。
朝型の生活習慣を身につけるきっかけにもなりますし、近所の方との交流も深まるかもしれません。
快適な生活環境を作るため、ぜひ試してみてください。
驚きの裏技!アライグマのゴミ荒らし撃退法5選

キュウリの皮でアライグマを寄せ付けない方法
キュウリの皮、実はアライグマ撃退の強い味方なんです。意外かもしれませんが、アライグマはキュウリの匂いが大の苦手。
この特性を利用して、ゴミ箱周りをアライグマの来ない場所に変身させちゃいましょう。
まず、キュウリの皮を薄く剥いて、ゴミ箱の周りに散らします。
「えっ、そんな簡単でいいの?」と思うかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
アライグマの鋭い鼻は、このキュウリの匂いを遠くからでも感知して、近づかなくなるんです。
- キュウリの皮を1〜2センチ幅に切る
- ゴミ箱の周り30センチくらいの範囲に散らす
- 2〜3日おきに新しい皮に交換する
- 雨の日は効果が薄れるので注意
新鮮なキュウリの皮ほど効果が高いので、こまめに交換しましょう。
また、ゴミ箱の大きさに合わせて、適量を使うのがコツです。
「でも、毎日キュウリを食べるわけじゃないし…」
そんな心配も大丈夫。
キュウリの皮は冷凍保存できるんです。
食べるときに皮を剥いて冷凍しておけば、必要なときにいつでも使えます。
これなら、キュウリを食べない日があっても安心ですね。
この方法、見た目もそんなに悪くないんです。
緑の皮が散らばっているだけなので、遠目には芝生のように見えることも。
アライグマ対策をしながら、ちょっとしたガーデニング気分も味わえちゃうかも。
キュウリの皮で作る、アライグマよけの緑のバリア。
簡単で効果的、しかも環境にも優しい方法です。
ぜひ試してみてください。
アンモニア水の「強烈な臭い」で撃退する技
アンモニア水、その強烈な臭いでアライグマを撃退できちゃうんです。アライグマは鋭い嗅覚の持ち主。
だからこそ、この強烈な匂いが効果てきめんなんです。
まず、アンモニア水を用意します。
でも、原液のまま使うのは危険。
必ず水で薄めて使いましょう。
目安は水とアンモニア水を1対1くらいの割合で混ぜるのがいいでしょう。
「そんな強い匂い、近所迷惑にならない?」
心配ご無用。
アンモニア水の匂いは、人間にはすぐに慣れてしまいます。
でも、アライグマにとっては長時間不快な匂いなんです。
使い方は簡単です。
- 古いタオルや布をアンモニア水溶液に浸す
- 軽く絞って、ゴミ箱の周りに置く
- ゴミ箱の蓋の裏側にも吊るす
- 2〜3日おきに新しい溶液で交換する
雨よけのカバーを用意するか、屋根のある場所に移動させるといいでしょう。
「でも、アンモニア水って手に入りにくくない?」
実は、アンモニア水は多くのホームセンターや薬局で手に入りますよ。
価格もそんなに高くないので、気軽に試せるんです。
この方法、見た目にもそんなに悪影響はありません。
タオルが少し見えるくらいで、遠目にはほとんど気になりません。
アライグマ対策をしながら、ゴミ箱周りの清潔感もアップ。
一石二鳥ですね。
アンモニア水の強烈な臭いで作る、アライグマよけの見えない壁。
簡単で効果的、しかも長続きする方法です。
ぜひ、お試しあれ。
アルミホイルの「音と触感」を利用した対策法
アルミホイル、実はアライグマ撃退の強い味方なんです。アライグマは意外と繊細な動物。
アルミホイルの音や触感が、彼らを寄せ付けない秘密の武器になるんです。
まず、アルミホイルをゴミ箱の周りに敷き詰めます。
「えっ、そんな簡単でいいの?」と思うかもしれません。
でも、これが意外と効果的なんです。
アライグマがアルミホイルの上を歩くと、カサカサ、ガサガサという音が鳴ります。
この予期せぬ音に、アライグマはびっくりして逃げ出してしまうんです。
- アルミホイルをゴミ箱の周り50センチくらいの範囲に敷く
- しわを寄せて凸凹をつけると、より効果的
- 風で飛ばないよう、端を石で押さえる
- 雨の日は効果が薄れるので注意
広い範囲に敷けば敷くほど効果が高まります。
また、しわを寄せてデコボコにすると、アライグマの足裏に不快な感触を与えるので、より効果的です。
「でも、見た目が悪くならない?」
そんな心配も大丈夫。
アルミホイルは意外と目立ちません。
夜間はむしろ月明かりを反射して、ゴミ箱周りを明るくする効果も。
一石二鳥ですね。
この方法、コスト面でもお得です。
アルミホイルは安価で手に入りやすいですし、長持ちします。
破れたら部分的に交換するだけでOK。
経済的な対策方法と言えるでしょう。
「ガサガサ、ビクッ!」
アライグマの驚く姿が目に浮かびますね。
アルミホイルで作る、アライグマよけの銀色の城。
簡単で効果的、しかも経済的な方法です。
ぜひ試してみてください。
LEDライトの「動体検知機能」を活用した方法
LEDライトの動体検知機能、アライグマ撃退の強力な武器になるんです。アライグマは夜行性。
だからこそ、突然の明かりに弱いんです。
この特性を利用して、ゴミ箱周りをアライグマの来ない場所に変身させちゃいましょう。
まず、動体検知機能付きのLEDライトを用意します。
これをゴミ箱の近くに設置するんです。
「そんなハイテクな方法、難しくない?」って思うかもしれません。
でも、実は取り付けはとっても簡単。
電池式のものなら、ネジで固定するだけでOKです。
- ゴミ箱の上や近くの壁に設置
- 検知範囲をゴミ箱全体に向ける
- 明るさは300ルーメン以上がおすすめ
- 電池の消耗に注意(ソーラー充電式もあり)
アライグマの動きを確実に捉えられる位置に設置しましょう。
また、明るければ明るいほど効果的です。
ただし、近隣の迷惑にならない程度に調整するのを忘れずに。
「でも、電気代が気になるな…」
そんな心配も無用です。
LEDライトは省電力。
しかも、動体検知機能のおかげで必要なときだけ点灯するので、電気代はほとんどかかりません。
環境にも家計にも優しい方法なんです。
この方法、防犯効果も抜群です。
不審者対策にもなるので、一石二鳥。
むしろ、ご近所さんから「良い取り組みですね」って褒められるかも。
「ピカッ!」
突然の明かりに驚いて逃げ出すアライグマの姿が目に浮かびますね。
LEDライトで作る、アライグマよけの光の壁。
ハイテクだけど簡単、しかも多目的に使える方法です。
ぜひ、お試しあれ。
コーヒーかすの「香り」でアライグマを混乱させる
コーヒーかす、実はアライグマ撃退の強い味方なんです。アライグマは鋭い嗅覚の持ち主。
だからこそ、コーヒーの強い香りが効果てきめんなんです。
まず、使用済みのコーヒーかすを用意します。
「えっ、捨てるはずのものが役立つの?」って思うかもしれません。
でも、これが意外と効果的。
アライグマはコーヒーの強い香りが苦手で、近づきたがらないんです。
使い方は簡単です。
- コーヒーかすを乾燥させる(天日干しがおすすめ)
- ゴミ箱の周りに薄く撒く
- ゴミ箱の中にも少量入れる
- 雨が降ったら交換する
新鮮なコーヒーかすほど香りが強く、効果も高いです。
また、多すぎると逆効果。
薄く広く撒くのがコツです。
「でも、毎日コーヒー飲むわけじゃないし…」
そんな心配も大丈夫。
コーヒーかすは冷凍保存できるんです。
使うときに必要な分だけ解凍すれば、いつでも新鮮な状態で使えます。
この方法、見た目にも悪影響はありません。
むしろ、土に似た色なので自然な感じ。
ガーデニング好きな方なら、肥料としても使えるので一石二鳥。
「しかも、いい香りがするね!」
そう、人間にとってはいい香り。
でも、アライグマにとっては避けたい強烈な香り。
コーヒーかすで作る、アライグマよけの香りのバリア。
エコで効果的、しかも家計にも優しい方法です。
毎朝のコーヒータイムが、アライグマ対策にもなるなんて素敵ですよね。
ぜひ試してみてください。