アライグマの採食行動と習性とは?【夜間に活発に食事】効果的な3つの被害防止策と餌場管理方法

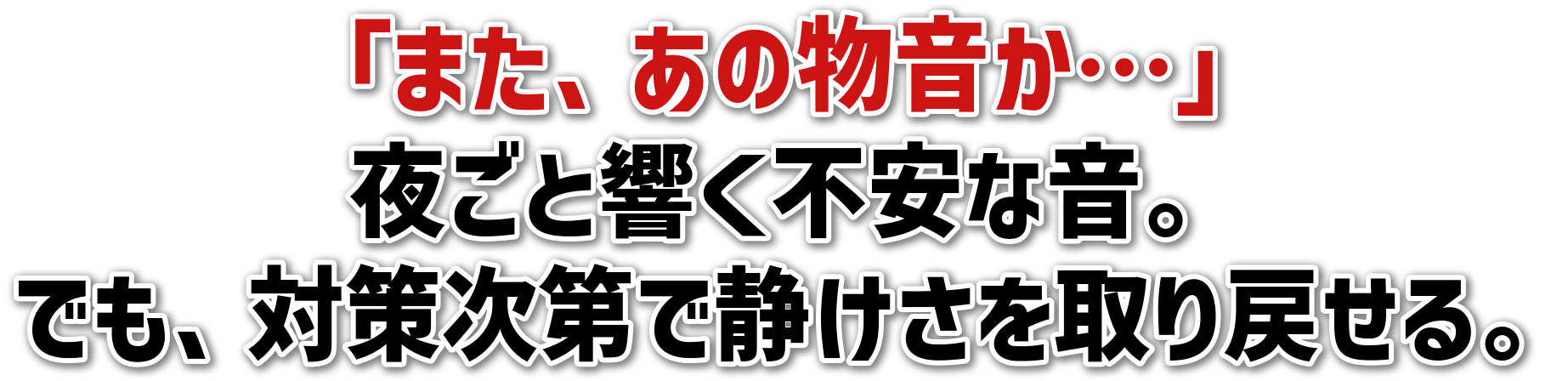
【この記事に書かれてあること】
真夜中にガサゴソと怪しい音。- アライグマは夜行性で、主に日没後から夜明け前に採食活動を行う
- 人家周辺の食べ物が豊富で安全な場所を好んで採食場所に選ぶ
- 前足を器用に使う特徴的な食べ方をする
- 単独で採食活動を行うが、豊富な食料がある場所では複数が集まることも
- 嗅覚と夜間視力が優れており、効率的に食べ物を探す
庭の作物が荒らされている跡。
もしかして、アライグマの仕業?
アライグマの採食行動と習性を知ることは、効果的な対策の第一歩です。
夜行性で器用な彼らは、人家周辺を好んで食事場所に選びます。
その行動パターンを理解すれば、被害を未然に防ぐチャンスが広がります。
この記事では、アライグマの食事習慣の秘密に迫り、家や庭を守る5つの効果的な対策法をご紹介します。
アライグマとの知恵比べ、一緒に勝利を目指しましょう!
【もくじ】
アライグマの採食行動と習性を知る

夜行性のアライグマ!「活発な採食時間帯」とは
アライグマの最も活発な採食時間帯は、日没後から夜明け前までです。特に真夜中の12時から2時頃がピークとなります。
「もぐもぐ、ガサガサ」
真夜中に庭から聞こえてくる不思議な音。
それは、夜行性のアライグマが採食活動を行っている証拠かもしれません。
アライグマは昼間は木の洞や建物の隙間でぐっすり眠り、夜になると活動を始めます。
「なぜ夜に活動するの?」
それには理由があるんです。
- 天敵から身を守りやすい
- 人間の活動が少なく、安全に食事ができる
- 夜行性の昆虫など、夜に活動する獲物を捕まえやすい
特に子育て中の母親アライグマは、昼間に食べ物を探すこともあるんです。
「えっ、昼間に見かけたら危険なの?」
いいえ、必ずしもそうではありません。
ただ、昼間に活動しているアライグマを見かけたら、何か理由があるかもしれません。
餌不足や病気の可能性もあるので、注意が必要です。
アライグマの夜の生活リズムを知ることで、効果的な対策を立てることができます。
例えば、夜間にゴミ箱を外に出さない、庭の果物を夕方までに収穫するなど、アライグマが喜ぶ「夜のごちそう」を減らすことが大切なんです。
アライグマが好む「採食場所」の特徴と対策
アライグマが好む採食場所は、食べ物が豊富で安全な場所です。特に人家の周辺が大好きなんです。
「えっ、なんで人家の近くなの?」という声が聞こえてきそうです。
実は、人間の生活圏には、アライグマにとって魅力的な食べ物がたくさんあるんです。
例えば:
- ゴミ箱の中の食べ残し
- 庭の果樹や野菜
- ペットのえさ
- コンポストの中の生ごみ
- 鳥の餌台
しかも、人家の周辺は、木々や建物の隙間など、身を隠せる場所も多いため、安心して食事ができるんです。
「ゴクゴク、パクパク」
夜中に庭で聞こえるこんな音は、アライグマが水を飲んだり、果物をむしゃむしゃ食べたりしている証拠かもしれません。
では、どうすればアライグマを寄せ付けないようにできるでしょうか?
- ゴミ箱は蓋をしっかり閉め、夜間は屋内に置く
- 庭の果物や野菜は早めに収穫する
- ペットのえさは夜間に外に置かない
- コンポストは蓋付きのものを使用する
- 鳥の餌台は夕方に片付ける
そうすれば、アライグマたちも「ここはおいしい食べ物がないな」と思って、別の場所を探すようになります。
アライグマの「器用な食べ方」に驚愕!その特徴とは
アライグマの食べ方を見たことがありますか?その器用さに驚くはずです。
まるで人間の赤ちゃんが食べているような、とても愛らしい姿なんです。
アライグマの食べ方の最大の特徴は、前足を器用に使うことです。
まるで小さな手のように、食べ物をつかんだり、洗ったりしてから口に運びます。
「えっ、洗うの?」
そう思った方も多いでしょう。
実は、アライグマが食べ物を洗う行動は、単に汚れを落とすためではないんです。
前足の感覚を高めて、食べ物の状態を確認しているんです。
アライグマの食べ方の特徴をまとめると:
- 前足で食べ物をつかむ
- 水辺で食べ物を「洗う」ような動作をする
- 両手で食べ物を持ち、くるくると回しながら食べる
- 硬い殻のある食べ物は、器用に割って中身だけを食べる
- 小さな食べ物は、手のひらですくうように口に運ぶ
こんな音が聞こえてきたら、それはアライグマが食事中かもしれません。
この器用な食べ方は、アライグマの生存戦略の一つなんです。
様々な種類の食べ物を効率よく、そして安全に食べることができるからです。
ただし、この器用さが時として厄介な問題を引き起こすこともあります。
例えば:
- ゴミ箱の蓋を器用に開けてしまう
- 庭の果物を一つずつ丁寧に収穫していく
- 鳥の餌台から上手に餌を取り出す
でも、アライグマにとっては自然な行動なんです。
アライグマの器用な食べ方を知ることで、より効果的な対策を立てることができます。
例えば、蓋のロックが簡単に外せるゴミ箱は避け、アライグマが開けられないような工夫をすることが大切です。
人家周辺での採食vsハクビシン!「厄介度」を比較
アライグマとハクビシン、どちらが人家周辺での採食で厄介なのでしょうか?実は、両者とも一筋縄ではいかない厄介者なんです。
まず、アライグマの特徴をおさらいしましょう:
- 大きな体格(体重4〜9kg)
- 器用な前足で物を扱える
- 強い顎で硬い物も噛み砕ける
- 高い知能と学習能力
- 小さな体格(体重1.5〜3kg)
- 細長い体で狭い隙間にも侵入できる
- 木登りが得意
- 果物が大好物
夜中に聞こえるこの音、アライグマとハクビシンのどちらでしょうか?
実は、音だけでは判断が難しいんです。
厄介度を比較すると:
- ゴミあさり:アライグマの方が厄介(力が強く、蓋を開けやすい)
- 果樹被害:ハクビシンの方が厄介(木登りが上手で、高い場所の果実も食べる)
- 家屋侵入:ハクビシンの方が厄介(小さな隙間から侵入できる)
- ペットフード被害:アライグマの方が厄介(大食漢で、量を食べる)
- 畑の被害:両者とも厄介(野菜や果物を幅広く食べる)
どちらの被害が多いかは、地域や環境によっても変わってきます。
大切なのは、アライグマとハクビシン、それぞれの特徴を理解し、適切な対策を取ることです。
例えば、ゴミ箱の管理を徹底し、果樹には防護ネットを張るなど、両者の対策を組み合わせることが効果的です。
「えっ、大変そう…」と思うかもしれません。
でも、コツコツと対策を積み重ねていけば、被害を最小限に抑えることができるんです。
ゴミあさりは逆効果!「餌付け防止」が重要な理由
アライグマのゴミあさりを放置するのは大変危険です。なぜなら、それは無意識の「餌付け」になってしまうからです。
「えっ、ゴミを放置しているだけで餌付けになるの?」
はい、その通りなんです。
アライグマにとって、人間のゴミは豊かな食料源なんです。
一度おいしい思いをすると、そこに何度も戻ってくるようになります。
餌付けが進むとどうなるでしょうか?
- アライグマの数が増える
- 人間との接触機会が増え、危険性が高まる
- 病気が広がるリスクが上がる
- 家屋への侵入など、被害が拡大する
夜中にこんな音が聞こえたら要注意です。
アライグマがゴミあさりを始めているかもしれません。
では、どうすれば餌付けを防げるでしょうか?
以下の対策が効果的です:
- ゴミは蓋つきの丈夫な容器に入れる
- ゴミ出しは収集日の朝に行う
- 生ゴミは新聞紙で包むなど、臭いを抑える
- 庭の果物や野菜は早めに収穫する
- ペットのえさは夜間に外に置かない
でも、これらの対策は人間の生活環境を清潔に保つことにもつながるんです。
一石二鳥というわけです。
餌付け防止は、アライグマ対策の中でも最も重要なポイントです。
なぜなら、食べ物がなければアライグマは別の場所を探すからです。
「ここには美味しいものがないな」とアライグマに思わせることが、最も効果的な対策なんです。
アライグマの群れ行動と感覚器官を徹底解剖

単独行動vs群れ行動!「採食時の違い」を比較
アライグマの採食行動は、基本的に単独行動ですが、状況によっては群れで行動することもあります。「えっ、アライグマって一人で食事するの?」
そう思った方も多いかもしれませんね。
実は、アライグマは基本的に単独行動を好む動物なんです。
でも、食べ物が豊富な場所では、複数のアライグマが集まることもあるんです。
では、単独行動と群れ行動の違いを見てみましょう。
- 単独行動:静かで素早い採食、警戒心が強い
- 群れ行動:にぎやかで長時間の採食、警戒心がやや低下
夜中に庭から聞こえるこんな音、1匹のアライグマかもしれませんし、複数かもしれません。
単独行動の場合、アライグマは非常に警戒心が強く、ちょっとした物音でサッと逃げてしまいます。
一方、群れで行動している場合は、お互いの存在が安心感となり、警戒心がやや低下するんです。
「じゃあ、群れで来られたら大変じゃない?」
確かにその通りです。
群れで来られると、被害が大きくなる可能性が高くなります。
でも、逆に言えば、群れでいる時の方が人間に気づきやすく、追い払いやすいという面もあるんです。
アライグマの群れ行動で特徴的なのは、親子での行動です。
子育て中の母親アライグマは、子供たちに採食方法を教えるため、一緒に食事をすることが多いんです。
「わー、可愛い光景なんだ!」
そう思うかもしれませんが、これが家庭菜園の作物を全滅させる原因にもなるんです。
親子で来られると、一晩で広範囲の被害が出てしまうことも。
対策としては、単独でも群れでも効果的な方法を組み合わせるのがおすすめです。
例えば:
- 動体検知式のライトを設置する
- においの強い植物(ミント系など)を植える
- 音の出るものを庭に置く(風鈴など)
子育て中の母アライグマ「採食指導」の驚くべき光景
子育て中の母アライグマによる「採食指導」は、驚くほど計画的で細やかなんです。「えっ、動物にも子育て方法があるの?」
そう思った方も多いかもしれませんね。
実は、アライグマの母親は非常に熱心な先生なんです。
母アライグマの採食指導は、主に夜間に行われます。
その光景を想像してみてください。
「ほら、こうやって前足を使うのよ」
母アライグマが器用に前足を使って食べ物を掴む様子を、子アライグマたちが真剣な眼差しで見つめています。
採食指導の内容は、主に以下のようなものです:
- 食べられる物と食べられない物の区別
- 前足を使った効率的な食べ方
- 危険を察知する方法
- 人間の生活圏での行動の仕方
夜中に庭から聞こえるこんな音、もしかしたら母アライグマが子供たちに食べ方を教えている音かもしれません。
特に興味深いのは、母アライグマが人間の生活圏での行動を教えている点です。
ゴミ箱の開け方や、庭の果樹からどうやって実を取るかなど、人間にとっては迷惑な行動ですが、アライグマにとっては生存に必要な技術なんです。
「それって、被害が増えるってことじゃない?」
確かにその通りです。
子育て中の母アライグマがいると、被害が長期化・広範囲化する可能性が高くなります。
でも、この習性を逆手に取った対策も可能です。
例えば:
- 母アライグマが好む巣作りの場所(屋根裏など)を封鎖する
- 庭に子アライグマが入りにくい柵を設置する
- 食べ物の匂いを徹底的に管理する
そうすれば、自然と別の場所を探すようになります。
母アライグマの採食指導を理解することで、より効果的な対策が立てられるんです。
可愛らしい光景ではありますが、私たちの生活を守るためには、適切な対応が必要なんです。
アライグマの視力と嗅覚!「優れた感覚」はどっち?
アライグマの感覚器官の中で、特に優れているのは嗅覚です。視力も優れていますが、食べ物を探す時は主に嗅覚に頼っているんです。
「えっ、目より鼻が頼りなの?」
そう思った方も多いでしょう。
実は、アライグマの鼻は驚くほど敏感なんです。
アライグマの嗅覚と視力を比べてみましょう:
- 嗅覚:人間の20〜40倍の能力
- 視力:夜間視力は人間の7〜8倍、色覚あり
夜中に庭から聞こえるこんな音、それはアライグマが鼻を使って食べ物を探している証拠かもしれません。
アライグマの嗅覚が優れている理由は、その生存戦略にあります。
夜行性で雑食のアライグマにとって、暗闇の中で様々な食べ物を見つけるには、嗅覚が最も頼りになるんです。
例えば、アライグマは地中に埋まったミミズや昆虫の幼虫なども嗅ぎ分けることができます。
まるで、地面の下に透視眼があるかのようです。
「じゃあ、視力はそんなに重要じゃないの?」
いいえ、そんなことはありません。
アライグマの視力も十分に優れています。
特に夜間視力は素晴らしく、暗闇でも障害物を避けたり、動く獲物を追いかけたりすることができます。
また、アライグマは色覚も持っています。
これは、熟した果実を見分けるのに役立っているんです。
では、この特徴を踏まえた対策を考えてみましょう:
- 強い香りの植物(ミントやラベンダーなど)を庭に植える
- 動体検知式のライトを設置して、視覚的に驚かせる
- 食べ物の匂いを徹底的に管理する(密閉容器の使用など)
アライグマの感覚器官を理解することで、より効果的な対策が立てられます。
彼らの能力を認識しつつ、上手く付き合っていく知恵が必要なんです。
夜間採食に適した「優れた視力」の秘密を解明
アライグマの夜間採食を可能にしている秘密は、その優れた夜間視力にあります。彼らの目は、暗闇での採食に特化した構造を持っているんです。
「えっ、アライグマって夜でもよく見えるの?」
そう思った方も多いでしょう。
実は、アライグマの目は驚くほど光に敏感なんです。
アライグマの夜間視力の秘密を見てみましょう:
- 大きな瞳孔:より多くの光を取り込める
- 反射板(タペタム):網膜に届いた光を再反射
- 桿体細胞の多さ:薄明かりでも物の動きを捉えられる
夜中に懐中電灯でアライグマを照らすと、目がこんな風に光って見えるんです。
これは、目の奥にある反射板(タペタム)が光を反射しているからなんです。
アライグマの夜間視力が優れている理由は、その進化の過程にあります。
夜行性の動物として、暗闇で効率よく食べ物を探す必要があったんです。
例えば、アライグマは月明かりだけでも十分に活動できます。
人間の目にはほとんど何も見えない状況でも、アライグマは障害物を避けながら歩き回り、食べ物を探すことができるんです。
「じゃあ、昼間は目が眩しくて動けないんじゃない?」
実はそうでもないんです。
アライグマの目は昼と夜の両方に適応できるように進化しています。
ただし、昼間はあまり活動的ではありません。
では、この夜間視力を踏まえた対策を考えてみましょう:
- 動体検知式の強力なライトを設置する(突然の明るさでアライグマを驚かせる)
- 反射板や光る物体を庭に設置する(アライグマの目を惑わせる)
- 夜間はカーテンをしっかり閉める(室内の光で外にいるアライグマを引き寄せない)
アライグマの夜間視力の秘密を理解することで、より効果的な対策が立てられます。
彼らの能力を認識しつつ、知恵を絞って対策を考えていくことが大切なんです。
触覚vs聴覚!「採食に重要な感覚」はどちら?
アライグマの採食行動において、触覚と聴覚はどちらも重要ですが、特に触覚が大きな役割を果たしています。「えっ、耳より手の感覚が大事なの?」
そう思った方も多いでしょう。
実は、アライグマの前足の感覚は驚くほど繊細なんです。
アライグマの触覚と聴覚を比べてみましょう:
- 触覚:前足の感覚が非常に敏感、水中でも物を識別可能
- 聴覚:高音に敏感、低音はあまり得意ではない
夜中に庭から聞こえるこんな音、それはアライグマが前足で食べ物を確認している音かもしれません。
アライグマの触覚が優れている理由は、その生活様式にあります。
水辺で食べ物を探すことが多いアライグマにとって、水中で物を識別できる能力は非常に重要なんです。
例えば、アライグマは目を閉じたまま、前足だけで食べられる物と食べられない物を区別することができます。
まるで、指先に目があるかのようです。
「じゃあ、聴覚はそんなに重要じゃないの?」
いいえ、聴覚も重要な役割を果たしています。
特に高音に対する感度が高く、小さな獲物の動きを聞き分けることができます。
ただし、低音には比較的鈍感で、人間の話し声程度の音はあまり気にしない傾向があります。
では、この特徴を踏まえた対策を考えてみましょう:
- 庭に小石を敷く(前足で歩くときの感触が不快)
- 高周波音を発する装置を設置する(聴覚を刺激して警戒させる)
- 水場の周りに金網を張る(触覚を使った採食を妨げる)
アライグマの感覚器官を理解することで、より効果的な対策が立てられます。
彼らの能力を認識しつつ、上手く付き合っていく知恵が必要なんです。
「へー、アライグマってこんなに繊細な感覚を持っているんだね」
そうなんです。
アライグマの感覚の鋭さを知ることで、私たちの対策も的確になります。
例えば、庭に小石を敷くだけでも、アライグマにとっては不快な環境になるんです。
また、高周波音を利用した対策は、人間には聞こえないので生活に支障がありません。
でも、アライグマにとっては非常に不快な音なんです。
触覚と聴覚、どちらもアライグマの生存に欠かせない感覚です。
これらの特徴を理解し、うまく活用することで、より効果的なアライグマ対策が可能になるんです。
アライグマの採食被害から家を守る5つの対策

LEDライトで撃退!「動体検知式照明」の設置方法
動体検知式のLEDライトは、アライグマを効果的に撃退する強力な武器です。突然の明かりにびっくりして逃げ出すアライグマの習性を利用した、賢い対策方法なんです。
「え?ただの明かりでアライグマが逃げるの?」
そう思った方も多いかもしれませんね。
でも、夜行性のアライグマにとって、突然の明るさは大敵なんです。
では、どうやって設置すればいいのでしょうか?
ポイントは3つあります。
- アライグマの侵入経路に向けて設置する
- 地面から1.5〜2メートルの高さに取り付ける
- 広範囲をカバーできるよう、複数設置する
突然の明かりに、アライグマは「ビクッ」と驚いて逃げ出します。
これを繰り返すことで、あなたの庭は「危険な場所」としてアライグマの記憶に刻まれるんです。
動体検知式LEDライトの効果を高める裏技もあります。
例えば、ライトの色を赤にすると、より効果的だという研究結果もあるんです。
赤い光は、アライグマにとって特に不快に感じるようですね。
「でも、ご近所迷惑にならない?」
心配ご無用です。
最近の動体検知式LEDライトは、感度調整ができるものが多いんです。
人間の動きには反応せず、アライグマサイズの動物にだけ反応するよう設定できます。
設置する際は、雨風に強い製品を選びましょう。
屋外で使用するので、耐久性は大切です。
また、太陽光で充電できるタイプなら、電気代の心配もいりません。
この方法で、アライグマとの知恵比べに勝利しましょう!
「アンモニア臭の肥料」でアライグマを寄せ付けない!
アンモニア臭のする肥料は、アライグマを寄せ付けない強力な武器です。その強烈な臭いが、アライグマの敏感な鼻をくすぐり、「ここは危険だ!」と勘違いさせるんです。
「え?ただの肥料でアライグマが逃げるの?」
そう思った方も多いでしょう。
でも、アライグマの鼻は人間の20〜40倍も敏感なんです。
私たちには気にならない臭いでも、アライグマには強烈な刺激になるんです。
では、どうやって使えばいいのでしょうか?
ポイントは3つあります。
- 庭の周囲に均等に撒く
- アライグマの侵入経路に重点的に撒く
- 雨が降った後は再度撒く
この臭いを嗅いだアライグマは、「ここは危険だ!」と思って逃げ出します。
これを繰り返すことで、あなたの庭は「近寄りがたい場所」としてアライグマの記憶に刻まれるんです。
アンモニア臭の肥料の効果を高める裏技もあります。
例えば、コーヒーかすを混ぜるんです。
コーヒーの苦みとアンモニアの臭いの相乗効果で、より強力な忌避効果が期待できます。
「でも、臭くて自分も庭に近づけなくなるんじゃ...」
心配ご無用です。
人間の鼻はアライグマほど敏感ではありません。
適量を使えば、人間には気にならない程度の臭いで済みます。
使用する際は、植物への影響も考えましょう。
アンモニア臭の肥料は、同時に植物の栄養にもなります。
一石二鳥ですね。
ただし、濃度が高すぎると根焼けの原因になるので、説明書をよく読んで適量を守りましょう。
この方法で、アライグマとの嗅覚勝負に勝利しましょう!
風鈴の音で警戒心アップ!「不規則な音」の効果
風鈴の音は、アライグマの警戒心を高める効果的な方法です。不規則に鳴る音が、アライグマに「ここは安全じゃない」と思わせるんです。
「え?ただの風鈴でアライグマが怖がるの?」
そう思った方も多いでしょう。
でも、アライグマは予測できない音に対して非常に敏感なんです。
風鈴の音は、まさにアライグマの神経を逆なでする音なんです。
では、どうやって使えばいいのでしょうか?
ポイントは3つあります。
- アライグマの侵入経路に複数設置する
- 風通しの良い場所を選ぶ
- 金属製の風鈴を選ぶ(より高い音が出るため)
この不規則な音を聞いたアライグマは、「ここは危険かも?」と警戒心を高めます。
これを繰り返すことで、あなたの庭は「落ち着かない場所」としてアライグマの記憶に刻まれるんです。
風鈴の効果を高める裏技もあります。
例えば、風鈴に小さな鏡や光る物を付けるんです。
音と光の相乗効果で、より強力な忌避効果が期待できます。
「でも、夜中にうるさくて眠れなくなるんじゃ...」
心配ご無用です。
最近の風鈴には、音量を調整できるタイプもあります。
また、夜間だけ設置するという方法もありますよ。
設置する際は、近所への配慮も忘れずに。
あまりにも大きな音だと、ご近所トラブルの原因になりかねません。
適度な音量で、アライグマ対策と近所付き合いの両立を図りましょう。
この方法で、アライグマとの音合戦に勝利しましょう!
「ペパーミントの植栽」で採食場所から遠ざける方法
ペパーミントの植栽は、アライグマを庭から遠ざける効果的な方法です。その強烈な香りが、アライグマの敏感な鼻を刺激し、「ここは居心地が悪い」と思わせるんです。
「え?ただのハーブでアライグマが逃げるの?」
そう思った方も多いでしょう。
でも、アライグマは強い香りが苦手なんです。
特にペパーミントの清涼感のある香りは、アライグマにとってはとても不快なにおいなんです。
では、どうやって植えればいいのでしょうか?
ポイントは3つあります。
- 庭の周囲に沿って植える
- アライグマの侵入経路に重点的に植える
- 定期的に葉をもんで香りを強くする
この強烈な香りを嗅いだアライグマは、「ここは居心地が悪い!」と思って逃げ出します。
これを繰り返すことで、あなたの庭は「近寄りがたい場所」としてアライグマの記憶に刻まれるんです。
ペパーミントの効果を高める裏技もあります。
例えば、ペパーミントオイルを布に染み込ませて庭に吊るすんです。
植物の香りとオイルの香りの相乗効果で、より強力な忌避効果が期待できます。
「でも、ペパーミントばかりじゃ庭が単調になるんじゃ...」
心配ご無用です。
ペパーミント以外にも、ラベンダーやローズマリーなど、アライグマの嫌いな香りの植物はたくさんあります。
これらを組み合わせて植えれば、見た目にも香りにも豊かな庭になりますよ。
植える際は、ペパーミントの繁殖力の強さにも注意しましょう。
地下茎で広がるので、プランターで育てるか、根止めをして植えるのがおすすめです。
この方法で、アライグマとの香り勝負に勝利しましょう!
「古いCD」の反射光でアライグマを混乱させる技
古いCDの反射光は、アライグマを混乱させる意外な武器です。不規則に動く光の反射が、アライグマの目をくらませ、「ここは危険だ」と思わせるんです。
「え?ただのCDでアライグマが怖がるの?」
そう思った方も多いでしょう。
でも、夜行性のアライグマにとって、予測できない光の動きは非常に不安を感じるものなんです。
CDの反射光は、まさにアライグマの神経を逆なでする光なんです。
では、どうやって使えばいいのでしょうか?
ポイントは3つあります。
- CDを糸で吊るして、風で自由に回転するようにする
- アライグマの侵入経路に複数設置する
- 月明かりや街灯の光が当たる場所を選ぶ
この不規則に動く光を見たアライグマは、「何だこれは?危険かも?」と混乱します。
これを繰り返すことで、あなたの庭は「落ち着かない場所」としてアライグマの記憶に刻まれるんです。
CDの効果を高める裏技もあります。
例えば、CDに小さな鈴を付けるんです。
光と音の相乗効果で、より強力な忌避効果が期待できます。
「でも、庭が安っぽく見えないかな...」
心配ご無用です。
CDを植物の間に隠すように設置したり、装飾的な吊り下げ方をしたりすれば、むしろ庭のアクセントになりますよ。
また、夜間だけ設置するという方法もあります。
設置する際は、CDの角で怪我をしないよう、エッジを少し削るのがおすすめです。
また、強風で飛ばされないよう、しっかりと固定することも忘れずに。
この方法で、アライグマとの視覚戦に勝利しましょう!