アライグマ捕獲後の再侵入防止策【侵入経路の徹底的な封鎖が重要】効果的な3つの環境改善テクニック

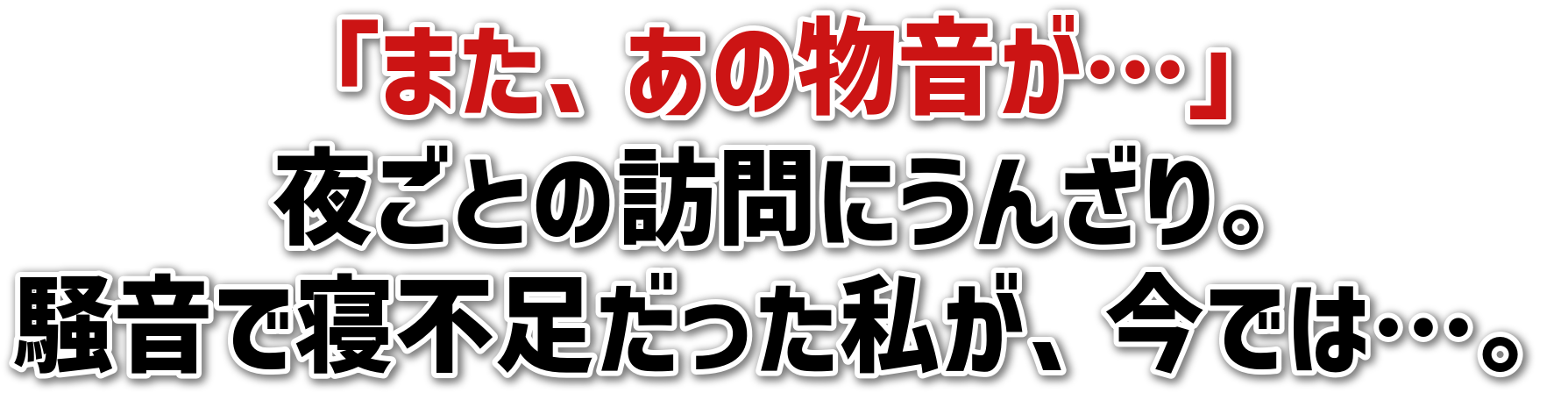
【この記事に書かれてあること】
アライグマを捕獲できたのに、また侵入されてしまった…。- アライグマの再侵入リスクは90%以上
- 家屋損傷や感染症のリスクが高まる
- 侵入経路の完全封鎖が最重要
- 環境改善でアライグマを寄せ付けない
- 継続的な監視と近隣との情報共有が効果的
- 10の意外な裏技で効果的に撃退
そんな経験はありませんか?
実は、アライグマの再侵入率は驚くべきことに90%以上なんです。
でも、大丈夫。
この記事では、アライグマの再侵入を防ぐための効果的な方法を詳しく解説します。
侵入経路の徹底的な封鎖から、意外と効く10の裏技まで、あなたの家を守るための秘策が盛りだくさん。
さぁ、一緒にアライグマとの知恵比べ、始めましょう!
【もくじ】
アライグマ再侵入のリスクと対策

アライグマが再び侵入する可能性は「90%以上」!
アライグマの再侵入率は驚くべきことに90%以上です。これは大変な数字ですよね。
「えっ、そんなに高いの?」と驚かれた方も多いのではないでしょうか。
なぜこんなに高いのでしょうか。
それは、アライグマの賢さと学習能力の高さにあるんです。
一度侵入に成功した場所は、アライグマの頭にしっかりと記憶されてしまうのです。
「ここは安全で、食べ物もあるぞ」とアライグマは考えるわけです。
さらに、アライグマは非常に器用で強い動物です。
小さな隙間からでも入り込めるし、爪で引っかいたり、歯で噛んだりして、侵入口を自分で広げることだってできちゃうんです。
そして何より、アライグマはとてもしつこいんです。
一度追い出されても、「きっとまた入れるはず」と何度も何度も挑戦してくるのです。
このアライグマの特性を考えると、再侵入防止策はとても重要になってきます。
具体的には以下のような対策が必要です。
- 侵入経路を完全に塞ぐ
- 餌になるものを徹底的に管理する
- 庭や家の周りを整理整頓する
- アライグマを寄せ付けない環境づくりをする
「もう二度と来ないだろう」なんて油断は禁物です。
再侵入防止には細心の注意を払い、継続的な対策が必要なんです。
再侵入を放置すると「家屋の損傷」が深刻化
アライグマの再侵入を放置すると、家の被害はどんどん大きくなっていきます。最初は小さな傷だったものが、気づいたら大きな穴になっていた…なんてことも珍しくありません。
まず、アライグマはとてつもない破壊力を持っています。
その強力な爪と鋭い歯で、家の様々な部分を傷つけてしまうんです。
例えば:
- 屋根裏や壁の断熱材をボロボロに
- 天井や壁に大きな穴をあける
- 電線やパイプを噛み切る
- 木製の部分を爪で引っかいてボロボロに
さらに厄介なのは、アライグマは複数で行動するということ。
一匹だけなら被害も限定的ですが、群れで侵入されると被害は倍増どころではありません。
「わぁ、家中がアライグマだらけに!」なんて悪夢のような状況になりかねないのです。
そして、時間が経てば経つほど被害は拡大します。
最初は小さな隙間だったものが、アライグマの執拗な攻撃で大きな穴になり、そこから雨水が入って家全体が傷んでしまう…といった具合に、被害は雪だるま式に大きくなっていくのです。
結果として、修理費用は膨大になってしまいます。
「ええっ、こんなにかかるの!?」と驚くような金額になることも珍しくありません。
家の価値も大きく下がってしまうかもしれません。
だからこそ、アライグマの再侵入は絶対に許してはいけないんです。
早めの対策が家を守る鍵となるのです。
衛生被害と健康リスク!再侵入で「感染症の危険性」も
アライグマの再侵入は、家の破壊だけでなく、私たちの健康も脅かす大きな問題なんです。「えっ、そんなに危険なの?」と思われるかもしれませんが、実はかなり深刻なんです。
まず、アライグマの糞尿による衛生被害があります。
彼らは家の中で排泄をするので、その臭いと汚れは想像以上。
「うわっ、この臭い!」と思わず鼻をつまみたくなるほどです。
特に、屋根裏や壁の中に糞尿がたまると、除去するのが非常に難しくなります。
でも、臭いだけなら我慢できるかもしれません。
問題は、その糞尿に潜む危険な病原体なんです。
アライグマは様々な感染症を運ぶ可能性があるんです。
例えば:
- アライグマ回虫症:重症化すると失明の危険も
- レプトスピラ症:高熱や黄疸などの症状が出る
- 狂犬病:致死率が非常に高い恐ろしい病気
「ゾっとする」話ですよね。
特に注意が必要なのは、子供やお年寄り、ペットです。
彼らは免疫力が弱いので、感染症にかかりやすいんです。
「うちの子が病気になったら…」と考えただけでも心配になりますよね。
そして、一度感染症が家庭内で広がってしまうと、その対処は大変です。
「家族全員で病院通い」なんて事態になりかねません。
さらに、アライグマが持ち込むダニやノミの問題もあります。
これらの虫たちは、アレルギー反応を引き起こしたり、別の病気を媒介したりする可能性があるんです。
このように、アライグマの再侵入は単なる「困りもの」ではなく、私たちの健康を直接脅かす深刻な問題なんです。
だからこそ、再侵入防止策はしっかりと行う必要があるのです。
健康を守るためにも、アライグマ対策は手を抜かずに行いましょう。
「餌付け」や「一時的な追い払い」はNG!逆効果な対策
アライグマ対策、頑張っているのに全然効果がない…そんな経験はありませんか?実は、良かれと思ってやっていることが、逆効果になっていることがあるんです。
今回は、やってはいけないアライグマ対策について、しっかりとお伝えしますね。
まず絶対にNGなのが「餌付け」です。
「かわいそうだから」「少しくらいなら…」と餌をあげてしまう人がいますが、これが最悪の対策なんです。
なぜでしょうか?
- アライグマが「ここに食べ物がある」と学習してしまう
- 餌付けされたアライグマは人を恐れなくなる
- 餌を求めてどんどん数が増えてしまう
次に注意したいのが「一時的な追い払い」です。
大きな音を出したり、光を当てたりして追い払っても、それは一時的な効果しかありません。
アライグマは賢いので、「人がいなくなったらまた戻ればいい」と学習してしまうんです。
そして、よくある間違いが「侵入経路の一部だけを封鎖」すること。
「この穴さえふさげば大丈夫」なんて考えるのは甘いんです。
アライグマは執念深いので、他の侵入口を見つけたり、新たな穴を開けたりしてきます。
さらに、「市販の忌避剤に頼りきり」なのもNGです。
確かに一時的な効果はありますが、アライグマはすぐに慣れてしまいます。
「このくらいの臭いなら我慢できる」とどんどん耐性がついてしまうんです。
最後に、「近所と協力しない」というのも大きな間違いです。
「うちさえ守れればいい」と考えるのは短絡的。
アライグマは広い範囲を行動するので、地域全体で対策しないと意味がありません。
これらの対策は、一見効果がありそうに見えますが、実は逆効果なんです。
「えっ、今までやってたことが間違ってた!?」と驚かれた方も多いのではないでしょうか。
大切なのは、アライグマの習性を理解し、長期的な視点で対策を立てること。
一時しのぎの対策ではなく、根本的な解決を目指すことが重要なんです。
これらのNG対策を避けて、正しい方法でアライグマ対策を行いましょう。
そうすれば、きっとアライグマとのイタチごっこから解放されるはずです。
効果的な再侵入防止策と環境改善

侵入経路の完全封鎖!「屋根裏」vs「床下」どちらが重要?
結論から言うと、屋根裏も床下も両方とも重要です。どちらか一方だけを封鎖しても、アライグマは別の経路から侵入してきてしまいます。
まず、屋根裏からの侵入を防ぐには、屋根の破損箇所や隙間をしっかりと塞ぐ必要があります。
アライグマは意外と器用で、小さな隙間からでも入り込んでしまうんです。
「えっ、こんな小さな穴から入れるの?」と驚くかもしれませんが、アライグマは体を縮めて驚くほど小さな隙間を通り抜けることができるんです。
一方、床下からの侵入を防ぐには、基礎や土台の隙間を塞ぐことが大切です。
アライグマは地面を掘る能力も高いので、少しでも隙間があるとそこを広げて侵入してくる可能性があります。
具体的な対策としては、以下のようなものがあります。
- 屋根の破損箇所を補修する
- 換気口や煙突にはしっかりとした金網を取り付ける
- 軒下や破風板の隙間を塞ぐ
- 床下の通気口には強固な金網を設置する
- 基礎と地面の間の隙間をコンクリートで埋める
「ちょっとした目張りくらいで大丈夫だろう」なんて考えは禁物です。
アライグマは予想以上に力が強いので、安易な対策ではすぐに破られてしまいます。
また、定期的な点検も忘れずに行いましょう。
時間が経つと新たな隙間ができたり、既存の対策が劣化したりする可能性があるからです。
「ガリガリ」「バリバリ」といった音が聞こえたら要注意。
アライグマが侵入を試みている可能性が高いです。
結局のところ、屋根裏も床下も両方をしっかりと封鎖することが、アライグマの再侵入を防ぐ最善の策なんです。
どちらか一方だけでは不十分。
両方の対策をしっかり行って、初めてアライグマに対する「鉄壁の守り」が完成するというわけです。
金属メッシュvs板材!「頑丈な素材」で徹底ガード
アライグマの再侵入を防ぐには、金属メッシュと板材の両方を適材適所で使うのが最も効果的です。でも、どっちがいいの?
と思われるかもしれませんね。
まず、金属メッシュの特徴を見てみましょう。
金属メッシュは通気性が良く、軽量で扱いやすいという利点があります。
特に、換気口や煙突の周りの封鎖に適しています。
でも、注意点もあるんです。
- 目の細かいメッシュを選ぶこと(2cm以下の隙間がおすすめ)
- 強度の高いステンレス製やガルバニウム鋼板製を使うこと
- しっかりと固定すること(アライグマは引っ張る力が強いので)
アライグマは驚くほど力が強く、普通の網ならあっという間に破られてしまいます。
一方、板材はどうでしょうか。
板材は強度が高く、大きな面積を一度に覆えるのが特徴です。
屋根の破損箇所や床下の広い隙間を塞ぐのに適しています。
- 金属板や堅木を使うこと(柔らかい木材はすぐに噛み破られる)
- 厚みのある板を選ぶこと(最低でも1.2cm以上)
- 隙間なくしっかりと固定すること
アライグマが板を噛んでいる可能性があります。
実は、金属メッシュと板材を組み合わせるのが最強の対策なんです。
例えば、大きな隙間を板材で塞ぎ、その周りを金属メッシュで補強する。
これなら、アライグマの鋭い爪や歯にも負けない「鉄壁の守り」ができあがります。
また、シーリング材を使って隙間を完全に埋めるのも効果的です。
アライグマは小さな隙間も見逃さない「すきま泥棒」なので、細かい部分まで丁寧に封鎖することが大切なんです。
結局のところ、金属メッシュか板材か、という二者択一ではなく、両方をうまく使い分けることが重要。
そうすることで、アライグマに「ここからは絶対に入れない!」と思わせる家づくりができるというわけです。
庭の整理整頓vs餌の管理!アライグマを「引き寄せない環境」作り
アライグマの再侵入を防ぐには、庭の整理整頓と餌の管理の両方が欠かせません。どちらか一方だけでは不十分なんです。
まず、庭の整理整頓について考えてみましょう。
アライグマは隠れ場所を好むので、乱雑な庭は格好の住処になってしまいます。
具体的には以下のような対策が効果的です。
- 積まれた薪や木材を片付ける
- 茂みや低木を刈り込む
- 物置やデッキの下をきれいに保つ
- 庭のゴミを定期的に片付ける
それが大間違い。
アライグマにとっては「ここなら安心して暮らせそう」というメッセージになってしまうんです。
次に、餌の管理について。
これがとても重要です。
アライグマは食べ物に敏感で、餌があると必ずやってきます。
以下のような点に注意しましょう。
- 生ごみは密閉容器に入れ、しっかりフタをする
- 果樹の落果はすぐに拾う
- ペットフードは屋外に放置しない
- バーベキューの後は食べ残しをきれいに片付ける
- 鳥の餌台は夜間は撤去する
アライグマの嗅覚は非常に鋭く、わずかな匂いでも察知してしまうんです。
実は、庭の整理整頓と餌の管理は密接に関係しています。
例えば、庭にゴミが散らかっていると、それが間接的に餌となってネズミなどの小動物を呼び寄せ、結果的にアライグマも引き寄せてしまうんです。
また、コンポストにも注意が必要です。
生ごみを堆肥化するのは環境に良いことですが、アライグマにとっては格好の「ごちそう」になってしまいます。
蓋付きの堆肥箱を使うなど、工夫が必要です。
「ガサガサ」「ゴソゴソ」という音が夜に聞こえたら要注意。
アライグマが餌を探して庭を徘徊している可能性があります。
結局のところ、庭の整理整頓と餌の管理は両輪の輪のようなもの。
どちらか一方だけでは不十分で、両方をしっかり行うことで初めて「アライグマよ、来るな!」という強いメッセージを発信できるんです。
そうすることで、アライグマに「この家には何もおいしいものはないな」と思わせることができるというわけです。
センサーライトvs防犯カメラ!「24時間監視」で早期発見
アライグマの再侵入を防ぐには、センサーライトと防犯カメラの両方を活用するのが最も効果的です。どっちがいいの?
と思われるかもしれませんが、実はそれぞれに長所があるんです。
まず、センサーライトの特徴を見てみましょう。
センサーライトは動きを感知して点灯するので、夜行性のアライグマを驚かせる効果があります。
- 突然の明るさでアライグマを威嚇できる
- 設置が比較的簡単で、電気代も節約できる
- 人間の目にも見えるので、すぐに状況が把握できる
一方、防犯カメラはどうでしょうか。
防犯カメラは24時間監視が可能で、アライグマの行動パターンを把握するのに役立ちます。
- アライグマの侵入経路や時間帯を特定できる
- 録画機能があるので、後から詳しく確認できる
- スマートフォンと連携して、外出先でも確認可能
実は、センサーライトと防犯カメラを組み合わせるのが最強の対策なんです。
例えば、センサーライトが点灯したタイミングで防犯カメラが録画を開始する。
これなら、アライグマを驚かせつつ、その反応も記録できるというわけです。
また、赤外線カメラを使えば、暗闇でもアライグマの動きをクリアに捉えることができます。
「真っ暗な夜でも、アライグマの行動が丸見え!」なんて状況も可能になるんです。
ただし、注意点もあります。
プライバシーの問題です。
カメラの向きや設置場所には気をつけて、近隣の人のプライバシーを侵害しないようにしましょう。
「ご近所トラブルの元」にならないよう、細心の注意が必要です。
結局のところ、センサーライトか防犯カメラか、という二者択一ではなく、両方をうまく活用することが重要。
そうすることで、アライグマに「この家は24時間監視されている!」と思わせる環境が作れるんです。
これなら、アライグマも「ここは危険だから、別の場所を探そう」と考えるはず。
早期発見・早期対応で、アライグマの再侵入を効果的に防ぐことができるというわけです。
近隣との情報共有!「地域ぐるみ」の再侵入対策が効果的
アライグマの再侵入を防ぐには、近隣住民との情報共有が非常に重要です。なぜなら、アライグマは一つの家だけでなく、地域全体を行動範囲としているからです。
まず、なぜ情報共有が大切なのか考えてみましょう。
アライグマの出没情報を共有することで、以下のようなメリットがあります。
- 地域全体での警戒レベルが上がる
- アライグマの行動パターンが把握しやすくなる
- 効果的な対策方法を共有できる
- 早期発見・早期対応が可能になる
アライグマは賢い動物なので、一つの家で対策をしても、別の家に移動するだけかもしれません。
では、具体的にどのように情報を共有すればいいのでしょうか。
以下のような方法が効果的です。
- ご近所のグループチャットを作る
- 回覧板を活用する
- 地域の掲示板に情報を張り出す
- 町内会や自治会の集まりで話し合う
顔を合わせて話すことで、より詳細な情報交換ができるんです。
情報共有の際に気をつけるべき点もあります。
- 正確な情報を伝える(噂や憶測は避ける)
- 過度の不安を煽らないよう配慮する
- プライバシーに配慮する(個人情報の取り扱いには注意)
- 定期的に情報を更新する
また、地域ぐるみの対策として、以下のようなアイデアも効果的です。
- 一斉清掃デーを設けて、地域全体の環境を整える
- アライグマ対策の勉強会を開催する
- 地域の見回り隊を結成する
- アライグマ被害マップを作成する
結局のところ、アライグマ対策は「点」ではなく「面」で考えることが重要なんです。
一軒一軒の家が孤立して対策をするのではなく、地域全体で「アライグマお断り!」の姿勢を示すことが大切。
そうすることで、アライグマに「この地域には住みにくいな」と思わせることができるんです。
地域ぐるみの対策は、単にアライグマ問題を解決するだけでなく、コミュニティの絆を強める良い機会にもなります。
「困ったときはお互い様」の精神で、近所同士が協力し合える関係を築くことができれば、それはアライグマ対策以上の大きな成果と言えるでしょう。
みんなで力を合わせれば、きっとアライグマに負けない強い地域を作ることができるはずです。
意外と効く!アライグマ撃退の裏技5選

「アンモニア溶液」の強烈な臭いで寄せ付けない!
アンモニア溶液は、アライグマを寄せ付けない強力な武器になります。その強烈な臭いは、アライグマの敏感な鼻を刺激して、侵入を諦めさせる効果があるんです。
まず、アンモニア溶液を使う際の注意点をお伝えしますね。
- 薄めたアンモニア溶液を使用すること
- 直接肌につかないよう、手袋を着用すること
- 目に入らないよう、保護メガネを使用すること
- 換気の良い場所で作業すること
「プンプン」という強烈な臭いで、アライグマは「うわっ、こんな臭いところには住めないよ!」と思って逃げ出すんです。
特に効果的な場所は、屋根裏や床下の入り口付近。
アライグマが好んで侵入しようとする場所なので、そこに置いておくと効果絶大です。
ただし、アンモニアの臭いは時間とともに弱くなるので、定期的な交換が必要です。
1週間に1回くらいのペースで新しいものと取り替えましょう。
「そろそろかな?」と思ったら交換のタイミングです。
また、雨に濡れると効果が薄れてしまうので、屋外で使う場合は注意が必要です。
屋根のある場所に置くなど、工夫が必要になりますね。
この方法、意外と知られていないんですが、実はとっても効果的なんです。
「えっ、こんな簡単なことでいいの?」と思われるかもしれませんが、アライグマの嗅覚はとても敏感。
強烈な臭いは、彼らにとって大きな脅威なんです。
ぜひ試してみてください。
アライグマが「プイッ」と顔をそむけて逃げ出す姿が目に浮かびますね。
「使用済み猫砂」で天敵の存在をアピール!
使用済みの猫砂、実はアライグマ撃退に大活躍するんです。なぜって?
アライグマにとって、猫は天敵の一種。
その存在を感じさせるだけで、アライグマは警戒心でいっぱいになっちゃうんです。
まず、この方法のポイントをおさえておきましょう。
- 新鮮な使用済み猫砂を使うこと
- 庭の複数箇所に少量ずつ撒くこと
- 雨で流されないよう、屋根のある場所も活用すること
- 1週間に1回程度、新しいものと交換すること
庭の入り口や、家の周りの植え込みの中なんかがおすすめです。
「えっ、こんなの効くの?」って思われるかもしれませんね。
でも、アライグマの鼻はとっても敏感なんです。
猫の匂いを嗅ぐだけで、「ここは危険だ!」と感じ取ってしまうんです。
面白いのは、実際に猫がいなくても効果があるということ。
つまり、猫アレルギーの方や、猫を飼えない環境の人でも、この方法を使えるんです。
ご近所に猫を飼っている人がいれば、使用済みの猫砂をもらうこともできるでしょう。
ただし、注意点もあります。
雨で流されてしまうと効果が薄れるので、定期的な交換が必要です。
それに、強風の日は飛ばされないよう気をつけましょう。
「あれ?昨日置いたはずの猫砂がない!」なんてことにならないようにね。
この方法、実は一石二鳥なんです。
アライグマを寄せ付けないだけでなく、他の小動物も遠ざける効果があるんです。
庭の野菜を荒らすネズミなんかも、寄ってこなくなるかもしれません。
ぜひ試してみてください。
アライグマが「ここは猫のテリトリーだ!」と勘違いして、そそくさと逃げ出す姿が目に浮かびますね。
「風船」の動きと音でアライグマを驚かせる!
風船、実はアライグマ撃退の強力な味方なんです。その不規則な動きと突然の音で、アライグマをびっくりさせて追い払うことができるんです。
まず、この方法のポイントをしっかりおさえておきましょう。
- 明るい色の風船を選ぶこと
- ヘリウムガスではなく普通の空気で膨らませること
- 風船を紐で庭の木や柵に結びつけること
- 複数の風船を異なる高さに設置すること
- 定期的に新しい風船と交換すること
まず、明るい色の風船をいくつか用意します。
赤や黄色など、目立つ色がおすすめです。
それを普通の空気で膨らませて、庭の木や柵に紐で結びつけます。
「えっ、たった風船だけ?」って思われるかもしれませんね。
でも、これがなかなか侮れないんです。
風で揺れる風船の動きは、アライグマにとって予測不能。
「ビクッ」としてしまうんです。
さらに、風船同士が当たって「パンパン」という音を立てると、アライグマは「何か危険なものがいる!」と勘違いしてしまうんです。
夜行性のアライグマにとって、突然の音や動きは大きな脅威なんです。
ただし、注意点もあります。
風船は時間が経つとしぼんでしまうので、1週間に1回程度は新しいものと交換しましょう。
それに、強風の日は風船が飛ばされないよう、しっかり固定することも大切です。
この方法、実は子供たちと一緒に楽しみながらできるのが魅力です。
「今日はアライグマ対策の風船を作ろう!」なんて言えば、きっと喜んで手伝ってくれるはずです。
ぜひ試してみてください。
夜中に「パタパタ」「パンパン」という音を聞いて、アライグマが「うわっ、なんだこれ!」と驚いて逃げ出す姿が目に浮かびますね。
楽しみながらアライグマ対策、素敵じゃないですか?
「ソーラー式スプリンクラー」で水を噴射!動きを感知
ソーラー式スプリンクラー、これがアライグマ撃退の切り札になるんです。動きを感知して水を噴射するので、アライグマを驚かせて追い払う効果があるんです。
まず、この方法のポイントをしっかりおさえておきましょう。
- ソーラー式の動体検知スプリンクラーを選ぶこと
- アライグマの侵入経路に向けて設置すること
- 夜間でも作動するモデルを選ぶこと
- 水の飛散範囲を適切に調整すること
- 定期的にバッテリーや水の残量をチェックすること
まず、ソーラー式の動体検知スプリンクラーを購入します。
これを庭のアライグマが侵入しそうな場所に設置します。
例えば、庭の入り口や、家の周りの植え込みの近くなどがおすすめです。
「えっ、ただの水でアライグマが逃げるの?」って思われるかもしれませんね。
でも、これがとっても効果的なんです。
アライグマが近づいてくると、センサーが反応して突然水が噴射されます。
その予期せぬ出来事に、アライグマは「ビクッ」として逃げ出すんです。
特に夜行性のアライグマにとって、突然の水しぶきは大きな驚きです。
「ジャー!」という音とともに水を浴びせられると、「ここは危険だ!」と感じて二度と近づかなくなるんです。
ただし、注意点もあります。
水の飛散範囲は適切に調整しましょう。
隣の家や道路に水がかからないようにするのが大切です。
それに、冬場は凍結の危険があるので、使用を控えた方がいいかもしれません。
この方法、実は一石二鳥なんです。
アライグマを追い払うだけでなく、庭の水やりも同時にできちゃうんです。
「おっ、庭の植物もいい感じに潤ってるぞ」なんて嬉しい発見があるかもしれません。
ぜひ試してみてください。
真夜中に「ジャー!」という音とともに、びしょ濡れのアライグマが「うにゃー!」と鳴きながら逃げ出す姿が目に浮かびますね。
エコで効果的なアライグマ対策、素敵じゃないですか?
「古いラジオ」で人の存在を演出!24時間稼働で効果的
古いラジオ、実はアライグマ撃退の強い味方になるんです。人の声や音楽を流し続けることで、アライグマに「ここには人がいる!」と思わせる効果があるんです。
まず、この方法のポイントをしっかりおさえておきましょう。
- 24時間放送している局を選ぶこと
- 音量は小さめに設定すること
- 防水対策をしっかりすること
- 複数箇所に設置するとより効果的
- 定期的に電池や動作確認をすること
まず、古いラジオを用意します。
新しいものである必要はありません。
むしろ、使わなくなった古いラジオの再利用にぴったりです。
これをアライグマが侵入しそうな場所、例えば庭や物置の近くに設置します。
「えっ、ただのラジオでアライグマが逃げるの?」って思われるかもしれませんね。
でも、これが意外と効果的なんです。
アライグマは警戒心が強く、人の気配を感じると近づきたがりません。
ラジオから流れる人の声や音楽は、アライグマにとって「ここには人がいる!」というサインになるんです。
特に夜行性のアライグマにとって、夜中に聞こえる人の声は不自然です。
「あれ?こんな時間に人がいるの?」と思って、警戒して近づかなくなるんです。
ただし、注意点もあります。
音量は小さめに設定しましょう。
大きすぎると近所迷惑になってしまいます。
それに、屋外に置く場合は雨対策も忘れずに。
ビニール袋で包むなど、工夫が必要です。
この方法、実は省エネにもなるんです。
電気を使う他の対策グッズと比べて、ラジオの消費電力はとても小さいんです。
「おっ、電気代もあまり上がってないぞ」なんて嬉しい発見があるかもしれません。
ぜひ試してみてください。
真夜中に人の声を聞いて、アライグマが「ここは危険だ!」と思って逃げ出す姿が目に浮かびますね。
簡単で効果的なアライグマ対策、素敵じゃないですか?