アライグマの保護管理計画の概要と重要性【自治体ごとに対策が異なる】効果的な3つの協力方法を紹介

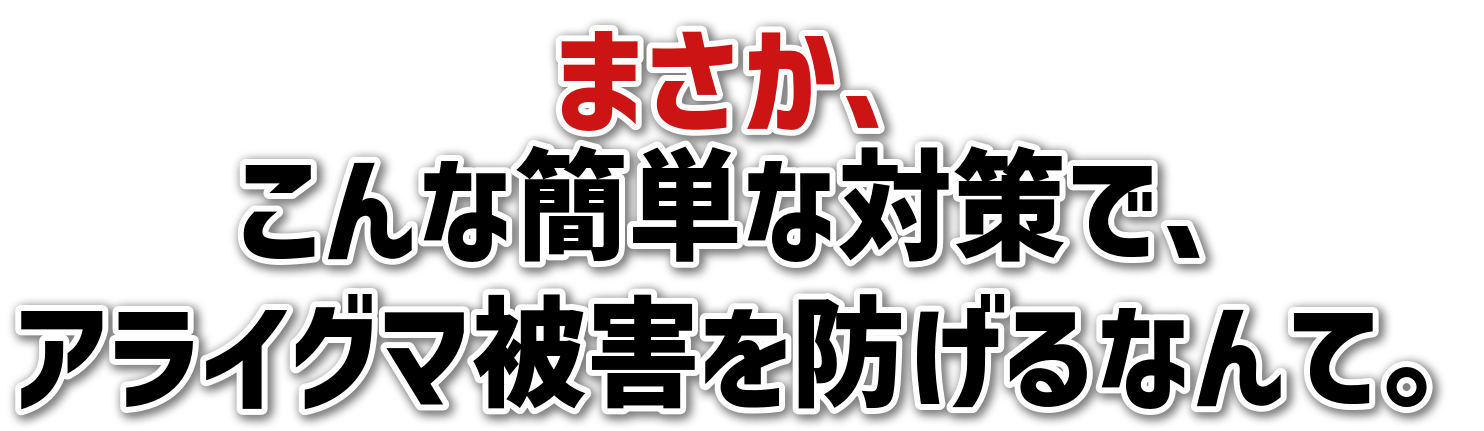
【この記事に書かれてあること】
アライグマの被害に悩まされていませんか?- アライグマの保護管理計画は生態系と農業被害軽減が目的
- 自治体ごとに地域特性に応じた対策を実施
- 個体数管理にはカメラトラップや足跡調査を活用
- 住民の役割は早期発見と餌資源管理が重要
- アライグマは年2回出産で驚異的な繁殖力を持つ
- 10の効果的な対策で被害を未然に防ぐ
実は、この問題には自治体ごとに異なる保護管理計画があるんです。
でも、その内容や重要性をよく知らない人も多いはず。
この記事では、アライグマ対策の要となる保護管理計画の概要を分かりやすく解説します。
さらに、驚くべき繁殖力の実態や、すぐに始められる10の効果的な対策もご紹介。
地域の生態系を守り、農業被害を減らすために、私たちにできることを一緒に考えてみましょう。
さあ、アライグマとの知恵比べ、始めますよ!
【もくじ】
アライグマ保護管理計画とは?自治体ごとの対策の違いを理解しよう

保護管理計画の目的は「生態系と農業被害の軽減」!
アライグマの保護管理計画は、生態系と農業被害を軽減するための重要な取り組みなんです。「えっ、アライグマを保護するの?」なんて思った人もいるかもしれません。
でも、ここでいう「保護管理」は、アライグマを守るという意味ではありません。
むしろ、その数を適切に管理して、私たちの環境を守ることが目的なんです。
アライグマは、もともと日本にいなかった外来生物。
北米が原産地で、1940年代に日本に持ち込まれました。
そして今では、あちこちで見かけるようになっちゃったんです。
でも、これって実は大問題。
アライグマは、在来の動植物を食べたり、農作物を荒らしたりして、大きな被害を引き起こしているんです。
「かわいいのに、そんなことするの?」って驚く人もいるでしょう。
でも、アライグマからすれば、ただ生きるために行動しているだけなんです。
そこで登場したのが、保護管理計画。
この計画には、主に3つの目的があります。
- アライグマの数を適切に減らすこと
- 生態系への悪影響を抑えること
- 農作物への被害を減らすこと
「そうか、ただ追い払えばいいってもんじゃないんだ」って気づいてもらえたでしょうか。
計画に含まれる「個体数調査」と「捕獲目標」の重要性
保護管理計画の中で、特に重要なのが「個体数調査」と「捕獲目標」なんです。これらは、アライグマ対策の基礎となる大切な情報なんです。
まず、「個体数調査」。
これは、文字通りアライグマの数を調べることです。
「えっ、野生動物の数なんてわかるの?」って思いますよね。
でも、実はいろんな方法があるんです。
- カメラトラップ:自動撮影カメラを設置して、通りかかったアライグマを撮影
- 足跡調査:地面に残された足跡を数える
- 捕獲実績:実際に捕まえた数を分析
「へぇ、意外と科学的なんだな」って感じですよね。
次に「捕獲目標」。
これは、調査結果をもとに、どれくらいのアライグマを捕まえるべきかを決めることです。
「えっ、全部捕まえちゃダメなの?」って思う人もいるでしょう。
でも、生態系のバランスを考えると、一気に全部いなくなるのも問題なんです。
だから、科学的な根拠に基づいて、適切な捕獲目標を設定するんです。
これによって、計画的かつ効果的な対策が可能になります。
「なるほど、ただやみくもに捕まえるんじゃないんだ」って気づいてもらえたでしょうか。
この「個体数調査」と「捕獲目標」が、アライグマ対策の羅針盤になるんです。
これらがあることで、対策の効果を測ったり、次の一手を考えたりすることができるんです。
まさに、アライグマとの知恵比べ、というわけです。
自治体ごとの対策が異なる理由と地域特性の影響
アライグマの保護管理計画、実は自治体によって対策が違うんです。「えっ、同じアライグマなのに?」って思いますよね。
でも、これには大切な理由があるんです。
まず、地域によって環境が全然違うんです。
例えば:
- 都会:ビルが多くて、公園や空き地が少ない
- 郊外:住宅地と田畑が混在している
- 山間部:森林が多くて、人家が少ない
「そうか、アライグマの生活環境も場所によって違うんだ」って気づきましたか?
次に、農業の形態も地域によって違います。
果樹園が多い地域もあれば、稲作が中心の地域もある。
当然、アライグマの被害の種類や程度も変わってきます。
「へぇ、アライグマの好みも地域によって違うのか」なんて思いませんか?
さらに、都市化の程度も影響します。
人口密度が高い地域では、アライグマと人間の接点が多くなります。
「そうか、都会のアライグマは人間に慣れてるのかも」なんて想像できますよね。
これらの地域特性を考慮して、それぞれの自治体が最適な対策を立てるんです。
例えば:
- 果樹園が多い地域:電気柵の設置を重視
- 都市部:ゴミ対策と住民啓発に力を入れる
- 山間部:捕獲に重点を置く
「なるほど、一律の対策じゃ効果が出ないんだ」って納得できましたか?
自治体ごとに対策が違うのは、まさにオーダーメイドの戦略なんです。
アライグマの特性と地域の特徴をよく理解して、最も効果的な方法を選んでいるんです。
これぞ、地域に根ざした野生動物管理の姿なんです。
効果的な対策方法の共有「自治体間の情報交換会」
アライグマ対策、実は自治体同士で情報を共有し合っているんです。その代表的な場が「自治体間の情報交換会」。
「へぇ、自治体も勉強会するんだ」なんて思いませんか?
この情報交換会、まるで「アライグマ対策の文化祭」みたいなもの。
各自治体が自分たちの取り組みを発表し合うんです。
例えば:
- A市:「電気柵を設置したら、農作物被害が半減しました!」
- B町:「住民向けの啓発イベントで、通報件数が増えました」
- C村:「新型の罠を導入したら、捕獲効率が上がりました」
「なるほど、他の地域の工夫が聞けるんだ」って感じですよね。
でも、失敗談も大切な情報源。
「うちではこの方法がうまくいかなかった」という話も、実は貴重なんです。
「そっか、失敗から学ぶこともあるんだ」って気づきましたか?
この情報交換会のいいところは、アイデアの相乗効果。
ある自治体の取り組みをヒントに、別の自治体が新しい対策を思いつくこともあるんです。
まさに「三人寄れば文殊の知恵」というわけ。
さらに、研究者や専門家を招いて、最新の研究成果を聞くこともあります。
「へぇ、科学的な裏付けもあるんだ」なんて感心しちゃいますよね。
この情報交換会を通じて、各自治体のアライグマ対策がどんどん進化していくんです。
「ふーん、自治体も日々勉強してるんだな」って思いませんか?
アライグマ対策は、まさに「知恵の輪」。
みんなで知恵を出し合って、より良い方法を見つけていく。
そんな取り組みが、着実にアライグマ問題の解決につながっているんです。
計画なしはNG!「独自の計画」か「広域的な連携」が必須
アライグマ対策、実は計画なしでは進まないんです。「えっ、見つけたら捕まえればいいんじゃないの?」なんて思う人もいるでしょう。
でも、それじゃあ効果が上がらないんです。
まず、小さな自治体でも独自の計画を立てることが大切。
「うちみたいな小さな町でも?」って思いますよね。
でも、それぞれの地域にはそれぞれの特徴があるんです。
例えば:
- 人口が少なくても、農地が多い町
- 面積は狭いけど、自然が豊かな村
- 観光地で、人の出入りが多い地域
「そうか、うちの町ならではの対策が必要なんだ」って気づきましたか?
ただ、小さな自治体だと人手やお金が足りないこともあります。
そんな時は、「広域的な連携」という手があるんです。
「へぇ、他の自治体と協力するんだ」って思いますよね。
広域連携のメリットは、スケールメリット。
例えば:
- 複数の自治体で専門家を雇える
- 大規模な調査が可能になる
- 捕獲や処分の施設を共同で作れる
「なるほど、小さな力も集まれば大きくなるんだ」って感じですよね。
でも、注意点もあります。
広域連携する場合でも、各自治体の特徴を無視してはいけません。
「みんな一緒」じゃなくて、「それぞれの良さを活かす」ことが大切なんです。
結局のところ、計画なしでアライグマ対策をするのは、「闇雲に手を動かしているだけ」。
効果も薄いし、お金と時間の無駄になっちゃうんです。
だから、小さな自治体でも、独自の計画か広域連携、どちらかの形で計画を立てることが必須なんです。
「そっか、計画って本当に大切なんだ」って、理解してもらえましたか?
個体数管理と住民の役割:アライグマ対策の要点

カメラトラップvs足跡調査!個体数把握の方法を比較
アライグマの数を知るには、カメラトラップと足跡調査が有効です。どちらも一長一短があるんですよ。
「え?アライグマの数ってどうやって数えるの?」って思いませんか?
実は、森の中に隠れ忍ぶアライグマたちを数えるのは、なかなか大変なんです。
でも、その数を知らないと対策のしようがありません。
そこで登場するのが、カメラトラップと足跡調査なんです。
まず、カメラトラップ。
これは、動物が通りそうな場所に自動撮影カメラを仕掛けるんです。
アライグマが通りかかると、パシャリ!
と写真を撮ってくれます。
「まるで森のパパラッチみたい!」なんて思いませんか?
- メリット:24時間監視できる
- メリット:複数の個体を識別できる
- デメリット:機材が高価
- デメリット:電池交換や故障の管理が必要
これは文字通り、地面に残された足跡を探すんです。
「探偵みたいでワクワクしそう!」って感じですよね。
- メリット:特別な機材が不要
- メリット:広範囲を調査できる
- デメリット:天候に左右される
- デメリット:他の動物の足跡と間違える可能性がある
だから、地域の特性に合わせて選んだり、両方を組み合わせたりするんです。
「なるほど、科学的なアプローチなんだな」って感じませんか?
アライグマの数を知ることは、対策の第一歩。
まるで、敵の数を探る忍者のように、慎重に調査を進めていくんです。
ぜひ、皆さんも地域の調査に参加してみてくださいね!
箱罠とICT技術の活用!進化する捕獲方法に注目
アライグマの捕獲方法は、昔ながらの箱罠から最新のICT技術まで、どんどん進化しているんです。「えっ、アライグマを捕まえるのにハイテク使うの?」って驚く人もいるかもしれません。
でも、アライグマは賢い動物。
昔ながらの方法だけじゃ、なかなか捕まらないんです。
まず、基本の箱罠。
これは、餌の匂いでアライグマを誘い込み、扉が閉まる仕組みです。
簡単そうに見えますが、実はコツがあるんです。
- 餌の選び方:マシュマロやキャットフードが人気
- 設置場所:アライグマの通り道や痕跡がある場所
- 罠のサイズ:アライグマが入りやすい大きさ
でも、アライグマは学習能力が高いんです。
一度罠にかかった場所には、二度と近づかなくなることも。
そこで登場するのが、ICT技術を活用した新しい捕獲方法です。
例えば、遠隔操作型の罠。
スマートフォンで罠の状況を確認し、アライグマが入ったら即座に扉を閉められるんです。
「まるでゲームみたい!」って感じですよね。
他にも、人工知能を使った画像認識システムもあります。
カメラがアライグマを認識したら自動で罠を作動させるんです。
「すごい!未来の技術だ!」って感動しちゃいます。
これらの新技術のメリットは:
- 捕獲効率の向上
- 誤捕獲の防止
- 作業負担の軽減
ただし、どんなに優れた技術でも、地域の特性や状況に合わせて使うことが大切。
「ハイテクだけに頼りすぎちゃダメだよね」って気づいてくれたでしょうか?
アライグマとの知恵比べ、これからもどんどん進化していくんです。
皆さんも、地域の捕獲活動に興味を持ってみてくださいね!
捕獲後の処分vs研究活用!自治体による対応の違い
捕まえたアライグマ、その後どうなるの?実は自治体によって対応が違うんです。
主に「処分」と「研究活用」の2つの道があります。
「えっ、かわいそう…」って思う人もいるかもしれません。
でも、外来生物であるアライグマを野に放てば、在来種や農作物への被害が続いてしまうんです。
だから、捕獲後の対応は慎重に決められているんです。
まず、多くの自治体で行われているのが安楽死処分です。
これは、法律に基づいて行われる方法なんです。
- 苦痛を与えない方法で行う
- 専門の施設で実施する
- 処分後は適切に焼却処理する
一方で、研究や教育に活用する自治体も増えてきています。
例えば:
- 生態研究:行動パターンや食性の調査
- 被害対策研究:効果的な防除方法の開発
- 環境教育:外来生物問題の啓発活動
中には、動物園で飼育展示するケースもあります。
「子供たちの学習に役立つかも」なんて思いますよね。
ただし、研究や展示に使えるのはごく一部。
多くは安楽死処分されるのが現状です。
「厳しい現実だけど、仕方ないのかな…」って感じるかもしれません。
大切なのは、捕獲から処分までの一連の流れを、人道的かつ科学的に行うこと。
アライグマの命を無駄にしないよう、できる限り有効活用する努力が続けられているんです。
自治体によって対応が違うのは、それぞれの地域の状況や資源に合わせた結果なんです。
「地域の特性に合わせた対応が大切なんだな」って理解してもらえましたか?
アライグマ問題、簡単には解決できません。
でも、一つ一つの命を大切に扱いながら、粘り強く対策を続けていく。
そんな姿勢が、長い目で見れば生態系を守ることにつながるんです。
住民の役割は「早期発見」と「餌資源管理」がカギ!
アライグマ対策、実は私たち住民にもできることがたくさんあるんです。特に大切なのが「早期発見」と「餌資源管理」。
この2つが、対策成功のカギを握っているんです。
「え?私たちにも役割があるの?」って思った人もいるでしょう。
でも、考えてみてください。
アライグマと一番近くで接しているのは、その地域に住む私たちなんです。
まず、早期発見。
これ、すごく重要なんです。
- 足跡や糞を見つけたら速やかに報告
- 夜間の物音や異常に気づいたら連絡
- 庭や畑の作物が荒らされていないかチェック
早く見つけて報告すれば、それだけ早く対策が打てるんです。
次に餌資源管理。
これは、アライグマを引き寄せないようにする作戦です。
- 生ゴミは密閉して保管
- 果樹の実はこまめに収穫
- ペットフードは室内で与え、食べ残しは片付ける
これらの行動、一人では大した効果がないように思えるかもしれません。
でも、地域みんなで取り組めば、大きな力になるんです。
まるで、小さな雫が集まって大きな川になるように。
そして忘れちゃいけないのが、近所との情報共有。
「昨日、庭にアライグマが来たよ」「うちの畑が荒らされたんだ」なんて、井戸端会議で話すだけでも大切な情報になるんです。
住民の協力があれば、自治体の対策もぐっと効果的になります。
「そっか、私たちにもできることがあるんだ!」って、やる気が出てきませんか?
アライグマ対策、決して他人事じゃありません。
みんなで力を合わせれば、きっと素敵な成果が生まれるはず。
さあ、あなたも地域の守護者の一員として、アライグマ対策に参加してみませんか?
計画参加のメリット!地域貢献と効果的な対策実現
アライグマの保護管理計画に参加すると、思わぬメリットがたくさんあるんです。地域への貢献はもちろん、効果的な対策の実現にもつながります。
一石二鳥どころか、一石三鳥くらいのいいことづくしなんです。
「えっ、面倒くさそう…」なんて思った人もいるかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。
参加することで、あなたの生活もよくなる可能性があるんです。
まず、地域貢献のメリット。
これが意外と大きいんです。
- 地域の生態系保護に直接貢献できる
- 農作物被害の軽減で地域経済に好影響
- ご近所との絆が深まる
次に、効果的な対策実現のメリット。
これが本当にすごいんです。
- 地域の実情に合った対策が立てられる
- 迅速な情報共有で被害を最小限に
- 継続的な取り組みで長期的な効果が期待できる
そして、意外かもしれませんが、個人的なメリットもあるんです。
- 野生動物や生態系について学べる
- 地域活動を通じて新しい人間関係が築ける
- 問題解決のスキルが身につく
計画に参加することで、あなたの意見や経験が地域の対策に反映されるんです。
「私の声が届くんだ!」って、ちょっと誇らしい気分になりませんか?
もちろん、参加の仕方は人それぞれ。
できる範囲で協力すればいいんです。
小さな一歩から始めて、少しずつ関わりを深めていけばいいんです。
アライグマ対策、実は地域づくりの一環でもあるんです。
みんなで力を合わせて取り組むことで、アライグマ問題だけでなく、地域全体がより良くなっていく。
そんな素敵な未来が待っているかもしれません。
さあ、あなたも一緒に、住みよい地域づくりに参加してみませんか?
アライグマ繁殖力の驚異と効果的な対策5選

アライグマvs在来種!驚異の繁殖力に要注意
アライグマの繁殖力は、日本の在来種と比べてとてつもなく高いんです。これが、アライグマ問題を深刻にしている大きな要因なんです。
「えっ、そんなに違うの?」って思いますよね。
実は、アライグマの繁殖力は、タヌキやキツネなどの日本の在来種と比べると、まるで別次元なんです。
まず、アライグマの繁殖の特徴を見てみましょう。
- 年に2回出産可能
- 1回の出産で2から5匹の子供を産む
- 生後1年で繁殖可能になる
一方、日本の在来種はどうでしょうか。
例えば、タヌキの場合:
- 年1回の出産
- 1回の出産で3から5匹の子供
- 生後10か月から1年で繁殖可能
「へぇ、アライグマの方が明らかに多産なんだ」って気づきましたか?
この違い、一見小さく見えるかもしれません。
でも、長期的に見ると大きな差になるんです。
例えば、10年後の個体数を単純計算すると、アライグマはタヌキの10倍以上に!
「まるで、ねずみ算みたい!」って感じですよね。
この驚異の繁殖力が、アライグマが外来種問題の代表格になっている理由の一つなんです。
「そりゃあ、あっという間に増えちゃうわけだ」って納得できましたか?
だからこそ、アライグマの対策は早めに始めることが大切。
油断していると、あっという間に手に負えなくなっちゃうんです。
皆さんも、アライグマを見かけたら、すぐに自治体に連絡してくださいね。
早期発見、早期対策が鍵なんです!
ヌートリアとの比較!アライグマの方が繁殖力が高い?
アライグマとヌートリア、どちらが繁殖力が高いと思いますか?実は、アライグマの方が若干繁殖力が高いんです。
両方とも外来種で問題になっていますが、繁殖のスピードが違うんです。
「えっ、ヌートリアって何?」って思った人もいるかもしれませんね。
ヌートリアも、アライグマと同じく外国から持ち込まれた動物で、河川や湖沼周辺で問題を起こしている外来種なんです。
では、アライグマとヌートリアの繁殖力を比べてみましょう。
まず、アライグマの特徴:
- 年2回出産可能
- 1回の出産で2?5匹
- 妊娠期間は約63日
- 生後1年で繁殖可能
- 年2?3回出産可能
- 1回の出産で2?9匹(平均5?6匹)
- 妊娠期間は約132日
- 生後4?8ヶ月で繁殖可能
でも、ちょっと待って!
実は、アライグマの方が妊娠期間が短く、年間を通じて繁殖できるんです。
ヌートリアは季節的な影響を受けやすいんです。
結果として、長期的に見るとアライグマの方が個体数の増加スピードが速いんです。
「なるほど、細かいところで差がついちゃうんだ」って感じですよね。
両方とも驚異的な繁殖力を持っていて、どちらも外来種問題の主役級。
でも、アライグマの方がちょっとだけ"優秀"なんです。
「優秀って言われても困るよね」なんて思いませんか?
この比較からわかるのは、外来種問題の複雑さ。
繁殖力だけでなく、環境への適応力や人間との関わり方など、様々な要素が絡み合っているんです。
だからこそ、一筋縄ではいかない問題なんです。
皆さんも、アライグマやヌートリアを見かけたら、すぐに自治体に連絡してくださいね。
外来種対策は、早めの対応が何より大切なんです!
ニホンザルとの違い!年2回出産のアライグマに驚愕
アライグマとニホンザル、どっちが子育て上手だと思いますか?実は、アライグマの繁殖力はニホンザルを大きく上回るんです。
その差は驚くほど大きいんですよ。
まず、アライグマの繁殖サイクルを見てみましょう:
- 年に2回出産可能
- 1回の出産で2?5匹の子供
- 妊娠期間は約2ヶ月
- 生後1年で繁殖可能に
一方、ニホンザルはこんな感じ:
- 年1回の出産
- 1回の出産で1匹(双子はまれ)
- 妊娠期間は約5?6ヶ月
- 生後3?5年で繁殖可能に
この違い、どれくらい大きいか想像できますか?
例えば、1組のカップルから始めて5年後を考えてみましょう。
アライグマの場合:
「えーと、2回×5匹×5年...うわっ、計算できないくらいたくさん!」
ニホンザルの場合:
「1匹×5年...たった5匹?」
この差、まるで競走で言えば「ウサギとカメ」のようなものです。
でも、この場合はウサギ(アライグマ)が絶対に休まないんです!
でも、ちょっと待って!
これは単純計算で、実際はもっと複雑です。
生存率や環境の影響なども考えないといけません。
それでも、アライグマの繁殖力が圧倒的に高いことは明らかですよね。
この驚異の繁殖力が、アライグマが外来種問題の"チャンピオン"になっている大きな理由なんです。
「そりゃあ、あっという間に増えちゃうわけだ」って納得できましたか?
だからこそ、アライグマの対策は本当に大切。
油断していると、あっという間に手に負えなくなっちゃいます。
皆さんも、アライグマを見かけたら、すぐに自治体に連絡してくださいね。
早期発見、早期対策が鍵なんです!
餌源を絶つ!「果樹の早期収穫」で侵入を防ぐ技
果樹の早期収穫、実はアライグマ対策の秘密兵器なんです。この方法で、アライグマの食料源を断ち切れるんですよ。
「えっ、早く収穫するだけでいいの?」って思いますよね。
実は、これがとっても効果的なんです。
アライグマって、実はすごく賢くて、おいしい果物がなっている場所を覚えちゃうんです。
一度美味しい思いをすると、毎年その時期になるとやってくる。
まるで、カレンダーを見ているみたい!
そこで登場するのが、早期収穫作戦。
アライグマが来る前に、さっさと収穫しちゃうんです。
具体的には:
- 果物が完熟する1?2週間前に収穫
- 少し青いうちに収穫して追熟させる
- 落下した果実もすぐに拾い集める
大丈夫です!
多くの果物は収穫後も熟成するので、うまくやれば美味しく食べられます。
この方法のメリットは:
- アライグマの餌を減らせる
- 果樹園や庭への侵入を防げる
- 被害を未然に防げる
- 農薬や忌避剤を使わなくて済む
ただし、注意点もあります。
果物の種類によって最適な収穫時期が違うので、ちょっと勉強が必要です。
でも、慣れれば簡単!
この方法、実は昔から農家さんの知恵として伝わっているんです。
「へぇ、先人の知恵ってすごいな」って思いません?
皆さんも、庭に果樹がある場合は、ぜひ試してみてください。
アライグマを撃退しながら、美味しい果物も楽しめる。
そんな素敵な一石二鳥を実現できるんです!
金網で完全防御!「家庭菜園」を守る簡単対策
家庭菜園を金網で囲うのは、アライグマ対策の王道です。この方法で、大切な野菜を守り抜くことができるんです。
「えっ、そんな簡単なことでいいの?」って思いますよね。
でも、これが意外とバッチリ効くんです。
アライグマって、器用な手を持っているんです。
普通のネットだと、すぐに破られちゃう。
でも、頑丈な金網なら、そう簡単には突破できないんです。
金網を使う時のポイントは:
- 目の細かい金網を選ぶ(2cm四方以下がおすすめ)
- 高さは1.5m以上に
- 地面にも30cm程度埋め込む
- 上部は内側に30cm程度折り返す
でも、これくらいしっかりしていないと、アライグマは侵入してきちゃうんです。
この方法のメリットは:
- アライグマの侵入を物理的に防げる
- 他の小動物からも野菜を守れる
- 一度設置すれば長期間使える
- 農薬を使わずに済む
ただし、注意点もあります。
金網の設置には少し手間がかかるし、見た目も少し野暮ったくなるかも。
でも、大切な野菜を守るためなら、それくらい我慢できますよね。
この方法、実は昔から畑を守る定番の方法なんです。
「へぇ、昔の人の知恵ってすごいな」って思いません?
皆さんも、家庭菜園をやっている場合は、ぜひ試してみてください。
手間はかかりますが、その後の安心感はバツグン。
「よーし、今年こそ自分で育てた野菜でサラダパーティーだ!」なんて、楽しみが増えること間違いなしです。
アライグマ対策と美味しい野菜の収穫、一石二鳥を実現しちゃいましょう!