アライグマ対策に効果的な柵やフェンスの選び方【高さ1.5m以上が理想的】設置方法と3つのメンテナンスポイント

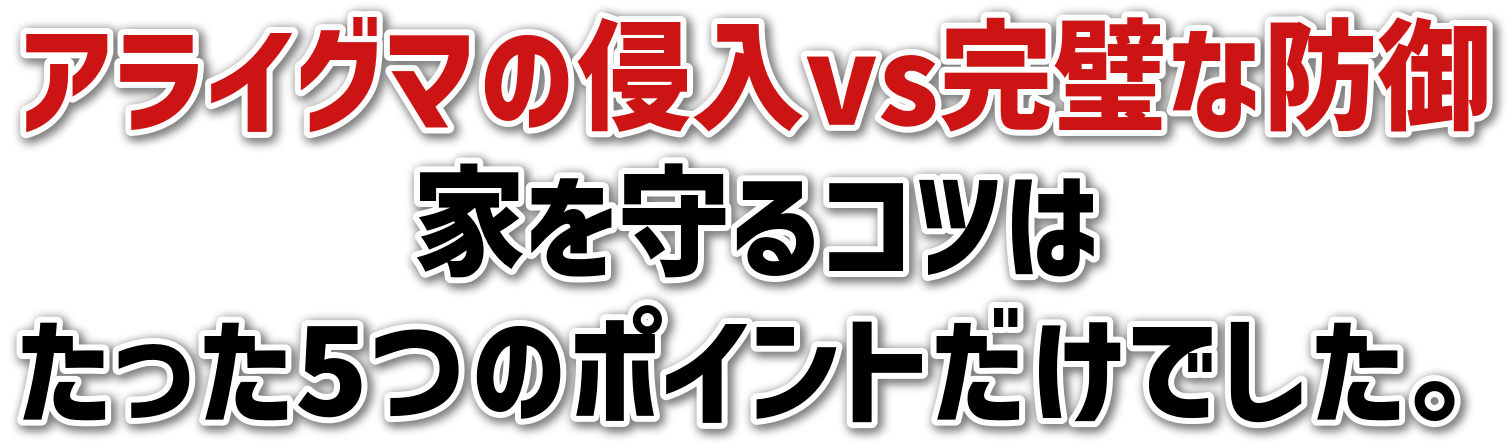
【この記事に書かれてあること】
アライグマの侵入に悩まされていませんか?- アライグマの侵入を防ぐ柵の高さは1.5メートル以上が理想的
- 金属製の細かい網目の柵が最も効果的
- 柵の上部は内側に45度の角度で折り返すとさらに効果的
- 月1回の定期点検で地際や接合部を重点的にチェック
- 長期的には金属製の柵が木製よりも経済的
- 裏技を活用してアライグマの侵入をさらに防ぐ
適切な柵やフェンスの選び方で、その悩みを解決できるかもしれません。
実は、アライグマは驚くほどの跳躍力と器用さを持っています。
でも、大丈夫。
正しい知識さえあれば、あなたの家や農地を守ることができるんです。
高さ1.5メートル以上の柵、細かい網目、そして意外な裏技の数々。
この記事を読めば、アライグマ対策のプロフェッショナルになれること間違いなし!
さあ、一緒にアライグマから大切な場所を守る方法を学んでいきましょう。
【もくじ】
アライグマ対策の柵やフェンスの選び方と設置のポイント

適切な高さは1.5メートル以上!アライグマの跳躍力に注目
アライグマ対策の柵やフェンスは、高さ1.5メートル以上が必要です。これはアライグマの驚異的な跳躍力に対抗するためなんです。
アライグマって、見た目はかわいいのに、実はすごい運動能力の持ち主なんです。
「えっ、そんなに跳べるの?」と驚く人も多いかもしれません。
実は、アライグマは垂直に1メートル以上も跳躍できるんです。
すごいでしょう?
ですから、柵やフェンスを低くしてしまうと、アライグマにとっては「よいしょっと」で簡単に越えられちゃうんです。
「せっかく柵を立てたのに、全然効果がない…」なんてことにならないように、しっかりと高さを確保することが大切です。
具体的には、次の3つのポイントを押さえましょう。
- 柵やフェンスの高さは最低でも1.5メートルに
- できれば2メートル以上がおすすめ
- 地面からの高さを均一に保つこと
地面にでこぼこがあると、そこから低くなった部分を狙われちゃうんです。
「ここなら飛び越えられそう!」とアライグマに思わせないように、しっかりと均一な高さを保ちましょう。
高さを十分に確保すれば、アライグマの侵入をぐっと防げます。
「これで我が家は安心!」という気持ちで、対策を進めていきましょう。
柵の素材選び「金属製の網目が細かいもの」が効果的
アライグマ対策の柵やフェンスには、金属製で網目が細かいものがピッタリです。なぜって?
アライグマは賢くて器用な動物だからなんです。
まず、金属製を選ぶ理由は強度です。
木製だと、アライグマにガジガジと噛まれて穴を開けられちゃうことも。
「せっかく立てた柵なのに…」なんて悲しい結果にならないよう、頑丈な金属製がおすすめです。
次に、網目の細かさがポイント。
アライグマの手は人間の赤ちゃんの手のようにとっても器用なんです。
「えっ、そんなに器用なの?」と思うかもしれませんが、本当なんです。
大きな網目だと、その隙間から手を入れて柵を登ってしまうんです。
具体的には、次の3つの特徴を持つ柵やフェンスを選びましょう。
- 金属製で頑丈なもの
- 網目のサイズが5センチ四方以下
- 表面が滑らかで登りにくいもの
「5センチあれば大丈夫かな?」と思っても、それじゃアライグマの小さな手が入っちゃうんです。
できるだけ細かい網目を選びましょう。
また、表面が滑らかなものを選ぶと、アライグマが爪をひっかけて登るのを防げます。
「ツルツルで登れない!」とアライグマも諦めてくれるはず。
金属製で網目の細かい柵やフェンスなら、アライグマの侵入をしっかりと防げます。
「これで我が家の周りは安全だ!」と胸を張れるはずです。
地面との隙間をなくし「支柱はしっかり固定」が鉄則!
アライグマ対策の柵やフェンスを設置する時、地面との隙間をなくし、支柱をしっかり固定することが超重要です。なぜかって?
アライグマは賢くて、ちょっとした隙間や弱点を見つけては侵入してくるからなんです。
まず、地面との隙間をなくすことから始めましょう。
アライグマは体をぺちゃんこにして、驚くほど小さな隙間から侵入できるんです。
「えっ、そんな薄っぺらになれるの?」と思うかもしれませんが、本当なんです。
だから、地面とピッタリくっつけるのがポイントです。
次に、支柱の固定。
これもすごく大切です。
アライグマは力が強くて、グラグラした支柱なんてあっという間に倒してしまいます。
「せっかく立てた柵が倒れちゃった…」なんて悲しいことにならないよう、しっかりと固定しましょう。
具体的には、次の3つのポイントを押さえて設置するといいですよ。
- 地面との隙間を5センチ以下に
- 支柱は地中30センチ以上埋め込む
- 支柱の周りはコンクリートで固める
「地面に立てればいいかな?」なんて甘く考えると、アライグマにひっくり返されちゃいますよ。
しっかりと地中に埋め込んで、グラグラしないようにしましょう。
また、支柱の周りをコンクリートで固めると、さらに安定します。
「これなら絶対に倒れない!」という自信が持てるはずです。
地面との隙間をなくし、支柱をしっかり固定すれば、アライグマの侵入をガッチリ防げます。
「我が家の防衛線は完璧だ!」と胸を張れるはずですよ。
柵の上部は「内側に45度の角度で折り返す」のがコツ
アライグマ対策の柵やフェンスの上部は、内側に45度の角度で折り返すのがとってもお勧めです。なぜって?
アライグマは賢くて器用な動物だから、普通の真っ直ぐな柵だと簡単に登って越えちゃうんです。
この45度の折り返しがあると、アライグマが柵の上に到達しても、そこから先に進めなくなるんです。
「えっ、そんな簡単なことで防げるの?」と思うかもしれませんが、これがすごく効果的なんです。
アライグマは柵を登る時、垂直な面なら得意なんです。
でも、突然45度に傾いた面に出くわすと、「うわっ、どうしよう!」ってなっちゃうんです。
体勢を崩して落下しちゃうことも多いんですよ。
具体的には、次の3つのポイントを押さえて設置するといいですよ。
- 折り返しの角度は45度に
- 折り返しの長さは30センチ以上
- 折り返しは内側に向ける
外側に向けちゃうと、アライグマにとっては「よいしょっと」で乗り越えやすい踏み台になっちゃうんです。
内側なら、「うわっ、落ちそう!」ってなるんです。
また、折り返しの部分はしっかりと固定することも大切です。
グラグラしていると、アライグマに揺すられて壊されちゃう可能性があるんです。
この45度の折り返しがあれば、アライグマの侵入をグッと防げます。
「我が家の柵は完璧!」って自信を持てるはずですよ。
アライグマもきっと「ここは無理だな〜」って諦めてくれるはずです。
アライグマの侵入を許す「やってはいけない」設置方法
アライグマ対策の柵やフェンスを設置する時、絶対にやってはいけないことがあるんです。これらを知っておくと、「あっ、それダメだったんだ!」って気づけるかもしれません。
まず、最大の禁忌は柵の下に隙間を作ること。
「ちょっとくらいなら大丈夫かな?」なんて甘く考えちゃダメです。
アライグマはね、驚くほど小さな隙間から侵入できちゃうんです。
体をペッタンコにして、スルスルっと入ってきちゃうんですよ。
次に、柵の近くに木や物を置くのも大NG。
これ、よく見落とされがちなんです。
「ちょっとした道具を置いただけなのに…」なんて後悔することになりかねません。
アライグマにとっては、それが絶好の足場になっちゃうんです。
では、具体的に「やってはいけない」ことをリストアップしてみましょう。
- 柵の下に5センチ以上の隙間を作る
- 柵の近くに登れそうな物を置く
- 柵の支柱をしっかり固定しない
- 網目の大きな柵を使う
- 柵の高さを1.5メートル未満にする
「地面に立てればOK」なんて簡単に考えちゃダメ。
アライグマは力が強いので、グラグラした柵はあっという間に倒されちゃいます。
また、網目の大きな柵も要注意。
アライグマの手は器用なので、大きな網目だと簡単に登られちゃうんです。
「こんな小さな手でも登れるの?」ってビックリするくらい器用なんですよ。
これらの「やってはいけない」ことを避ければ、アライグマの侵入をグッと防げます。
「よし、これで完璧!」って自信を持って設置できるはずです。
アライグマも「ここは無理だな〜」って諦めてくれるはずですよ。
アライグマ対策の柵やフェンスのメンテナンスと費用比較

月1回の定期点検で「地際や接合部」を重点チェック
アライグマ対策の柵やフェンスは、月に1回の定期点検が必要です。特に地際や接合部をしっかりチェックしましょう。
「えっ、そんなに頻繁に?」と思われるかもしれません。
でも、アライグマは本当に賢くて、ちょっとした隙を見逃しません。
月1回の点検は、実は最低限の頻度なんです。
地際や接合部って、どうしてそんなに大切なの?
それは、アライグマがよく狙う場所だからです。
地面と柵の間に少しでも隙間があると、そこからスルスルっと入り込んでしまうんです。
「こんな小さな隙間、入れるはずない」なんて甘く見ていると、大変なことになっちゃいます。
具体的には、次の3つのポイントを重点的にチェックしましょう。
- 地際の隙間:5センチ以上の隙間がないか確認
- 接合部のゆるみ:ネジや金具のゆるみをチェック
- 柵の変形や破損:アライグマの爪痕や噛み跡がないか調査
地面が柔らかくなって、柵と地面の間に隙間ができやすいんです。
「ちょっとくらい…」なんて油断は禁物。
アライグマにとっては、それが絶好の侵入口になっちゃうんです。
定期点検は面倒くさいかもしれません。
でも、「これで我が家は安全!」という安心感を得られるんです。
それに、小さな問題を早期発見できれば、大きな被害を防げます。
月に1回、30分程度の投資で、大切な家や庭を守れるんです。
がんばって続けましょう!
金属製vs木製!長期的には「金属製が経済的」な理由
アライグマ対策の柵やフェンス選びで悩むのが、金属製か木製か。結論から言うと、長期的には金属製の方が経済的なんです。
「えっ、金属製の方が高そうなのに?」って思いますよね。
確かに、最初の費用は木製の方が安いんです。
でも、長い目で見ると話が違ってくるんです。
まず、耐久性の違い。
金属製は風雨に強く、アライグマの爪や歯にも負けません。
一方、木製は腐ったり、アライグマにかじられたりして、どんどん傷んでいっちゃうんです。
「せっかく立てた柵なのに…」なんて悲しい思いをしたくないですよね。
次に、メンテナンス費用の差。
金属製はほとんどメンテナンス不要。
一方、木製は定期的な塗装や部分交換が必要になります。
これが、実は大きな費用の差になるんです。
具体的に、金属製と木製の特徴を比べてみましょう。
- 金属製:初期費用は高いが、耐久性抜群で長持ち
- 木製:初期費用は安いが、定期的な補修や交換が必要
- メンテナンス:金属製はほぼ不要、木製は年1回以上の塗装が必要
- 耐用年数:金属製は20年以上、木製は5〜10年程度
- アライグマ対策効果:金属製の方が高い(噛み破られにくい)
確かに、自然な雰囲気は木製の方が出せます。
でも、アライグマ対策を考えると、やっぱり金属製がおすすめなんです。
長期的に見れば、金属製の方が断然お得。
「最初は高くても、長く使えるなら…」って考えると、金属製の良さが分かりますよね。
家計にも優しく、アライグマ対策もバッチリ。
一石二鳥の選択なんです。
DIYvs業者依頼!コストは「2倍以上の差」が出ることも
アライグマ対策の柵やフェンス設置、自分でやるか業者に頼むか、迷いますよね。実はコストの差が2倍以上になることも。
でも、単純に安いからDIYがいいとは限らないんです。
「えっ、そんなに差があるの?」って驚く人も多いはず。
確かに、業者に頼むと人件費がかかるので、どうしても高くなります。
でも、ちょっと待って!
安さだけで決めちゃダメなんです。
DIYのメリットは何と言ってもコストの安さ。
材料費だけで済むので、業者依頼の半分以下になることも。
「よし、これで浮いたお金で別の対策も!」なんて思えちゃいますよね。
でも、業者依頼にもメリットがあるんです。
例えば、
- プロの技術:隙のない設置で、アライグマの侵入をしっかり防げる
- 時間の節約:自分の時間を他の大切なことに使える
- 保証がある:問題があれば対応してもらえる安心感
- 適切な材料選び:状況に合った最適な材料を選んでくれる
実際、どのくらい差があるのか、具体例を見てみましょう。
例えば、20メートルの柵を設置する場合:
- DIY:材料費のみで約5万円〜10万円
- 業者依頼:材料費+工賃で約15万円〜25万円
でも、ここで考えてほしいんです。
「自分の技術に自信がある?」「休日をフルに使える?」「失敗したときのリスクは?」こういうことも、しっかり考慮に入れてくださいね。
結局のところ、状況によって最適な選択は変わってきます。
DIYで楽しみながらやれるなら、それも素敵な選択。
でも、確実さを求めるなら業者依頼も悪くない。
大切なのは、自分の状況をよく考えて決めることなんです。
繁殖期や秋は「点検頻度を増やす」ことがカギ
アライグマ対策の柵やフェンス、いつもと同じペースで点検してるだけじゃダメなんです。繁殖期や秋には、点検の頻度を増やすことが大切です。
「えっ、季節によって変えるの?」って思いますよね。
実は、アライグマの活動も季節によって変わるんです。
特に気をつけたいのが繁殖期と秋。
この時期は、アライグマが特に活発になるんです。
まず、繁殖期。
アライグマは年に2回、春と秋に繁殖期を迎えます。
この時期、彼らは安全な巣を探して必死。
「うちの屋根裏、いい感じ!」なんて思われたら大変です。
柵やフェンスの隙間を見つけて侵入してくる可能性が高くなるんです。
次に秋。
これは食べ物が関係しています。
冬に備えて、アライグマは必死で食べ物を探すんです。
「うわっ、庭の果物がなくなってる!」なんて経験したことありませんか?
そう、彼らの食欲は秋にピークを迎えるんです。
では、具体的にどうすればいいの?
ポイントは3つ。
- 点検頻度を2倍に:通常月1回なら2週間に1回に
- 夜間の見回りを追加:アライグマは夜行性なので夜の様子をチェック
- 柵の周りの環境整備:食べ物になりそうなものを片付ける
でも、この時期の対策が、その後の被害を大きく左右するんです。
ちょっと面倒でも、がんばって続けましょう。
繁殖期や秋の点検強化、実は予防効果も抜群なんです。
アライグマに「ここは入りにくいな」って思わせることができれば、被害はグッと減ります。
「よし、これで我が家は安全!」って自信を持てるはずです。
季節に合わせた対策で、アライグマから大切な家や庭を守りましょう。
木製は「定期的な塗装や部分交換」でコストアップに注意
木製の柵やフェンスって、見た目が良くて人気ですよね。でも、アライグマ対策としては要注意です。
定期的な塗装や部分交換が必要で、思わぬコストアップにつながっちゃうんです。
「えっ、そんなにメンテナンスが必要なの?」って驚く人も多いはず。
実は、木製の柵やフェンスは意外とデリケートなんです。
雨や日差しにさらされて傷んだり、アライグマにかじられたりと、いろんな要因で劣化が進んでいきます。
まず、塗装の問題。
木製の柵は、1〜2年に一度は塗り直しが必要です。
「そんなに頻繁に?」って思いますよね。
でも、これをサボると木が腐って、アライグマの格好の侵入口になっちゃうんです。
次に部分交換。
アライグマは歯が鋭くて、木をかじるのが得意なんです。
「うわっ、柵に穴が開いてる!」なんて気づいたら、すぐに交換が必要になります。
具体的なメンテナンスのポイントを見てみましょう。
- 塗装:1〜2年に1回、防腐剤や防水塗料を塗る
- 点検:月1回は必ず行い、傷や腐りをチェック
- 部分交換:傷んだ部分は速やかに交換(放置すると全体交換に)
- 補強:弱くなった部分は金具などで補強
- 清掃:カビや苔の発生を防ぐため、定期的に清掃
実際、木製の柵のメンテナンス費用を計算してみると、驚きの結果に。
例えば、20メートルの柵の場合:
- 塗装:2年に1回、約3万円
- 部分交換:5年に1回程度、約5万円
「えっ、新しく作り直せちゃうじゃん!」って感じですよね。
木製の柵やフェンス、見た目は確かに素敵。
でも、アライグマ対策と長期的なコストを考えると、やっぱり金属製がおすすめです。
「最初は高くても、長い目で見れば…」って考えると、金属製の良さが分かりますよね。
選ぶ前に、しっかり考えてみてくださいね。
アライグマの特性を知り、効果的な柵やフェンスを設置しよう

アライグマvs猫!「垂直跳躍力は1メートル以上」の驚異
アライグマの垂直跳躍力は1メートル以上!これは多くの人が想像する以上の高さなんです。
「えっ、そんなに跳べるの?」って驚く人も多いはず。
実は、アライグマは猫よりもずっと高く跳べるんです。
猫の平均的な垂直跳躍力が60〜90センチメートルくらいなのに対して、アライグマは軽々と1メートルを超えてしまうんです。
この驚異的な跳躍力は、アライグマの体の特徴から来ています。
彼らは、
- 強靭な後ろ足の筋肉
- しなやかな体
- バランスの取れた体型
例えば、アライグマが庭に侵入しようとしている場面を想像してみてください。
普通の柵なら、ピョンッと一発で簡単に越えられちゃうんです。
「うちの柵、大丈夫かな…」って不安になりますよね。
だからこそ、アライグマ対策の柵は高さが重要なんです。
最低でも1.5メートル、できれば2メートル以上の高さが理想的です。
「そんな高い柵、見た目が…」って思う人もいるかもしれません。
でも、アライグマの被害を考えると、やむを得ないんです。
ちなみに、アライグマの跳躍力は人間の平均とほぼ同じくらいなんです。
「えっ、人間と同じくらい?」って驚きますよね。
成人男性の平均的な垂直跳躍力が50〜60センチメートルくらいなので、アライグマの方が上かもしれません。
この驚異的な跳躍力を知っておくと、アライグマ対策の重要性がよくわかりますよね。
高い柵を設置するのは大変かもしれませんが、「これで我が家は安全!」って安心できるはずです。
アライグマの特性を理解して、しっかりと対策を立てましょう。
柵の上部にローラーを設置!「回転で落下」させる裏技
柵の上部にローラーを設置する裏技、これがアライグマ対策の決め手になるかもしれません。アライグマが掴もうとすると、クルクルっと回転して落下するんです。
「え、そんな簡単なことで効果があるの?」って思うかもしれません。
でも、これがすごく効果的なんです。
アライグマは器用で賢い動物ですが、回転するものを掴むのは苦手なんです。
具体的には、こんな感じで設置します:
- 柵の上部に直径10センチくらいのプラスチック管を取り付ける
- プラスチック管が自由に回転するように設置
- ローラーの長さは柵全体をカバーするように
ローラーがくるくる回って、掴めないんです。
「うわっ!」ってな感じで、そのまま落下。
この裏技のいいところは、アライグマを傷つけずに追い返せること。
「かわいそう…」って思う人もいるかもしれませんが、これなら動物にも優しい対策になるんです。
ただし、注意点もあります。
ローラーはしっかり固定しないと、アライグマの重みで外れちゃうかもしれません。
また、定期的なメンテナンスも必要です。
「よし、これで完璧!」って油断しちゃダメですよ。
この裏技、実は人間の知恵の勝利なんです。
アライグマの習性を利用して、巧妙に撃退する。
「なるほど、こういう方法もあるんだ!」って感心しちゃいますよね。
柵の上部にローラーを設置する、この意外な裏技。
試してみる価値は十分にありそうです。
「よし、これでうちの庭は守れる!」って自信が持てるはずです。
使用済み猫砂を柵の周りに撒いて「天敵の匂い」で撃退
使用済みの猫砂を柵の周りに撒く、これがアライグマ撃退の意外な裏技なんです。猫の匂いがアライグマを寄せ付けない効果があるんです。
「えっ、猫砂?」って驚く人も多いはず。
実は、アライグマにとって猫は天敵の一つなんです。
野生のボブキャットやリンクスなどの大型ネコ科動物を本能的に恐れているんですね。
この裏技、具体的にはこんな風に使います:
- 使用済みの猫砂を集める(もちろん、飼い猫のものを使いましょう)
- 柵の周囲30〜50センチの範囲に薄く撒く
- 雨が降った後は再度撒く必要があります
- 2週間に1回程度、新しい猫砂に交換するのがおすすめ
確かに、人間にも多少匂いは感じます。
でも、アライグマの鋭い嗅覚にとっては強烈な警告になるんです。
この方法のいいところは、自然な方法でアライグマを寄せ付けないこと。
薬品を使わないので、環境にも優しいんです。
「うちの庭、生き物に優しくアライグマ対策ができてるな」って、ちょっと誇らしい気分になれるかも。
ただし、注意点もあります。
近所に野良猫が多い地域では、逆に猫を引き寄せてしまう可能性も。
「アライグマは来なくなったけど、今度は猫が…」なんてことにならないよう、状況を見ながら使いましょう。
この裏技、実は昔から農家さんの間で伝わる知恵なんです。
「へえ、先人の知恵ってすごいな」って感心しちゃいますよね。
使用済み猫砂を活用した、この意外なアライグマ対策。
「よし、これで完璧!」って自信が持てるはずです。
自然の力を借りて、しっかりとアライグマから庭を守りましょう。
ソーラーパネル付きLEDライトで「突然の明かり」に驚かせる
ソーラーパネル付きLEDライトを柵に取り付けると、夜間の突然の点灯でアライグマを驚かせることができます。これ、意外と効果的な裏技なんです。
「え、ただの明かりでいいの?」って思うかもしれません。
でも、アライグマは夜行性の動物。
突然の明るい光は、彼らにとってはビックリする出来事なんです。
この裏技、具体的にはこんな風に使います:
- 動体検知機能付きのソーラーパネルLEDライトを選ぶ
- 柵の上部や周囲に数メートル間隔で設置
- センサーの向きを庭側に調整する
- 明るさは500ルーメン以上が理想的
と明るい光が点灯。
「うわっ、まぶしい!」ってな感じで、アライグマはビックリして逃げ出すんです。
この方法のいいところは、電気代がかからないこと。
ソーラーパネルで充電するので、「毎日の電気代が気になる…」なんて心配はありません。
しかも、一度設置すれば基本的にはメンテナンスフリー。
「楽チンだな〜」って感じですよね。
ただし、注意点もあります。
近所の迷惑にならないよう、光の向きや強さには気をつけましょう。
「隣の家の寝室に光が入っちゃった!」なんてことにならないように。
この裏技、実は一石二鳥の効果があるんです。
アライグマ対策だけでなく、防犯対策にもなります。
「おっ、これは使える!」って思いませんか?
ソーラーパネル付きLEDライトを活用した、この意外なアライグマ対策。
「これで夜も安心して眠れる!」って感じではないでしょうか。
環境にも優しく、効果的な方法で、しっかりとアライグマから庭を守りましょう。
柵の周りに「ペパーミントを植える」香りの防衛線
柵の周りにペパーミントを植えるのは、アライグマ対策の中でも特に効果的な裏技です。この強い香りが、アライグマを遠ざける自然な防衛線になるんです。
「え、ただのハーブでいいの?」って思う人もいるでしょう。
でも、アライグマは実はペパーミントの香りが苦手なんです。
その強烈な香りが、彼らの敏感な鼻をくすぐって不快にさせるんです。
この裏技、具体的にはこんな風に実践します:
- 柵の内側に沿ってペパーミントを植える
- 30〜50センチ間隔で植えるのがおすすめ
- 定期的に剪定して香りを強く保つ
- 乾燥した葉を柵の周りに撒くのも効果的
「うわっ、この匂い嫌だ!」って感じで、アライグマは近寄るのを躊躇してしまいます。
この方法のいいところは、見た目にも美しいこと。
ペパーミントの緑の葉っぱが、庭の景観を良くしてくれます。
「アライグマ対策しながら、庭もきれいになるなんて!」って、一石二鳥ですよね。
ただし、注意点もあります。
ペパーミントは繁殖力が強いので、広がりすぎないように注意が必要です。
「気づいたら庭中ペパーミントだらけ!」なんてことにならないように、定期的な手入れを忘れずに。
この裏技、実は昔からハーブの効能として知られていたんです。
「へえ、昔の人の知恵ってすごいな」って感心しちゃいますよね。
ペパーミントを植えるという、この自然なアライグマ対策。
「これで庭も安全、香りも良い!」って感じじゃないでしょうか。
自然の力を借りて、優しくも効果的にアライグマから庭を守りましょう。