アライグマが天井裏に住み着く理由と対処法【暗くて安全な環境を好む】効果的な追い出し方と再侵入防止策3選

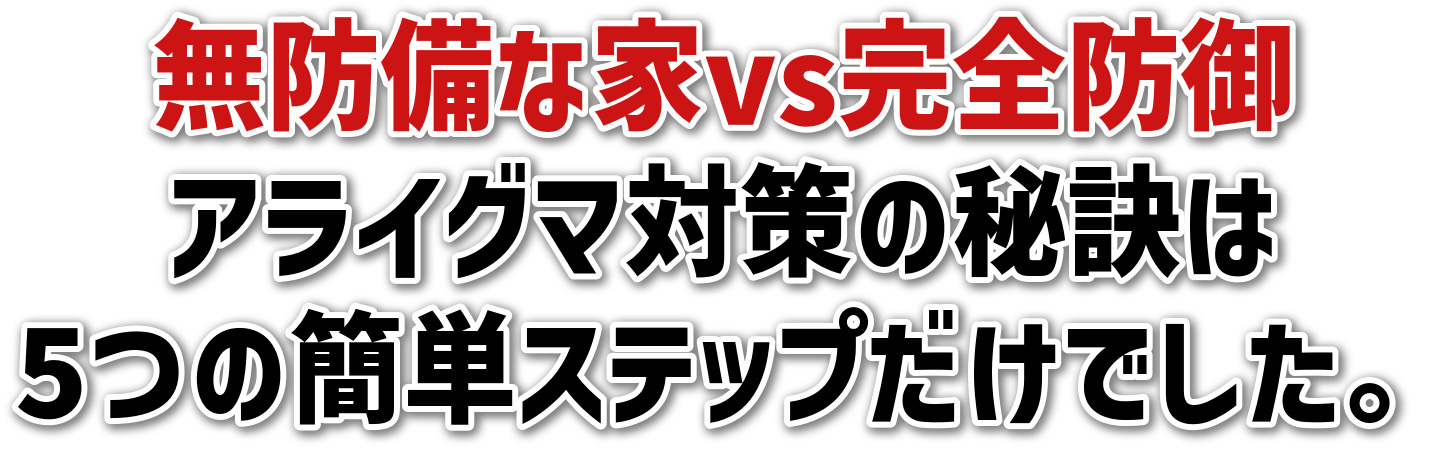
【この記事に書かれてあること】
「ガサガサ…」という不気味な物音。- アライグマは暗くて安全な環境を求めて天井裏に住み着く
- 侵入経路は屋根の破損箇所や換気口が主な原因
- 光や音、強い臭いを利用して居心地の悪い環境を作り出す
- 金属製メッシュで侵入口を完全に塞ぐことが重要
- 庭の果実や生ゴミの管理でアライグマを寄せ付けない
「臭い!」という異臭。
天井裏からするこんな気配、もしかしてアライグマ?
そう気づいた時には、もう手遅れかもしれません。
アライグマは天井裏を隠れ家として選ぶ厄介な動物なんです。
でも、大丈夫。
この記事では、アライグマが天井裏を好む理由から、効果的な追い出し方、再侵入を防ぐ方法まで、詳しく解説します。
これを読めば、あなたの家を守る具体的な対策がわかりますよ。
さあ、アライグマとの知恵比べ、始めましょう!
【もくじ】
アライグマが天井裏に住み着く理由と危険性

暗くて安全な環境!アライグマが天井裏を好む3つの理由
アライグマが天井裏を好むのは、暗くて安全な環境だからです。その魅力的な理由を3つ見ていきましょう。
まず、天井裏は暗いんです。
アライグマは夜行性の動物なので、明るい場所よりも暗い場所を好みます。
「ここなら安心して昼寝できるぞ」とアライグマは考えているでしょう。
次に、天井裏は静かです。
外の騒音から遮断されているので、アライグマにとっては落ち着ける空間なんです。
「シーン…静かで気持ちいいな」とアライグマは満足しているかもしれません。
最後に、天井裏は外敵から身を隠せる安全な場所です。
地上にいるよりも、天敵に見つかりにくいんです。
アライグマにとっては、まさに「ここは俺の城だ!」という感じでしょう。
これらの理由から、アライグマは天井裏を絶好の住処として選んでしまうのです。
その結果、以下のような問題が起こりやすくなります:
- 天井材の破損
- 糞尿による悪臭
- 夜間の騒音
- 感染症のリスク
でも心配しないでください。
後ほど、効果的な対策方法もお伝えしますよ。
アライグマの習性を理解することが、対策の第一歩なんです。
天井裏の温度と湿度がアライグマにとって「快適な環境」に
天井裏の温度と湿度は、アライグマにとって驚くほど快適な環境なんです。それはまるで、アライグマ専用のリゾートホテルのようなもの。
なぜそんなに快適なのか、詳しく見ていきましょう。
まず、温度について考えてみましょう。
天井裏は、季節を問わず比較的安定した温度が保たれています。
夏は外より涼しく、冬は外より暖かいんです。
「ここなら一年中快適に過ごせるぞ」とアライグマは喜んでいるでしょう。
湿度も、アライグマにとって理想的です。
天井裏は適度な湿度が保たれているため、アライグマの体調管理にぴったりなんです。
「カラカラに乾燥してるわけでもなく、ジメジメしてるわけでもない。ちょうどいい!」とアライグマは満足しているはずです。
この快適な環境は、アライグマにとって次のようなメリットがあります:
- 体温調節がしやすい
- 毛並みを良好に保てる
- 休息がとりやすい
- 子育てに適している
実際、人間の住宅の天井裏は、図らずもアライグマにとって理想的な環境になってしまっているんです。
だからこそ、アライグマを追い出すには、この快適な環境を不快なものに変える必要があるんです。
例えば、強い光や音を使って居心地の悪い空間にするのが効果的。
アライグマに「ここはもう快適じゃない!」と思わせることが大切なんです。
天井裏に潜む「思わぬ餌」!アライグマが長居する原因
天井裏には、私たちが思いもよらない「餌」が潜んでいるんです。これがアライグマを長居させる大きな原因になっています。
どんな餌があるのか、詳しく見ていきましょう。
まず、小さな動物たちがいます。
ネズミやコウモリ、昆虫類など、天井裏には意外と多くの生き物が住んでいるんです。
アライグマにとっては、これらが絶好の獲物になります。
「ここは天然の食料庫だ!」とアライグマは喜んでいるかもしれません。
次に、建材や断熱材も餌になることがあります。
アライグマは好奇心旺盛で、何でも口にする習性があります。
柔らかい素材は噛んだり引き裂いたりして遊ぶこともあるんです。
「この白いフワフワしたものは何だろう?食べてみよう!」なんて考えているかもしれません。
さらに、天井裏に置かれた物も餌になることがあります。
例えば:
- 古い衣類や布団
- 段ボール箱に入った食品
- 植物の種や球根
- ペットフード(天井裏に保管している場合)
アライグマは雑食性で、ありとあらゆるものを食べてしまうんです。
この「思わぬ餌」の存在が、アライグマを天井裏に長居させる大きな理由になっています。
だからこそ、アライグマを追い出すには、これらの餌源を除去することが重要なんです。
天井裏の清掃や、不要な物の撤去をすることで、アライグマにとっての魅力を減らすことができるんです。
「ガサガサ…ムシャムシャ…」という音が聞こえたら要注意。
それはきっと、天井裏のアライグマが「思わぬ餌」を楽しんでいる合図かもしれません。
早めの対策が大切ですよ。
アライグマの侵入経路!「屋根の破損箇所」に要注意
アライグマが天井裏に侵入する主な経路、それは「屋根の破損箇所」なんです。ここを見逃すと、アライグマの侵入を許してしまう可能性が高くなります。
屋根の破損箇所は、アライグマにとって絶好の侵入口になります。
例えば:
- 瓦のズレや割れ
- 軒下の隙間
- 通気口の破損
- 雨どいの接続部分の隙間
- 煙突周りの隙間
特に注意が必要なのは、台風や強風の後です。
「ゴロゴロ…ガタガタ…」という音がした後は要注意。
屋根が傷んでいる可能性が高いんです。
アライグマは「おっ、新しい入口ができたぞ!」と喜んで侵入してくるかもしれません。
また、古い家屋ほど侵入されやすい傾向があります。
経年劣化で隙間ができやすいからです。
「うちは大丈夫」と油断は禁物。
定期的な点検が欠かせません。
侵入を防ぐには、こまめな屋根の点検と修理が重要です。
でも、高所作業は危険が伴います。
「よっこらしょ…」と自分で屋根に上るのは避けましょう。
専門家に依頼するのが安全です。
屋根の破損箇所をふさぐ際は、アライグマの力強さを考慮する必要があります。
簡単な板や網では、「ガリガリ…バリバリ…」とすぐに破壊されてしまいます。
金属製のメッシュなど、丈夫な材料を使うことがポイントです。
「屋根の破損箇所」という侵入経路を知ることで、効果的な対策が打てるんです。
アライグマに「ここは入れない」と思わせる家づくりが大切なんです。
アライグマを追い出そうとするのは逆効果!危険な対処法
アライグマを見つけたら、すぐに追い出したくなりますよね。でも、ちょっと待ってください!
直接追い出そうとするのは、実は逆効果で危険なんです。
まず、アライグマは追い詰められると攻撃的になります。
「グルル…」と威嚇する声が聞こえたら要注意。
これは「近づくな!」というサインなんです。
無理に近づくと、鋭い爪や歯で攻撃されるかもしれません。
次に、アライグマは病気を媒介する可能性があります。
直接触れると、狂犬病やアライグマ回虫症などの危険な病気に感染するリスクがあるんです。
「えっ、そんな怖い病気があるの?」と驚く方も多いでしょう。
さらに、子連れの場合は特に注意が必要です。
母親のアライグマは子供を守るために、より攻撃的になります。
「ガルルル…」という低い唸り声は、最後の警告です。
危険な対処法には、他にもこんなものがあります:
- 殺鼠剤の使用(毒殺は法律で禁止されています)
- 煙で追い出す(火災の危険があります)
- 水をかけて追い出す(家屋への被害が大きくなります)
- 大きな音で驚かせる(パニックを起こし、予期せぬ行動をとる可能性があります)
安全で効果的な対処法は、専門家に相談することです。
彼らは適切な捕獲方法や、再侵入を防ぐノウハウを持っています。
自分で対処する場合は、間接的な方法を選びましょう。
例えば、光や音、臭いを使って居心地の悪い環境を作り出すんです。
アライグマに「ここはもう快適じゃない」と思わせることが大切なんです。
アライグマ対策は、焦らず慎重に。
安全第一で取り組むことが、最も効果的な方法なんです。
効果的なアライグマ対策と追い出し方法

光vs音!アライグマを追い出す効果的な方法の比較
アライグマを追い出すなら、光と音の組み合わせが効果的です。どちらがより効果的なのか、比較してみましょう。
まず、光による対策です。
アライグマは夜行性なので、強い光は大の苦手。
「まぶしっ!」とばかりに逃げ出してしまうんです。
特に、不規則に点滅するストロボライトは効果抜群。
天井裏にこれを設置すれば、アライグマは落ち着いて過ごせなくなります。
一方、音による対策も有効です。
大きな音や人の声は、アライグマに危険を感じさせます。
「ここは安全じゃない!」と思わせるわけです。
例えば、ラジオを終日つけっぱなしにするのも良い方法。
人間の声が常に聞こえる環境は、アライグマにとってストレスになるんです。
では、どちらがより効果的なのでしょうか?
実は、両方を組み合わせるのがベストなんです。
- 光だけだと、目を慣らして適応してしまう可能性がある
- 音だけだと、慣れてしまう可能性がある
- 光と音を組み合わせると、相乗効果で追い出し効果が高まる
アライグマが動くたびに「ピカッ!」と光が点き、「ガヤガヤ」と音が鳴る。
これなら、アライグマも「もうここには住めない!」と感じるはずです。
ただし、近所迷惑にならないよう、音量や光の強さには注意が必要です。
「ご近所さんに怒られちゃった…」なんてことにならないよう、適度な設定を心がけましょう。
臭いvs物理的な障害物!アライグマ撃退法の効果を検証
アライグマを撃退するなら、臭いと物理的な障害物、どちらが効果的でしょうか?両方の方法を比較してみましょう。
まず、臭いによる撃退法です。
アライグマは鋭い嗅覚を持っているので、強い臭いは効果的な撃退方法になります。
例えば、アンモニア臭のする布を天井裏に置くと、アライグマは「うわっ、臭い!」と感じて逃げ出すかもしれません。
ミントオイルや木酢液も効果があるんです。
一方、物理的な障害物による方法も有効です。
金属製のメッシュで侵入口を塞いだり、天井裏への入り口に一方通行のドアを取り付けたりするんです。
「えっ、入れない!」とアライグマも困惑するはず。
では、どちらがより効果的なのでしょうか?
実は、状況によって変わってくるんです。
- 臭いによる方法は、即効性があり、設置も簡単
- 物理的な障害物は、長期的な効果が期待できる
- 臭いは時間とともに効果が薄れる可能性がある
- 障害物は一度設置すれば、持続的な効果が得られる
例えば、まず強い臭いでアライグマを追い出し、その後すぐに侵入口を物理的に塞ぐんです。
「臭いし、入れないし、もうここには住めない!」とアライグマも諦めるはずです。
ただし、臭いを使う場合は家族や近所への影響も考慮する必要があります。
「家族が臭くて家に入れない…」なんて悲劇にならないよう、使用する場所や量には十分注意しましょう。
物理的な障害物を設置する際も、家の外観を損なわないよう配慮が必要です。
効果的な撃退には、アライグマの習性をよく理解し、状況に応じた適切な方法を選ぶことが大切なんです。
昼間の対策vs夜間の対策!時間帯別アライグマ対策の違い
アライグマ対策、昼と夜で全然違うんです。時間帯によってどう対策を変えるべきか、見ていきましょう。
まず、昼間の対策です。
アライグマは夜行性なので、昼間は主に寝ている時間。
この時間帯は、アライグマを直接追い出すのではなく、夜の活動に備えた準備をする時間です。
例えば:
- 侵入経路の点検と修理
- 庭の果実や生ゴミの片付け
- 光や音を使った装置の設置
一方、夜間の対策は全く異なります。
アライグマが活発に活動する時間なので、より積極的な対策が必要です。
例えば:
- 動体検知センサー付きライトの作動
- ラジオなどの音源を流す
- 定期的な見回り
では、どちらの時間帯の対策がより重要なのでしょうか?
実は、両方とも欠かせないんです。
昼間の準備があってこそ、夜の対策が効果を発揮する。
逆に、夜の対策があるからこそ、昼間の準備が意味を持つんです。
例えば、昼間に侵入経路を塞いでおけば、夜にアライグマが来ても「あれ?入れない!」となります。
逆に、夜に光や音で追い払っても、昼間に侵入経路を放置していれば「また来ちゃった…」ということになりかねません。
大切なのは、昼夜の対策をバランス良く行うこと。
「昼は準備、夜は実行」という感じで、24時間体制でアライグマと戦うのが効果的なんです。
ただし、夜間の対策で近所に迷惑をかけないよう、音量などには十分注意しましょう。
一時的な対策vs長期的な対策!効果の持続性を比較
アライグマ対策、一時しのぎと長期戦、どっちがいいの?両方の特徴を比べてみましょう。
まず、一時的な対策です。
これは即効性があり、すぐに効果が出ます。
例えば:
- 強い光や音を使って追い払う
- 臭いの強い物質を置く
- 人が頻繁に動き回る
でも、これらの効果は短期的。
アライグマが慣れてしまったり、対策をやめた途端に戻ってきたりする可能性があるんです。
一方、長期的な対策は効果が出るまで時間がかかりますが、持続性があります。
例えば:
- 侵入経路を完全に塞ぐ
- 庭の環境を改善し、餌源をなくす
- 近隣地域と協力して、広域的な対策を行う
では、どちらが良いのでしょうか?
実は、両方を組み合わせるのがベストなんです。
例えば、まず一時的な対策でアライグマを追い払い、その間に長期的な対策を施す。
「ピカピカ!ガヤガヤ!」と光と音で追い払いながら、侵入経路を塞いでいく感じです。
ただし、注意点もあります。
一時的な対策は近所迷惑になる可能性があるので、やりすぎには注意。
「隣の家がうるさくて眠れない!」なんて苦情が来ないよう、配慮が必要です。
長期的な対策も、費用がかかることがあるので、計画的に進めましょう。
アライグマ対策は、短期と長期のバランスが大切。
「今すぐ追い払いたい!」という気持ちはわかりますが、「二度と来ないでほしい」という願いも込めて、じっくり対策を立てていくのが賢明です。
アライグマの習性を利用!「子連れ」に注意した追い出し方
アライグマの追い出し、子連れの場合は要注意です。アライグマの習性を理解して、安全に追い出す方法を見ていきましょう。
まず、知っておくべきなのは、アライグマの子育ての特徴です。
- 春から夏にかけて出産する
- 1回の出産で2〜5匹の子どもを産む
- 子育て期間は約4ヶ月
「子どもを守るぞ!」という強い本能が働くわけです。
では、子連れのアライグマを安全に追い出すには、どうすればいいでしょうか?
まず大切なのは、直接的な接触を避けること。
母親アライグマは子どもを守るために、人間に向かってくることもあるんです。
「グルル…」という低い唸り声が聞こえたら要注意。
これは最後の警告サインです。
代わりに、間接的な方法で追い出すのが効果的です。
例えば:
- 明るい光を当て続ける
- ラジオなどの音を流し続ける
- 天井裏の温度を徐々に上げる
ただし、すぐに追い出そうとするのは危険。
子どもが小さすぎると、移動できない可能性があるからです。
「赤ちゃんを置いていかれちゃった…」なんて事態は避けたいですよね。
そこで、段階的なアプローチがおすすめです。
1. まず、アライグマの存在を確認する(子連れかどうかも)
2. 軽い不快感を与え、自主的な退去を促す
3. 徐々に不快度を上げていく
4. アライグマが完全に出て行ったことを確認してから、侵入口を塞ぐ
このように、アライグマの習性を理解し、子どもの成長に合わせた対策を取ることが大切です。
焦らず、安全第一で追い出しを行いましょう。
「そうか、アライグマにも家族があるんだ」と思えば、少し優しい気持ちで対策できるかもしれませんね。
再侵入を防ぐ!アライグマ対策の決定版

隙間を完全封鎖!「金属製メッシュ」で侵入口を塞ぐ方法
アライグマの再侵入を防ぐなら、金属製メッシュでの完全封鎖が効果的です。どうやって使うのか、詳しく見ていきましょう。
まず、なぜ金属製メッシュなのでしょうか?
それは、アライグマの鋭い歯や爪に耐えられるからです。
「ガリガリ…」と噛んでも、「ガシガシ…」と引っ掻いても、簡単には破れないんです。
では、どんなメッシュを選べばいいのでしょうか?
ポイントは3つあります。
- 材質:ステンレス製が最適
- 目の細かさ:1cm四方以下
- 強度:19ゲージ(約1mm)以上の厚さ
でも、アライグマは予想以上に力が強いんです。
中途半端な対策では、すぐに突破されちゃいます。
さて、実際の封鎖作業はどうすればいいでしょうか?
手順を追って説明します。
1. まず、家の外回りを丁寧に点検。
「あれ?ここに穴が…」というように、侵入口を全て見つけます。
2. 見つけた穴より少し大きめにメッシュを切ります。
はみ出し部分は後で折り曲げるんです。
3. メッシュを穴にあて、ステープルガンでしっかり固定。
「カチッ、カチッ」と音を立てながら、端から順に留めていきます。
4. はみ出した部分は内側に折り曲げて、さらにステープルで固定。
「これで完璧!」という仕上がりに。
作業中は安全に気をつけてくださいね。
高所作業になることもあるので、「よいしょ…」と無理はせず、必要に応じて友人や家族に手伝ってもらいましょう。
この方法で封鎖すれば、アライグマも「もう入れない…」とあきらめるはず。
家族みんなで「やったー!」と喜べる日も近いですよ。
屋根と外壁の点検!アライグマの爪痕や毛を見逃すな
アライグマの侵入を防ぐには、屋根と外壁の入念な点検が欠かせません。どんな痕跡を探せばいいのか、詳しく見ていきましょう。
まず、アライグマが残す痕跡には主に4種類あります。
- 爪痕:木材や軟らかい素材に残る引っ掻き跡
- 毛:灰色がかった茶色の毛が引っかかっている
- 足跡:泥や砂の上に残る、人の赤ちゃんの手のような形
- 糞:犬の糞に似ているが、中に種や果物の皮が混ざっている
でも、これらを見つけることで侵入経路が特定できるんです。
では、具体的にどう点検すればいいでしょうか?
手順を追って説明します。
1. まず、家の周りをゆっくり歩きます。
「キョロキョロ…」と目を凝らしながら、地面や壁の下部をチェック。
2. 次に、はしごを使って屋根に上ります。
「よいしょ…」と慎重に移動しながら、瓦のすき間や軒下を確認。
3. 特に注意すべきは換気口や煙突の周り。
「ここから入ったのかな?」と想像しながら、集中的にチェックします。
4. 見つけた痕跡は必ず写真に撮っておきましょう。
「後で見返すときに便利だな」と感じるはずです。
点検中は安全第一です。
高所作業は危険が伴うので、可能なら友人や家族に手伝ってもらいましょう。
「二人で見た方が見落としも少ないしね」という具合です。
もし、痕跡が見つからなくても油断は禁物。
夜間に観察するのも効果的です。
アライグマは夜行性なので、「カサカサ…」という音がしたら要注意。
懐中電灯を使って慎重に追跡してみましょう。
このように丁寧に点検することで、アライグマの侵入経路がわかります。
「ここを塞げば安心だ!」という対策のヒントが見つかるはずですよ。
庭の環境改善!「果実や生ゴミ」の管理でアライグマを寄せ付けない
アライグマを寄せ付けない庭づくり、それが再侵入防止の鍵です。特に気をつけたいのが「果実や生ゴミ」の管理。
どうすればいいのか、具体的に見ていきましょう。
まず、アライグマが好む食べ物を知ることが大切です。
主に次のようなものが餌になります。
- 果物(特に熟した柿やぶどう)
- 野菜(トマトやとうもろこしなど)
- 小動物(カエルや小魚)
- 生ゴミ(食べ残しや腐ったもの)
では、具体的にどう対策すればいいのでしょうか?
ポイントは3つあります。
1. 果樹の管理:落下した果実はすぐに拾います。
「今日も一個も落ちてないぞ」と毎日チェックする習慣をつけましょう。
熟しすぎる前に収穫するのも効果的です。
2. 野菜畑の保護:ネットや柵で囲みます。
「これで安心!」と思わず笑顔になるような、しっかりとした防御を。
高さは1.5m以上、地面との隙間は5cm以下が理想的です。
3. 生ゴミの適切な処理:密閉容器に入れて保管します。
「臭いが漏れてない?」と時々確認するのを忘れずに。
コンポストを使う場合は、蓋付きの丈夫なものを選びましょう。
これらの対策を行うと、アライグマは「ここには美味しいものがない」と感じて寄り付かなくなります。
さらに、庭の整備も重要です。
茂みや積み木など、隠れ場所になりそうな場所は減らしましょう。
「スッキリした庭になったな」と満足感を味わえるはずです。
こうした環境改善は、一朝一夕にはいきません。
でも、家族みんなで協力して少しずつ進めていけば、「うちの庭、アライグマ知らずだね」と胸を張れる日が来るはずです。
アライグマ対策は、実は素敵な庭づくりのチャンスなんです。
天井裏にアンモニア臭の布を設置!「強烈な臭い」で撃退
アライグマを追い出すなら、アンモニア臭の布が効果的です。その強烈な臭いで、アライグマは「ここには住めない!」と感じるんです。
なぜアンモニア臭がいいのでしょうか?
それは、アライグマの鋭敏な嗅覚を利用しているからです。
人間の約100倍も敏感な鼻を持つアライグマにとって、アンモニアの臭いは耐えられないほど強烈なんです。
では、具体的にどうやって使うのでしょうか?
手順を追って説明します。
1. まず、古いタオルや布を用意します。
「これならもう使わないな」というものでOKです。
2. 次に、アンモニア水を準備。
市販のものを薄めて使います。
「くさっ!」と思うくらいの濃さで十分です。
3. 布をアンモニア水に浸し、よく絞ります。
「ぎゅっ」としっかり絞って、滴り落ちない程度に。
4. その布を、ビニール袋に入れて天井裏に置きます。
「ここなら人間の生活に影響しないな」という場所を選びましょう。
5. 2〜3日おきに新しい布に交換します。
「まだ臭うかな?」と確認しながら、効果が続くようにケアしましょう。
ただし、注意点もあります。
アンモニアは刺激の強い物質なので、取り扱いには十分気をつけてください。
「目が痛い!」「喉がヒリヒリする!」と感じたら、すぐに換気をしましょう。
また、子どもやペットがいる家庭では、アンモニア水や臭い布に触れないよう工夫が必要です。
「触ったらダメだよ」と、しっかり説明することも大切ですね。
この方法は、即効性があるのが魅力です。
でも、長期的には他の対策と組み合わせるのがおすすめ。
「臭いだけじゃなく、侵入口も塞いじゃおう!」という具合に、総合的な対策を心がけましょう。
アンモニア臭の布、その強烈な臭いでアライグマを撃退。
「やっと静かになった!」と喜べる日も近いはずです。
超音波装置の活用!人間には聞こえない「高周波」でストレスを与える
アライグマ対策の切り札、それが超音波装置です。人間には聞こえない高い音で、アライグマに「ここは居心地が悪い!」と感じさせる優れものなんです。
なぜ超音波が効くのでしょうか?
それは、アライグマの聴覚が人間より優れているからです。
人間には聞こえない高周波でも、アライグマにはハッキリ聞こえるんです。
その音がストレスとなって、アライグマは逃げ出してしまうというわけ。
では、具体的にどう使えばいいのでしょうか?
ポイントは3つあります。
- 周波数:20〜50kHzが効果的
- 設置場所:アライグマの侵入経路や活動場所に向けて
- 使用時間:夜間を中心に、24時間稼働も可能
でも大丈夫、最近の装置は使いやすくなっているんです。
具体的な使い方を見ていきましょう。
1. まず、適切な装置を選びます。
「この周波数なら効果がありそう!」と思える製品を。
2. 次に、設置場所を決めます。
「アライグマがよく通るのはここかな?」と想像しながら、最適な場所を探しましょう。
3. 電源を入れたら、あとは装置におまかせ。
「ピー」という音が聞こえたら正常に作動しているサイン。
人間には聞こえないはずですが、もし聞こえても心配ありません。
ただし、注意点もあります。
ペットにも影響を与える可能性があるので、犬や猫を飼っている家庭では使用を控えましょう。
「ワンちゃん、変な様子ない?」と、ペットの様子をよく観察することが大切です。
また、近所迷惑にならないよう、設置場所には気を付けてください。
「隣の家に向けちゃってないかな?」と、ちょっと気にかけるだけでOK。
この超音波装置、目に見えない音でアライグマを追い払います。
「静かなのに効果抜群!」と、きっと驚くはずです。
他の対策と組み合わせれば、さらに効果的。
アライグマフリーの家を目指して、頑張りましょう!