アライグマの鳴き声と発声パターンの特徴は?【チャタリングやトリルなど多様】効果的な追い払い音の選び方3選

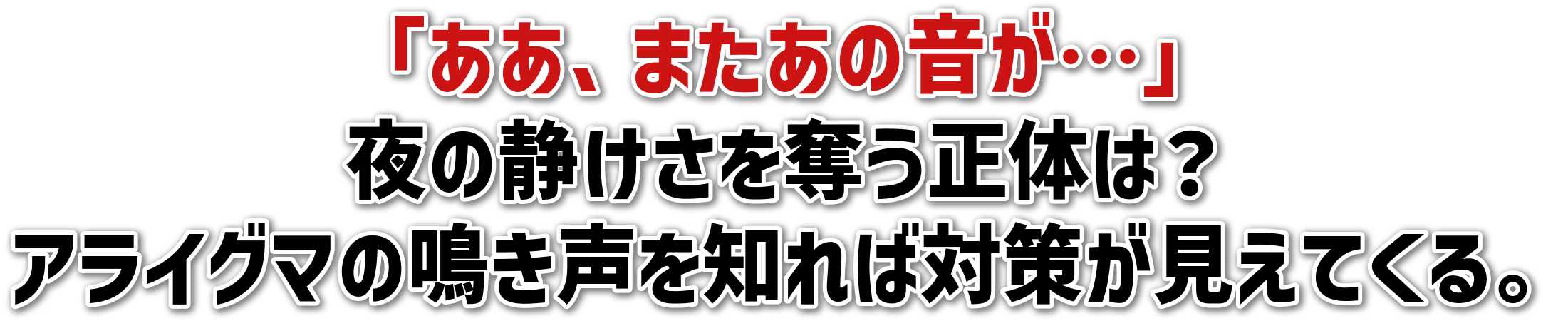
【この記事に書かれてあること】
夜中に聞こえてくる不思議な鳴き声、それはアライグマかもしれません。- アライグマの多様な鳴き声と発声パターン
- チャタリングやトリルなど特徴的な音の意味
- 夜行性に基づく鳴き声の頻度と時間帯
- 他の動物との鳴き声の聞き分け方
- アライグマの鳴き声に対する5つの効果的な対策
チャタリングやトリルなど、アライグマの鳴き声は実に多様で、その意味も状況によって変化します。
アライグマの声を理解することは、効果的な対策の第一歩なのです。
この記事では、アライグマの鳴き声と発声パターンの特徴を詳しく解説し、他の動物との聞き分け方や、騒音被害を解消する5つの対策法をご紹介します。
アライグマとの上手な付き合い方を学んで、快適な生活を取り戻しましょう。
【もくじ】
アライグマの鳴き声と発声パターンの特徴

チャタリングやトリル!多様な鳴き声の種類と意味
アライグマの鳴き声は実に多様で、状況に応じて様々な音を使い分けています。主な鳴き声には、チャタリング、トリル、スクリーム、パーがあります。
まず、チャタリングは歯をカチカチと鳴らす音です。
「カチカチカチ」という感じですね。
これは警戒や威嚇の意味を持っています。
「近づくなよ!」というメッセージなんです。
次にトリルは、鳥のさえずりのような音で、「ピルルルル」と聞こえます。
これは主に母親が子どもを呼ぶときに使う優しい声なんです。
「こっちにおいで〜」という感じでしょうか。
スクリームは高音で甲高い悲鳴です。
「キーッ!」という感じで、痛みや恐怖を感じたときに発します。
「助けて〜!」という叫びだと思ってください。
最後にパーは、「プルル」という短い音で、リラックスしているときや仲間を呼ぶときに使います。
「元気〜?」「一緒に遊ぼう!」といった友好的な意味合いです。
- チャタリング:警戒や威嚇
- トリル:母親が子どもを呼ぶ
- スクリーム:痛みや恐怖の表現
- パー:リラックスや仲間を呼ぶ
「あ、今のはチャタリングだ。警戒しているんだな」なんて、アライグマの行動を予測できるようになりますよ。
夜行性のアライグマ!発声の頻度と時間帯の特徴
アライグマは夜行性の動物です。そのため、鳴き声も主に夜間に聞こえることが多いんです。
日没後から明け方にかけて、最も活発に鳴く傾向があります。
発声の頻度は、季節によっても変化します。
特に春から夏にかけての繁殖期には、鳴き声の頻度が格段に増加します。
「ピルルルル」というトリルの音が、夜中にあちこちから聞こえてくるなんてことも。
「うわぁ、アライグマたちの婚活シーズンかな?」なんて思っちゃいますね。
一晩の鳴き声の頻度は、個体差や状況によってさまざまです。
しかし、数分おきに断続的に鳴くこともあります。
特に、縄張り争いや繁殖活動が活発な時期には、鳴き声が頻繁に聞こえるようになります。
- 主な活動時間:日没後〜明け方
- 鳴き声が増える季節:春〜夏(繁殖期)
- 一晩の鳴き声頻度:状況により数分おき
「あ、今日もアライグマさんたち、元気に活動中だな」なんて、ちょっと自然観察気分も味わえちゃいますよ。
でも、頻繁な鳴き声は睡眠の妨げにもなりかねません。
アライグマの活動が活発な時期には、防音対策を考えることも大切です。
窓を二重にしたり、耳栓を使ったりするのも一つの手段ですね。
猫やタヌキとの聞き分け方「決定的な違い」に注目
アライグマの鳴き声は、時として猫やタヌキの声と間違えられることがあります。でも、よく聞くと決定的な違いがあるんです。
まず、猫との違いです。
アライグマの高音のスクリームは、確かに猫の鳴き声に似ています。
でも、アライグマの方がより甲高く、持続時間が短いんです。
猫の「ニャーオーン」が長く伸びるのに対し、アライグマは「キーッ」と短く鋭い感じ。
「あれ?猫にしては短すぎるな」と思ったら、アライグマかもしれません。
次に、タヌキとの違いです。
タヌキは「キャンキャン」と鳴きますが、アライグマはもっと多様で複雑な鳴き声を出します。
タヌキの声が単調なのに対し、アライグマは「カチカチ」「ピルルルル」「プルル」と、まるで楽器を演奏しているかのよう。
「なんだか色んな音が聞こえるな」と思ったら、アライグマの可能性が高いです。
- 猫との違い:より甲高く、持続時間が短い
- タヌキとの違い:多様で複雑な鳴き声
- アライグマの特徴:様々な音を組み合わせる
単調な鳴き声ならタヌキや猫の可能性が高いですが、色んな音が組み合わさっていたら、それはアライグマかもしれません。
また、鳴き声の時間帯も大切なヒントです。
夜中に頻繁に聞こえる場合は、夜行性のアライグマの可能性が高くなります。
「夜中にいろんな音がするな」なんて思ったら、アライグマが近くにいるサインかもしれませんよ。
アライグマの鳴き声対策は「やってはいけない」NG行動に注意
アライグマの鳴き声に悩まされたとき、つい過剰な対応をしてしまいがちです。でも、ちょっと待って!
いくつかの行動は逆効果になることがあるんです。
まず、絶対にやってはいけないのが、大声で怒鳴ったり物を投げつけたりすること。
「うるさい!」って怒鳴っても、アライグマにはその意味が伝わりません。
むしろ威嚇されたと勘違いして、より攻撃的になる可能性があるんです。
「人間が怖いぞ!」とアライグマを刺激してしまうかもしれません。
また、エサを与えて黙らせようとするのも大きな間違い。
一時的に静かになっても、結局はアライグマを引き寄せてしまい、長期的には問題を悪化させてしまいます。
「おいしいものがあるぞ!」とアライグマ仲間に知らせてしまうようなものです。
では、どうすればいいのでしょうか?
ここで効果的な対策をいくつか紹介します。
- 録音した鳴き声を再生する(縄張り意識を刺激)
- レモンやユーカリの香りを使う(強い香りが苦手)
- 風鈴を設置する(音に敏感な習性を利用)
- 動体検知センサー付きLEDライトを設置する(光を嫌う特性を活用)
- 二重窓で防音対策をする(鳴き声の侵入を遮断)
「やさしく賢く対策」が、アライグマ対策の鉄則です。
根気強く続けることで、徐々に効果が表れてきますよ。
アライグマの鳴き声から読み取る行動パターン

警戒心の表れ?チャタリングvsスクリーム「意味の違い」
アライグマの鳴き声には、チャタリングとスクリームという二つの特徴的な音があります。これらの鳴き声には、全く異なる意味が込められているんです。
まず、チャタリング。
これは「カチカチカチ」と歯を鳴らす音で、警戒心や威嚇の表れなんです。
「近づくな!」というメッセージですね。
例えば、あなたが庭でアライグマと鉢合わせしたとき、こんな音が聞こえたら要注意です。
「うわっ、怒ってる?」なんて思うかもしれません。
一方、スクリームは全然違う意味を持っています。
これは高音で甲高い悲鳴で、痛みや恐怖を感じたときに発する音なんです。
「キーッ!」という感じですね。
例えば、アライグマが罠にかかってしまったときなんかに聞こえる可能性があります。
この二つの鳴き声の違いを知ることで、アライグマの状態をより正確に把握できるんです。
- チャタリング:警戒、威嚇の表れ
- スクリーム:痛み、恐怖の表現
- チャタリングを聞いたら接近に注意
- スクリームを聞いたら何か問題が起きている可能性あり
「チャタリングが聞こえたら、そっと離れよう」「スクリームが聞こえたら、何か問題が起きているかも」なんて具合に、状況に応じた対応ができるようになるんです。
繁殖期の鳴き声vs非繁殖期の鳴き声「頻度の差」に注目
アライグマの鳴き声は、季節によって大きく変化します。特に繁殖期と非繁殖期では、鳴き声の頻度に明確な違いが見られるんです。
繁殖期は主に春から夏にかけて。
この時期、アライグマたちは恋の季節真っ盛り!
鳴き声の頻度がグッと増えます。
特に夜間、「ピルルルル」というトリルの音が頻繁に聞こえるようになります。
これは主に母親が子どもを呼ぶ声なんですが、恋人探しの合図にもなっているんです。
「ねえねえ、そこのイケメンアライグマさん!」なんて呼びかけているみたいですね。
一方、非繁殖期はどうでしょう。
秋から冬にかけては、鳴き声の頻度がぐっと減ります。
静かな夜が戻ってくるんです。
でも、完全に鳴き止むわけではありません。
食べ物を探したり、縄張りを守ったりするために、時々鳴き声を上げることがあります。
この頻度の差を知ることで、アライグマの生態をより深く理解できるんです。
- 繁殖期(春〜夏):鳴き声の頻度が増加
- 非繁殖期(秋〜冬):鳴き声の頻度が減少
- 繁殖期はトリルの音が特に増える
- 非繁殖期も完全に無音になるわけではない
逆に「急に静かになったな」と思ったら、非繁殖期に入ったのかもしれません。
こんな風に、鳴き声の頻度から季節の変化を感じ取ることができるんです。
面白いですよね。
単独行動時vs群れ行動時「鳴き声の変化」を見逃すな
アライグマの鳴き声は、単独で行動しているときと群れで行動しているときで、大きく変化します。この違いを知ることで、アライグマの行動パターンをより正確に把握できるんです。
単独行動時、アライグマの鳴き声は比較的シンプル。
主に警戒や威嚇を表すチャタリング(カチカチという歯を鳴らす音)が中心です。
例えば、庭に一匹のアライグマが現れたとき、「カチカチカチ」という音が聞こえたら、それは「近づくな!」というメッセージ。
「おっと、一匹で警戒してるな」なんて感じですね。
一方、群れで行動しているときは様子が変わります。
特に母親と子どもたちの群れでは、鳴き声のレパートリーが豊かになります。
トリル(ピルルルルという鳥のさえずりのような音)やパー(プルルという短い音)が頻繁に聞こえるようになります。
これらは主にコミュニケーションのための声。
「こっちにおいで〜」「大丈夫?」なんてやり取りをしているんです。
- 単独行動時:主にチャタリングを使用
- 群れ行動時:トリルやパーなど多様な鳴き声を使用
- 単独時は警戒や威嚇が中心
- 群れでは豊かなコミュニケーションを展開
「あれ?いろんな鳴き声が聞こえるぞ」と思ったら、それは群れがいる証拠かもしれません。
逆に「カチカチという音だけだな」と感じたら、単独行動のアライグマがいる可能性が高いです。
こんな風に、鳴き声の変化を観察することで、アライグマの行動パターンが見えてくるんです。
面白いですよね。
アライグマの鳴き声と天候の関係「雨の日は要注意」
アライグマの鳴き声は、実は天候と深い関係があるんです。特に雨の日は要注意!
鳴き声の頻度や種類が大きく変化することがあります。
晴れた日、アライグマたちは比較的静か。
外で食べ物を探したり、のんびり過ごしたりしているので、鳴き声もそれほど多くありません。
でも、雨が降り出すと状況が一変!
雨の日、アライグマたちは屋内に避難しようとします。
そのため、家の屋根裏や軒下などに集まってくることが多いんです。
すると、狭い空間に複数のアライグマが集まることになり、鳴き声が増えるんです。
「ピルルルル」「プルル」「カチカチカチ」なんて、いろんな音が聞こえてきます。
まるでアライグマたちのおしゃべりパーティーみたい!
特に大雨の日は要注意です。
普段は外で生活しているアライグマたちが、一斉に屋内避難を始めます。
そうなると、縄張り争いが起きたり、子育て中の母親が警戒したりして、鳴き声がより激しくなることがあるんです。
- 晴れの日:比較的静か
- 雨の日:鳴き声が増加
- 大雨の日:特に鳴き声が激しくなる可能性あり
- 屋根裏や軒下に注意
これは、アライグマたちが避難してきた証拠かもしれません。
雨の日に備えて、家の隙間を塞いだり、屋根裏の点検をしたりするのが効果的です。
アライグマたちの雨宿りパーティーを未然に防ぐことができますよ。
天気予報をチェックして、雨の日の対策を立てておくのがおすすめです。
アライグマの鳴き声対策と防音テクニック

録音した鳴き声の再生で「縄張り意識」を刺激!追い払い効果
アライグマの鳴き声を録音して再生するという、ちょっと変わった対策方法があるんです。これが意外と効果的なんですよ。
アライグマって、縄張り意識がとても強い動物なんです。
自分の縄張りに他のアライグマが入ってくるのを嫌がります。
そこで、アライグマの鳴き声を録音して、スピーカーで再生するんです。
「ん?ここに他のアライグマがいるのか?」とびっくりして、逃げ出すことがあるんです。
でも、ちょっと注意が必要です。
録音する鳴き声は、威嚇音がいいでしょう。
例えば、「カチカチカチ」というチャタリング音がおすすめです。
「ここは危険だぞ!」というメッセージになるんです。
この方法のいいところは、こんな感じです。
- 人間にはあまり気にならない音で追い払える
- 電気代以外のコストがほとんどかからない
- アライグマにストレスを与えすぎない
- 24時間稼働させられる
「あ、この音は本物のアライグマじゃないな」と気づかれちゃうかもしれません。
そこで、再生場所や音量、タイミングを時々変えるのがコツです。
この方法で、アライグマたちに「ここは危険な場所だ」と思わせることができれば、自然と寄り付かなくなるんです。
優しく賢く、アライグマを追い払う。
そんな対策、素敵じゃないですか?
レモンやユーカリの香りで「鼻を刺激」アライグマを寄せ付けない
アライグマって、実は鼻がとっても敏感なんです。そこで、強い香りを使ってアライグマを寄せ付けない方法があります。
特に効果的なのが、レモンやユーカリの香り。
これらの香りは、アライグマにとっては「うわ、くさい!」と感じるみたいなんです。
具体的な方法としては、レモンやユーカリの精油を布に染み込ませて、アライグマが来そうな場所に置くんです。
例えば、庭の入り口や、家の周りに置いてみてください。
「うっ、この匂い苦手」って、アライグマが近づかなくなるんです。
この方法のいいところは、こんな感じです。
- 人間にとっては良い香りなので快適
- 化学物質を使わないので環境にやさしい
- アライグマに危害を加えない
- 比較的安価で手に入る
雨が降ったり、風が強かったりすると、香りが飛んでしまうことがあります。
そのため、定期的に香りをつけ直す必要があります。
「あれ?香りが薄くなってきたかな」と思ったら、すぐに補充しましょう。
また、家の中に置く場合は、ペットや小さな子供がいる家庭では注意が必要です。
精油の中には、ペットや子供にとって刺激が強すぎるものもあるからです。
「うちの猫、くしゃみをしてるぞ」なんてことにならないよう、適量を守りましょう。
この方法を使えば、アライグマに「ここは居心地が悪い場所だな」と思わせることができます。
人間にとっては良い香りで、アライグマには「お断り」の香り。
これって、素敵な共存の形じゃないですか?
風鈴の設置で「音に敏感な習性」を利用!侵入を防ぐ
風鈴を使ってアライグマを追い払う?意外に思えるかもしれませんが、これが結構効果的なんです。
アライグマって、実はとっても音に敏感な動物なんです。
特に、予期せぬ音にはビックリしやすい性質があります。
そこで登場するのが風鈴。
風が吹くたびに「チリンチリン」と鳴る風鈴の音は、アライグマにとっては「何だこの音は?」と警戒心を抱かせる原因になるんです。
まるで、アライグマ用の警報装置みたいですね。
風鈴を使う際のポイントは、こんな感じです。
- 玄関や窓際など、アライグマが侵入しそうな場所に設置する
- 複数の風鈴を使って、音の変化をつける
- 金属製の風鈴を選ぶ(より鋭い音が出るため)
- 定期的に位置を変えて、慣れを防ぐ
「チリンチリン」という涼しげな音を聞きながら、アライグマ対策ができるなんて、一石二鳥ですよね。
ただし、注意点もあります。
風の弱い日はあまり効果が期待できません。
そんな時は、扇風機などを使って風を起こすのも一つの手です。
「今日は風がないな。よし、扇風機で風鈴を鳴らそう!」なんて工夫をしてみてください。
また、近所迷惑にならないよう、音量には気をつけましょう。
「隣の家の風鈴がうるさくて眠れない」なんて苦情が来たら大変です。
適度な音量で、人間もアライグマも、お互いに心地よい環境を作りましょう。
動体検知センサー付きLEDライトで「光を嫌う特性」を活用
アライグマは夜行性で、暗いところを好む動物です。そんなアライグマの特性を逆手に取った対策が、動体検知センサー付きのLEDライトなんです。
これが意外と効果的なんですよ。
仕組みはとってもシンプル。
アライグマが近づいてくると、センサーが反応して突然明るいライトが点灯します。
「うわっ、まぶしい!」とアライグマはびっくり。
そして、「ここは危険だ」と感じて逃げ出すんです。
まるで、アライグマ専用の防犯ライトみたいですね。
この方法の良いところは、こんな感じです。
- 電気代が節約できる(必要な時だけ点灯するため)
- 設置が簡単(コンセントに差し込むだけ)
- 人間の安全対策にもなる
- 昼間は目立たないので景観を損なわない
ライトの向きや明るさには気をつけましょう。
近所の家に光が入ってしまうと、「隣の家のライトがまぶしくて眠れない」なんて苦情が来るかもしれません。
アライグマだけでなく、人間にも優しい設置を心がけましょう。
また、アライグマが慣れてしまう可能性もあります。
そこで、ライトの位置や点灯パターンを時々変えるのがコツです。
「今日はこっち、明日はあっち」なんて具合に、アライグマを油断させないようにしましょう。
この方法を使えば、アライグマに「ここは明るくて危険な場所だ」と思わせることができます。
人間にとっては安全、アライグマにとっては不快。
こんな風に、お互いの特性を理解し合いながら共存する。
それって、素敵な関係じゃないですか?
二重窓の設置で「鳴き声の侵入」を遮断!快適な睡眠環境に
アライグマの鳴き声って、意外とうるさいんです。特に夜中に「キーッ」とか「カチカチカチ」という音が聞こえてくると、ぐっすり眠れなくなっちゃいますよね。
そんな時の強い味方が、二重窓なんです。
二重窓は、文字通り窓を二重にする仕組み。
外側の窓と内側の窓の間に空気層ができて、音を遮断する効果があるんです。
まるで、家全体にイヤーマフをつけるようなものですね。
この方法のいいところは、こんな感じです。
- アライグマの鳴き声を大幅に軽減できる
- 冷暖房効率が上がり、光熱費の節約になる
- 防犯効果も期待できる
- 結露の防止にも役立つ
まず、設置費用がかかります。
「えっ、こんなにするの?」と驚くかもしれません。
でも、長期的に見れば快適な睡眠環境と省エネ効果で元は取れるはず。
投資だと思って前向きに考えましょう。
また、完全に音を遮断するわけではありません。
特に、窓を開けている時は効果が薄れます。
「暑いから窓を開けたいけど、アライグマの声も聞こえちゃう」なんてジレンマに陥ることもあるかもしれません。
そんな時は、網戸にも注目。
音を遮る特殊な網戸もあるんです。
二重窓を設置すれば、アライグマの鳴き声を気にせずぐっすり眠れるようになります。
朝起きた時、「あれ?昨日はアライグマの声聞こえなかったな」なんて感じるかも。
快適な睡眠環境で、心も体もリフレッシュ。
アライグマとの平和な共存、始まりますよ。